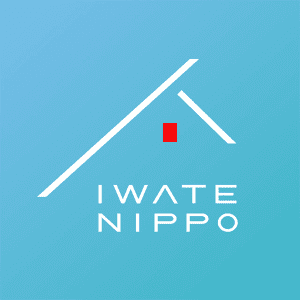東日本大震災と東京電力福島第1原発事故から13年2カ月たった今も、被ばく後に生きる牛がいる。政府や福島県が進める殺処分をよしとせず、出荷できぬ「家族」の命をつなぐ畜産農家がいる。第1原発から半径20キロ圏内の、かつての警戒区域。時を経て、放牧地だった場所には息絶えた牛が埋められる。岩手大や北里大の研究者は長期的な低線量被ばくの影響を検証するため、現地を訪ね続ける。調査に11、12の両日同行し、福島の今と人々の思いに触れた。
青草がそよ風に揺れ、土の香りが漂う。原発から北西約10キロに位置する、浪江町の小丸共同牧場に11日、線量計や青い防護服、長靴を身に着けて入った。全域が原則立ち入り禁止の「帰還困難区域」で、除染のめどは立っていない。
「生活を支えてくれた牛は、守らなければならない家族。殺処分には反対です。住民が帰ってくる気力がなくならないよう、農地や景観の保全に役立てたい」。震災前まで和牛の繁殖を営み、同牧場の代表を務める渡部典一(わたなべふみかず)さん(65)が牛の毛並みを整えながら、優しく語った。