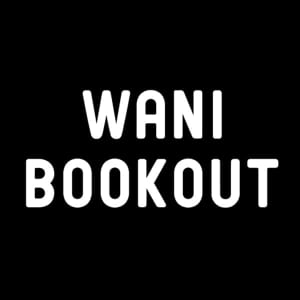フランスの地方都市ナントで、フランス人パートナーと2人の子と家族4人で暮らしている大畑典子さん。
一級建築士の資格を持ち日本の建築事務所でバリバリと働いていた彼女が渡仏して約8年。
「シンプルな暮らし」を楽しむフランス生活で得たもの、捨てたものを、日々つれづれに綴っていただきます。
渡仏後3ヵ月経って感じた精神的な「疲れ」
皆さん、いかがお過ごしでしょうか。
フランスの地方都市、ナント在住の大畑典子です。
新年度が始まり、約1ヵ月半が経ちました。「五月病」という言葉があるように、新しい環境に慣れ始めたこの時期は、精神的な疲れが出やすくなりますよね。今回は、私が留学生時代になった「五月病」の経験についてお話ししたいと思います。
日本とは生活習慣がだいぶ違うフランスでの生活に馴染むにはそれなりに時間がかかるもので、私が症状を感じたのは、渡仏後3~4ヵ月経ったころからです。
フランスの新年度は9月始まりですので、一年目の冬、12月ごろになり、徐々に精神的な不安を徐々に感じるようになったのです。

△12月のナント朝空、朝9時でやっとこの明るさ。
フランスの冬は日照時間が日本と比べて短いので、それも精神的にこたえました。太陽がこんなにも気持ちを左右するなんて、フランスに来るまでは気付きもしませんでした。冬の間は、日の出が朝の8時半過ぎになることもあるので、真っ暗な中起きて一日を始めなければいけません。旅行で過ごす程度の期間の滞在だったら耐えられるかもしれませんが、これが何ヵ月も続くと徐々に気持ちが落ち込んでいくのです。新しい海外生活での精神的な疲れと、この日照問題が相まって、フランスの留学一年目の半年〜一年くらいはとてもつらかったのを、昨日のことのように覚えています。
それに加えて、フランスの大学院生はそのほとんどが学部からストレートに上がってくる子達なので、年齢は二十歳前後。29歳で留学した私は、彼らとのジェネレーションギャップにも悩まされました。意地悪な発言をしてくる人もいましたが、せっかくフランスに来たのだからたくさんの事を吸収しなくちゃ、と自分を奮い立たせて色んな人とランチに行ったり、頑張って彼らとの生活に馴染もうと必死だったのです。
父の死をきっかけに学んだ「手放す」ことの重要性
フランスに来て半年が過ぎたころのことです。ある日、突然日本の家族から電話がありました。父が急死したのです。まだ62歳でした。急いで日本へ帰り、父の葬儀や事務処理に追われ、とても悲しむ暇もありませんでした。
でも諸々の法的な手続きがあらかた終わり、フランスでの日常生活に戻った途端、突然の喪失感、今までとは比較にならないほどの精神的な落ち込みに襲われたのです。今までの海外生活で積もりに積もったストレスが父の死をきっかけに爆発したようでした。
突然涙がでては、なぜ自分は大切な家族と離れてフランス生活を送っているのだろう、家族に何かあってもすぐに駆けつけられないこの遠い土地で生活を続ける意義はどこにあるのだろう、今していることに何の意味があるのだろう、と虚無感に苦しめられていました。
それまでは、フランスに早く馴染めるように居心地が悪くても無理をして現地の学生と出来るだけ一緒に過ごすような生活をしてましたが、父の死をきっかけに「なぜ私は、自分のことをリスペクトをしてくれない人と仲良くする努力をしているんだろう」と疑問を持つようになり、この人間関係を手放すことに決めました。
仲良くなる人は自然に仲良くなるし、無理をして自分の気持ちに蓋をしてまで一緒に時間を過ごす必要なんてないんじゃないかと思うことができたのです。

△フランス一年目のつらい時期にロンドンから旧友が遊びに来てくれた時の一枚。
それから、食生活も改めるようになりました。それまではせっかくフランスに来たのだからと、出来るだけ現地のものを食べるようにしていました。フランスの食事と言えば、バターやチーズなど、カロリーが高く脂質の多いものが中心なのですが、思い切ってフランス料理を中心とした食生活をやめました。
そして、食べ慣れていた和食中心の食事に徐々にシフトさせていったのです。
食習慣を整え、無理をしていた人間関係を手放し始めると、不思議なことに、今まで感じていた不安感が徐々になくなっていくことに気づいたのです。心と体はつながっているとはよく言ったものですよね。
このフランス一年目の冬は、私の人生にとっても大変つらい時期でしたが、無理していることを手放す大切さ、そして心が元気になる食生活の大切さを気づかせてくれたのです。
皆さんも、ご自身の心の声に耳を傾けて無理していることを少しずつ手放してみませんか。
それではまた次回、アビアント〜!
*次回は5月29日(水)更新予定です。