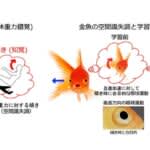
中部大学大学院の田所慎氏らの研究グループは、方向感覚を失う空間識失調が人と同様に金魚でも発症することを発見し、短時間の訓練で解消できることを確認した。航空機事故や転倒防止など人への応用が期待される。
航空機などで操縦者が自分や操縦機の姿勢、位置、運動状態(方向、速度、回転)などの空間識を客観的に把握できなくなった状態を空間識失調と呼ぶ。航空機事故の原因の約3割はこの空間識失調という統計データがある。航空機の操縦士に限らず、一般の人の乗り物酔いも空間識失調に起因すると考えられている。
原因は耳の中にある加速度センサーである耳石器(内耳にある器官)が並進運動の加速と重力に対する傾斜を区別できなくなるためと考えられている。しかし、空間識失調発症の詳細な神経メカニズムは不明であり、有効な発症防止法も未知である。
研究グループは今回、金魚に並進と傾き運動、視覚刺激を与えるシステムを開発。人と同様の空間識失調が生じることを、前庭動眼反射と呼ばれる反射的な目の動きを評価することにより発見した。
さらに 3 時間以内の視覚と並進運動を協調させる訓練を実施した結果、空間識失調が解消されることを確認した。またこの空間識失調と解消過程を再現する数理モデルを構築し、脳内での空間識形成過程の計算理論も提案した。
前庭動眼反射は運動時の視野安定化を実現する生存上重要な眼球運動であり、脳内で形成される空間識を反映し、人と金魚ではその神経メカニズムに高い類似性があることが知られている。今回の成果が、航空機操縦士の空間識失調防止や、一般の人の不安定な視野に起因する転倒や乗り物酔い防止に役立つことが期待されるとしている。
論文情報:

