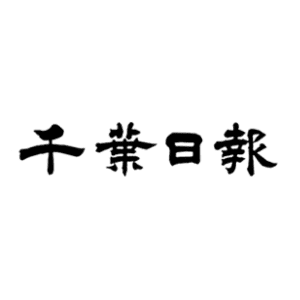「子どもと良好な関係を築くには、もちろん、愛して、認めることが大切ですが、これを実践するというのは大変です」と語るのは、千葉市で長年、私塾・フリークスールを運営してきた千葉日報カルチャー講師の古山明男さん(千葉市教育機会確保の会代表)。全国で不登校の児童生徒が急増する中、親や教師が気を付けるべき点として、まずは「子どもが言われて、少し『嫌だな』と思う言葉を言わないことが大切」と訴えています。(ちばとぴ!タウン=千葉日報カルチャーチャンネル)
文部科学省によると、2022年度の不登校児童・生徒数は約29万9千人(前年度比22.1%増)で過去最多。10年連続で増加しています。
教育相談などを長年、続けてきた古山さんは、言われて嫌な言葉の一つとして、「気を付けてね」という言葉を挙げています。
「例えば自分が車を運転しているとして、出掛ける際に『気を付けてね』と声を掛けられると、僕の運転が信用できないのかなと少し思ってしまう。子どもだってそうです」と古山さん。
「気を付けてね」には「信用できない」という意味がこもってしまう上、これだけだと、「何に気を付けていいのか分からない」という問題もあるのだといいいます。
◆本当に危ない時は… とはいえ、例えば、子どもが木の上の方まで登ってしまうなど、本当に危ない時もありますよね。
そういった時に突然、「気を付けてね」と言われると、かえって緊張してしまうこともあることから、こうした時は「すごいね。でもね、もう降りておいで、大丈夫だからね」などと、信頼していることが相手に伝わる言い方をした方がいいのではないか、と古山さんは語っています。
古山さんは他にも、こうした「言われて少し嫌になる言葉」について、オンライン講座で解説しています。