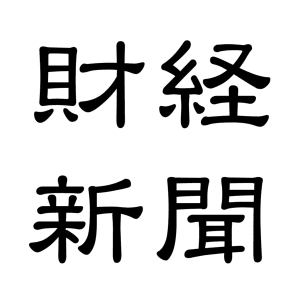これまでの火星探査により、約30億年前の堆積層調査が実施されている。当時の火星環境は現在と異なり、液体の水が存在することが判明し、併せて有機化合物の堆積物の存在も確認された。これが生命由来であれば、画期的な発見に繋がることは間違いない。
東京工業大学は13日、火星誕生初期の堆積有機化合物の炭素同位体(炭素13)構成比に着目し、これが生物由来なのか否かについて、実験と理論計算により推定を試みた結果を発表した。
研究によれば、火星誕生初期の堆積有機化合物の炭素13構成比率は、0.92%~0.99%で、同年代の地球の構成比率である1.04%と比べて著しく低い。
地球の堆積有機化合物が示した値は、それが生命由来であることを示す。だが火星のそれは生命由来ではなく、火山活動などを通して大気に流入した二酸化炭素のうち、最大で20%がCOを経由して炭素13同位体異常をもつ有機物に変換された結果だ。このCOが地表に堆積していたことが、同位体分別の実験結果とモデル計算による初期火星炭素循環の解析により判明したという。
通常自然界に存在する炭素は、質量数12の炭素12がほとんどで、この炭素12よりも原子核内に中性子が1個だけ多い同位体である炭素13の存在比率は、極めて少ない。
地球大気中の二酸化炭素における炭素13の構成比率は1.07%、生命由来の有機化合物における構成比率は1.04%、隕石中の有機化合物における構成比率はおよそ1.05%だが、火星の古代堆積有機化合物が示した値は、これらとは著しく異なっていた。
火星や地球のような岩石惑星大気中の炭素13の構成比率は、著しく低い。地球ではその後、大気を原料として生命活動により生成された大気中での炭素13の比率が高めとなったが、火星では生命活動が起こらず、炭素13の比率が低い値のままだったという結論だ。
この結論は、火星での生命誕生に期待がかかっていただけにやや残念だが、30億年前の地球環境と火星環境の違いが明確になった事実は、大変貴重で今後の生命誕生の謎解明にも役立ちそうだ。
なお今回の研究は、東京工業大学の上野雄一郎教授とコペンハーゲン大学のMatthew Johnson教授らの研究チームにより実施され、その成果は、英国科学雑誌「Nature Geoscience」に5月9日付けでオンライン掲載されている。