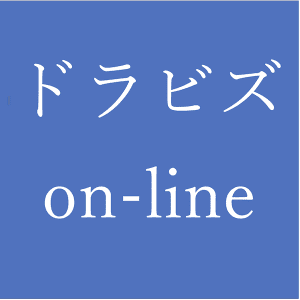【2024.05.16配信】厚生労働省は5月16日、次期薬機法改正について議論する厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会を開催した。
次期薬機法改正のテーマに関しては、これまで「医薬品の販売制度に関する検討会」で議論を重ねてきた。検討会は2023年2月から12月にかけて計11回開催され、2024年1月には「とりまとめ」を公表していた。
1つの大きなテーマとして、社会問題化している市販薬の濫用があり、医薬品の販売制度の観点からもどのような見直しができるか議論されてきた。濫用の対象となりやすい「濫用のおそれのある医薬品」については、「とりまとめ」の中で「直接購入者の手の届く場所に陳列しないこととする」とされた。
これに対し、日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)は、「現在想定されている濫用等のおそれのある医薬品は市場に約1500品目あり、販売現場においてはそのうち約250~400品目をそれぞれ採用して棚に陳列している」とし、店頭の空箱陳列などは非現実的だと反対の意見を表明した。意見書の中で、「そのすべてを空箱にして購入者が店頭で現品を触ることができないようにすることは現実的ではなく、適正使用者のアクセスを過度に阻害します。すなわち、現品をバックヤードに保管する場合は、購入者が希望する商品を購入の都度、取りに行くことが求められます。また、鍵付き什器を設置する場合は、その設置場所の確保およびその什器設置の費用等の負担が生じます。販売店にかかるこれらの負担は、限りなく実現不可能です」とした。
検討会での改正の方向に反対するのであれば、JACDSはどのような制度の見直しができると考えているのだろうか。JACDSは意見書の中で、「JACDSとしては現行法の規制を強化して、購入者が対象医薬品を手に取って購入しようとする際などに薬剤師等が対象医薬品の販売コーナーやレジ等において適切に販売に関与することで、薬剤師等による情報提供や声掛けの実効性は高まると考えております」としている。
ここには具体的な“規制強化”の内容は描かれていないが、参考人として出席したJACDS理事の森信氏は、「濫用のおそれのある医薬品全てに7m以内の医薬品コーナーに資格者がいるということにはなっていないのが現状。ここにいるようにすることを宣言する」と述べた。すなわち、手の届かない場所の陳列は反対するが、医薬品コーナーから7m以内に陳列し、その医薬品コーナーに資格者がいるようにすることで目が届くようにし情報提供、声かけを徹底するということだろうか。
この提案に対し、日本薬剤師会副会長の森昌平氏は、「陳列に関しては、情報提供や声かけを確実にするために、とりまとめでは直接購入者の手の届く場所に陳列しないこととした」とし、JACDSの提案では不十分ではないかとの見方を示した。「実効性が心配。声掛けはこれまで取り組んできた。そういう中でこれだけ濫用が起きているということは改めて見直すべきではないか」と述べた。
認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長の山口育子氏も、「万引き対策はどのように考えているのか」と疑問を呈した。市販薬の濫用では万引きなど不適正な入手方法も指摘されており、検討会ではその防止のためにも「手の届かない場所の陳列」でまとまった経緯がある。
これに 対し、JACDSの森氏はタグやセンサーなどの万引き防止策はあり得るとの見方を示した。ただ、総合感冒薬の1つ1つにタグをつけるのは大変でもあるとし、「今日すぐとはいえない」とした。
JACDS森氏のいう、「濫用のおそれのある医薬品全てに7m以内の医薬品コーナーに資格者がいるということにはなっていないのが現状」とは、どういう意味なのか。
濫用のおそれのある医薬品のリスク分類はまたがっているが、多くが指定第2類だ。その指定第2類の販売方法としては「情報提供設備」から7m以内の陳列が求められている。情報提供設備については、相談カウンターなど薬剤師等と客が対面で情報提供を行なうことができる、通常動かすことのできないものとの規定があるが、肝心の薬剤師等がその設備に常駐していることなどは規定がないので、そのようになっていないという意味に解せる。
この実態には疑問が生じる部分もある。そもそも一般用医薬品は、薬剤師等が販売することとされている(薬機法第36 条の9)。そして、情報提供設備は薬局や店舗販売業の構造として求められている。しかし、一般的には情報提供設備にいると思われる薬剤師等がいるように法規定がなっていないために不在であるなら、資格者はどこで何をしているのか。
この問題は、濫用のおそれのある医薬品だけでなく、一般用医薬品の専門家による関与そのものの問題ともいえる。検討会では「実態として店舗管理者やその他の薬剤師等は、店舗内で勤務していても、第二類・第三類医薬品(比較的リスクの低い医薬品)の個別の販売には関与せず、一般従事者がこれらの医薬品の販売を行う事例がみられる」とも指摘されている。そのため、検討会とりまとめでは、購入する医薬品と購入者の状況を薬剤師等が確認できる動線・体制を確保することなどの見直しが必要としている。「動線・体制」としては、例えば、薬剤師等のレジへの配置や、情報提供設備を経由する動線等を挙げており、一般用医薬品専用のレジ等があればより望ましいとしている。JACDS森氏の「いるようにする宣言」はこういった実効性ある制度見直しにもつながるものともいえそうだ。
JACDS理事の森信氏、「オーバードーズ、どれくらいの死者がいるのか」
濫用のおそれのある医薬品の対応としての制度見直しに関連しては、JACDS理事の森信氏は、次のように述べた。
「1つだけ皆さんにお考えいただきたいのは、濫用のおそれがある、濫用のおそれがあるというが、適正に利用している人が大多数なんです。そのことが議論されずにオーバードーズ、オーバードーズと。それならどれだけのオーバードーズがあって、どれだけの死者が出ているのか。そこのところがはっきりしないのでは、バランスが全然違うと思うんです。だから適正に利用できる方が利用できないようになると、極論をいって、麻薬製剤だったら全部処方箋薬にしなさいとなったら医療崩壊しますよ。風邪をちょっと引いただけでどんどん病院に行ったらほかの治療ができなくなるしコロナ禍みたいになる。そのへんのところもお考えいただきたい」と述べた。
そもそも処方箋薬にするという議論はされていないが、この意見に対し、日本薬剤師会の森昌平氏は、「一般用医薬品の国民へのアクセスは重要だと思っている。ただ、これだけ社会の中で濫用が起こっている」と指摘。「どれだけオーバードーズが起こっているのか」とのJACDS森氏の問いに対しては、これまでの検討会の中でさまざまなデータが示されてきたが、改めて日本薬剤師会の森氏はその中のいくつかを紹介。薬物依存症の治療を受けた10代患者の主たる薬物の推移では、2016年に市販薬の比率は25%だったものが2020年には56%になっているとのデータを示した。また、コロナ禍で市販薬の過量服薬による救急搬送が2倍になっているとのデータも示した。さらには、「過去1年以内に市販薬の乱用経験がある」という高校生は約60人に1人の割合という調査結果も示した。これらは全て、過去の検討会で示されてきた資料。
これに対しJACDSの森氏は次のように述べた。「濫用、濫用というとみんな麻薬製剤だと思っている(が違う)」との見方を示し、「当日文献(①一般用医薬品による中毒患者の現状とその対策、②ゲートキーパーとしての薬剤師;医薬品の薬物乱用・依存への対応)も提出したが」とし、「搬送でも多いのはカフェイン。30%以上です。鎮痛薬でもアセトアミノフェンです」と述べ、濫用のおそれのある医薬品と問題になっている成分が違うとの見解を示し、「よくデータを見て、イメージで咳止めだ、風邪薬だと規制をやったら国民のためにならない」と述べた。
当日提出された2つの文献の中からは搬送で「カフェイン30%以上」との文言は見つけられなかったが、文献にあった致死量摂取例のデータのことなのだろうか。文献では、「一般用医薬品による致死量摂取例86例の一般用医薬品による急性薬物中毒患者のうち,28 例(33%)が致死量を摂取していた。致死量に達した成分別ではカフェインが 13 例(46%)ともっとも多く,アセトアミノフェン 12 例(43%),アスピリン2 例(7%),ジフェンヒドラミン 1 例(4%)であった」と記述がある。一方、同じ文献内には「摂取した製剤(延べ 111 例)の内訳は総合感冒薬 32 例(29%),解熱鎮痛薬 25 例(23%),催眠鎮静薬 19 例(17%),眠気防止薬 18 例(16%),鎮咳薬 7 例(6%),鎮暈薬 2 例(2%),その他 8 例(7%)であった。これらの製剤は医薬品分類では解熱鎮痛薬や総合感冒薬,鎮暈薬の第 2 類医薬品が 15 例(54%)で,眠気防止薬の第 3 類医薬品が 13 例(46%)であった」との記述もある。濫用に用いられる製剤と、「致死量」に達している「成分」とでは捉え方が違うのではないかとも思われた。