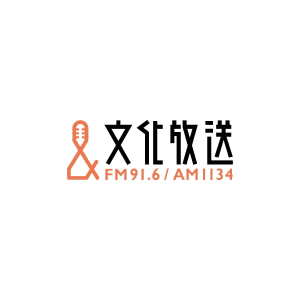お笑いタレント、大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』(文化放送・毎週月〜金曜13:00~15:30)が5月17日に放送され、
集英社新書から発売中の『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』を著した、文芸評論家の三宅香帆がゲストに出演。番組パートナーの室井佑月とともに、本の内容について伺った。

大竹「三宅さんが『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』という本を書いたら、この本は売れたんですね」
三宅「(笑)たくさんの人に、「働いてるから『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』が読めない」って言われます」
大竹「三宅さんは、社会人になって1年目にずいぶんショックを受けられたとお書きになってますね」
三宅「私は昔からすごく本が好きで、本とかマンガに囲まれて暮らしていきたいみたいな人間で、文学部にずっと居たんです。大学院でも文学研究を勉強していて本当に本漬けの生活だったので、こんな本好きの自分が、働いたぐらいで読めなくなる日が来るとは全然思っていなかったんです」
大竹「どんな職場で働いていたんですか?」
三宅「IT企業のいわゆる大企業って感じで」
室井佑月「めっちゃ忙しいの?」
三宅「メールのやり取りがずっとあったりとか。長時間労働ではないんですけど、ずっと仕事のこと考えちゃうみたいな感じはちょっとありましたね」
大竹「週に5日間、毎日9時半から20時過ぎまで会社にいる。そのハードさで驚いたそうですね」
三宅「でも多分世の中の人からしたら、そこまでめっちゃ激務ってわけでもないと思うんですよ。私の友達とかも朝7時から夜の11時まで働いてますみたいな人も結構いるし。別に過労ってわけでは全然ないのに、でもやっぱりそれでもすっごく疲れて本が読めなくなるっていうのが、日本の会社って何なんだろうって思うようになったきっかけです」
大竹「本が読みたいのに読めない社会が今広がっていて、なんでだろうとお考えになった」
三宅「明治時代から現代に至るまで、日本の労働と読書史みたいなものを並べて、昔の人は本を読んでたのか調べると、意外と昔の人も例えば立身出世を語る自己啓発書っぽい本だったら読んでいたりします。あとバブル期ぐらいだと新聞や雑誌連載の小説だったり日常に溶け込む本が、すごく多かったと思います。明治とか戦後ぐらいのベストセラーは新聞連載が多かったりとか、その後は雑誌からベストセラー小説が生み出されてたりしたのに、今ってベストセラー小説ってだいたい書き下ろしとかじゃないですか」
大竹「その上で、本が読めない状況について三宅さんは、新しい文脈を作ることができない、とおっしゃってます。これはどういうことですか?」
三宅「今、なかなか本が読めないと、特に忙しいサラリーマンの人が思っている理由の一つに、何を読んでも仕事にひっつけちゃうっていう問題があります。仕事のためになる本だったら読めるけど、仕事のためにならない本は読めないっていうような状況です」
トークの続きはradikoのタイムフリー機能でご確認ください。