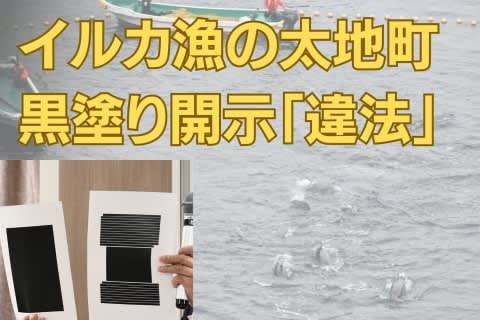
イルカの追い込み漁で知られる和歌山県太地町の鯨類取引をめぐり、環境保護NGOが町に対して公文書の開示を求めていた訴訟で、大阪高裁(森崎英二裁判長)は5月17日、町側の控訴を棄却した。鯨類の販売資料などを非開示とした町の対応は、公文書開示条例に違反しているとの一審を支持した。
弁護士ドットコムニュースは町側に判決の受け止めを問い合わせたが、「担当者不在で回答できない」としている。
●高裁「開示によって町側の利益を害する証拠はない」
追い込み漁のあり方に反対する「Life Investigation Agency(LIA)」の代表ヤブキレン氏は、毎年その動向を注視。太地町民として、2021年9月に15年分の飼育数や販売取引に関する文書を条例に基づき開示請求したが、ほぼ黒塗りだったため、2022年4月に提訴。和歌山地裁は2023年9月、条例に基づき町側に開示するよう命じた。
控訴した町側は「情報は外部に流通しない重要なノウハウで、開示することにより、競争上の地位その他の正当な利益を害する」と主張したが、高裁は一般論にすぎないと指摘。具体的な事実関係に基づいて認め得る証拠もないとして、主張を退けた。
また、町側は反捕鯨団体によって日常的に脅威に晒されているから、開示すれば事業者の生命にすら重大な危険が及ぶなどと訴えていた。しかし、高裁は「(脅迫文書などは)氏名不詳者からの単発的なもので、過激な団体による活動も限定的だ」と指摘。LIAが犯罪行為も辞さないような団体である証拠もないとして、町側の主張を採用しなかった。
NGO側代理人の高野隆弁護士は「公共団体と取引を行う事業者の利益を理由とする非開示が許される要件を厳格に解し、それを認めるための重い立証責任を行政側に課したという点で、画期的な判例だと思います」とコメント。吉田京子弁護士も「一審判決よりもさらに進んだ。太地町にはこの判決に従って適切に公文書を開示していただきたい」とした。

●NGO側「真っ当な行政運営を」
ヤブキ氏は、町立くじらの博物館は鯨類の生態に関する学習や研究目的ではなく、生体販売取引によって利益を得ている上、鯨類を不適切な状態で飼育している可能性があると考え、以下の7つの資料について情報公開を求めていた。
1.太地町による「いさな組合」からの鯨類の購入にかかる請求書 2.収入金通知票 3.鯨類に関するCITE(ワシントン条約を意味する)と輸出関係資料(申請、承認など) 4.鯨類の販売に関する契約書 5.博物館における生物の飼育動物一覧表 6.博物館における生物の死体処理にかかる請求書 7.博物館における生物の飼育検査記録
判決後、ヤブキ氏は以下のようにコメントした。
「税金で運営される行政庁の公文書や事業資料は、広く公開されて然るべきです。納税者には、行政の暴走や不適切な行政運営を防ぎ、同時に行政庁の業務内容を監視する目的もあります。太地町は、これらの不適切な行政運営を指摘し、正す者が誰もいなかった為に、真っ当な行政運営がなされず、不適切な行政運営がまかり通ってきた現実があります。町は判決を真摯に受け止め、正当な行政庁に生まれ変わる事を願います」

