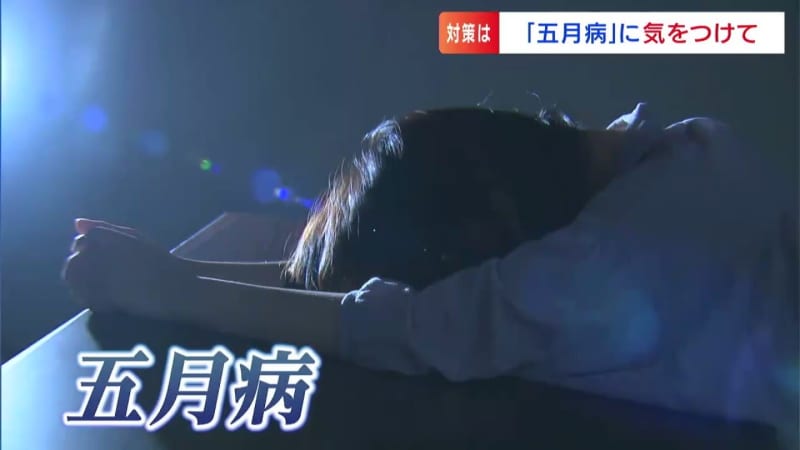
5月も半ばです。この時期に心配されるのが、いわゆる「五月病」です。進学や就職など生活環境が変わることでストレスを抱えやすくなり、心や体に不調を抱える人も現れやすいといいます。精神科医の岡山大学学術研究院社会科学学域(文学部)の 耕野敏樹准教授に「五月病」への対応方法などを聞きました。
耕野准教授は、「昨年の今頃はコロナ明けのタイミングでもあり、五月病の症状を感じる人が多かったが、今年もまだコロナ禍の影響を引きずっている印象がある。症状が出る前に楽しんでできていたこと、人と交流していたことを思い出すことが大切」といいます。
(2023年5月の記事再掲です)
「五月病」今の時期、不調を訴える相談が増える
(街の人)
「起きるのとかしんどかったり、めんどくさいなとか」
「GW明け、最初はだるいかなと思ったことは結構ありましたけど。朝と夜で気温が違うので大変ですね」
「眠れなくなっています。梅雨の前後は、そういう感じがありますよね」
いまの時期に心配されるのが、いわゆる「五月病」です。岡山市北区の岡山県精神科医療センター・医師の耕野さんは「日常生活における環境の変化により、特にこの時期不調を訴える相談が増えている」と言います。
(岡山県精神科医療センター 耕野敏樹 医師・当時)
「日本の場合は、4月に色々な社会環境が変わる出来事が多いものですから、どうしても『1カ月くらい自分なりに工夫をしてきたけど、やっぱり上手くいかない』と相談に来る人が多くいる」
「寝られない」「不安が止まらない」
4月に新年度を迎え、進学・就職・人事異動などで周囲の環境が変わり、新しい状況に適応するために努力をしてきた人も多いはず。
耕野さんによりますと、「五月病」では「環境の変化のなか、思うような力が発揮できず悩んだり」「悩みを解決できず、気持ちのコントロールが難しくなる」など、日常生活を送る上で支障をきたす様々な症状が出てくるということです。
(岡山県精神科医療センター 耕野敏樹 医師)
「『寝られない』という人もいますし、『不安が止まりません』という人も、中には『人に対してついつい攻撃的になってしまったり』『お酒の量が増えたり』いろいろな形ででますので」
主にメンタル面に症状のでる「五月病」ですが、懸念されるリスクは「体調面への影響」だと言います。
(岡山県精神科医療センター 耕野敏樹 医師)
「『身体的な健康』と『メンタルヘルス』というのは、切っても切り離せない。例えば年単位で長引いてしまうと、体の健康面でも心配になってきます」
「五月病」対策は?
「五月病」のリスクを減らす上で、耕野さんは3つのポイントを上げます。
①自分が調子が良かった時に取り組んでいた好きなこと、リラックスできるストレス解消法を思いだし実践する
②友人や家族など、自分にとって心地いい人間関係を重視する
③アルコールに頼りすぎない
です。
(岡山県精神科医療センター 耕野敏樹 医師)
「自分がやっていて心が和んだり少し活気がでるような活動は、必ずどこかにあると思います。改めてご自身のメンタルヘルスのストレスの部分と、ストレスに対処してきた部分を両方見ていくきっかけにしていただければなと」
「五月病」の症状を放置しておくと、日常生活に支障が出る恐れもあります。少しでもリラックスする時間を設けるなど、早めの対応が大切になりそうです。
特に「五月病」で注意する状況や症状について医師の耕野さんに伺ったところ
①職場や学校などで相談できる環境がなく、孤立している
②不眠などの身体的不調
③自分の将来に対する絶望感を抱いた時、などが上げられるということです。
そして、メンタル面で不調を訴えている人がいた場合、周りの人に何が出来るか。
①相手に寄り添い、相手のペースで話をきく
②協力できることを手助けする意思を示すことなど
相手に寄り添った対応を取ることが大切だということです。

