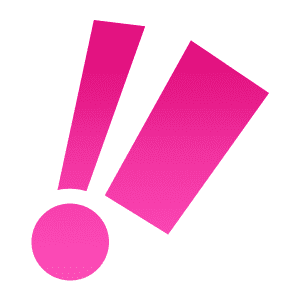ある日、幼い娘が失踪した――。17日に劇場公開を迎えた映画『ミッシング』で、娘との再会を望む夫婦を支援したいと思いながら、視聴率というバズを重視する会社との板挟みで苦悩する地元テレビ局の記者・砂田を演じた中村倫也。百戦錬磨の彼が見せる人間くささは、作品の屋台骨になっている。そんな中村が、作品の舞台裏はもとより、「役への共感」「表現しない演技」「マンネリ化しないコツ」など、俳優/人間としての現在地をたっぷりと語った。
■“削ぎ村倫也”で挑んだ『ミッシング』
――中村さんが今回演じられた砂田は、上に無理を言われて下の面倒を見て――と板挟みになる中間管理職ポジションです。そうした立ち位置について、ご自身が共感する部分はありましたか?
中村:厳密に言うと企業の中の中間管理職と僕は違うし、役者だからそう見られてもいないと思いますが、そうした感覚は確かにあります。作品づくりの中で年上と年下が半々だったり、どちらかがちょっと多かったりするような立ち位置になってきましたしね。主演をやっていたら周りがこちらの意向をうかがってくれる立場ではありますが、対人でいうと中間ですから、そうしたマインドは自分の中に常にあります。年上との接し方は昔から割と得意でしたが、年下との付き合い方は結構試行錯誤しています。
年齢的に真ん中な自分がどういう言葉を投げかけ、どんな接し方をすれば年下の子たちが良い空気感で芝居を出来るのか――アドバイスした方がいいのか、しない方がいいのか、する場合はどんなニュアンスで伝えるかなど、俳優だけでなくもちろんスタッフに対しても一つひとつ考えながら動いています。
僕自身、企業の人間ではないですが砂田に対するシンパシーは抱いていましたし、ご覧になってくれる方々も社会に出た方ならきっとそう思ってくれるはず。だからこそ、演じる上ではアピールしすぎずにそのさまが自然と出るようにするのが一番いいかな、と思いながら取り組んでいました。
そういった意味では、今回は吉田恵輔監督(※)からのリクエストもあり表現しない、“削ぎ村倫也”で臨みました(笑)。自ら表現しないことで、おのずと周りとの関係性や受け答えのニュアンスで見えてくる情報量が増えてくるはずだ、と考えて。「お客さんを見くびらない」ではないですが、しっかり想像してくれることを知っていますし。とはいえ長く役者をやっていると、台本を読み込んで「こういうことだろうな」と理解して提示しちゃう癖がどうしてもついてしまうから、意識的に「表現しない」と決めました。
――そんな中、砂田が一瞬激情を見せるシーンが鮮烈でした。
中村:砂田を演じながら、ちょうどよくアウトプットできない不器用な真面目さがあるヤツなんだろうなとは感じていました。溜まったものの発露がああいう形になってしまって、しかも彼自身無自覚なのかもしれないけど森優作さん演じる圭吾とリンクしてしまった――ということだけ頭に入れて演じていました。
撮影スケジュール上も森くんのその芝居を目撃するシーンが先にあったので、吉田監督に「ミラーリンクではないですが、圭吾の表情を受け取った状態でこのシーンに至る、で大丈夫ですよね?」と確認した記憶があります。
――ちなみに中村さんにとって、役への共感はどれくらい必要なものですか? 距離がある方がうまくいく場合もあるでしょうから、必ずしも近い方がいいものでもないかなと思ったのですが。
中村:なにかあったとき、弁護は必要な気がします。役を弁護するためにはなんとなく分かっていないといけないかなと。もちろん、自分が生きてきた中で得た感覚や経験、性格と照らし合わせて素早く共感に結びつくパターンもありますが、そうじゃなかったとしても「こういうヤツかもな」くらいの弁護はできるようにしています。
その上で距離感についてお話しすると、実はどんな役でも同じです。役に引っ張られることもないし、僕が引っ張ることもありません。
――それはキャリアを重ねていく中で到達したものなのでしょうか。
中村:というよりも、生きている歴が長くなったからですね。見てきているものや経験していることが増えると、結びつきやすさの要素は増えていきますから。これは僕の性質的なものかもしれませんが、役に没入すること自体、これまであまり経験がありません。
――舞台で長く一つの役を演じられるときも、距離感は変わらずでしょうか。
中村:舞台は超冷静です。どちらかと言えば、映像の方が集中しています。ガッと入り込んでいるように見えても、冷静にその様子を見ている自分がいます。
――確かに、舞台だと自分で場を展開していかないといけませんもんね。
中村:そうそう。舞台は役者たちが見せるべきポイントを編集して提示していくものですから。もちろん入り込んで演じる役者もいますが、それすらコントロールできた方がクレバーだなとは感じます。
――先ほど上世代と下世代への接し方のお話をしていただきましたが、2度目・3度目の共演も増えてきたかと思います。プラスに作用すること、逆にお互い分かっているからこそ枷(かせ)になることなどはございますか?
中村:枷に感じたことはないかなぁ…。昔から知っている共演者とラブシーンをやらないといけないときに照れくさい、くらいでしょうか。お互いに笑っちゃって「なんだこれ」ってなる――みたいなものはあります(笑)。
――中村さんにお話を伺っていると、常々「自己の客観視」を感じます。芝居においても対人コミュニケーションにおいても「自分がこう思っていても相手に伝わらない」ことは往々にしてあるかと思いますが、どんな工夫をされているのでしょう。
中村:僕はこの仕事を始めた10代の頃から、自分の考えていることが表に出ず、伝わらないことをずっと悩んできました。でも、あるとき「自分もそうなんじゃないか」と思ったんです。人のことを知ろうとするけど全然つかめていなかったり、経験値が上がるほどデータ量は増えますが、それが当てはまらない場合もたくさんあったりするんだろうなと考えるようになってきて。だからこそ、知る誠意といいますか、一緒に歩みながらものづくりをしていく努力はもちろんしつつ、「知った気になって決めつけて、何かを事前に思い込んでは失礼だ」と心がけるようにしています。
今回の砂田に関していうと、彼のキャラクター性や環境は社会に出た多くの人と重なるもので、誰もが一度は経験した葛藤をリアルタイムで抱いている人間なんじゃないかと感じました。分母が大きいぶん、表現しないほうが見た方が育ててくれると感じて、先ほどの「削ぐ」方法論を取りました。
――役者の中で「正解」と思っても、監督やお客さんの中ではそうでない場合もあるでしょうから、委ねる余白を作るというのは非常に納得できます。
中村:仮に、監督からこう演出されて「おかしくない!?」と思ったとしても、実はプロデューサーが監督に指令を出していた…みたいなことも“あるある”ですしね。もちろん、劇団☆新感線でそうした引き算の芝居をしてもしょうがないので(笑)、ジャンルに合わせて変えていくものの内の一つではありますが。
――削いでいく上でも作品を通して「その人物を見続けられる」味付けをしていかなければなりませんから、その塩梅の調整は難しいだろうな――と想像します。
■「なんだか落ち着かない」がちょうどいい
中村:撮影に入る前や撮影中に色々と考えてはいるのですが、結果的に「あんまり考えていない」に到達したように思います。相対する人によって微妙に砂田も変わるでしょうし、「沙織里と話していても上司の顔がちらつく」みたいに局面ごとに揺れ動くものですから、それを取りこぼさないように一生懸命やっていた――という感じでしょうか。流されてしまっているように見える一方で、カメラを回してインタビューを始めたら「ちゃんとやりたいことがある人なんだ」と感じられる部分もありますし、とにかく「砂田はこういう人」と決めつけずに転がしていました。そういった姿を映し出してくれることで、見る側にとっても気になる人になれたのではないかなと思います。
あと、本作はざっくり「沙織里サイド」と「砂田サイド」の二つの視点で進む構成になっていますよね。向こうがガッと激しいテンションで進むからこそ、こちらが静かな方がコントラストが出て映える――というような意識もあったかもしれません。
――ちなみに、『ミッシング』のように監督が脚本も書かれてオリジナル作品である、という作品だと、中村さんのアプローチも変わるものでしょうか。
中村:そうですね。絶対的な答えを持っている人がいる、という感覚です。脚本を書いている時もシーンをイメージしているでしょうし、撮る時ももちろんそうでしょうから、決まっているゴールにいかに近づけるか――という側面はあるかなと。そういう意味では、現場で監督の言うことをちゃんと聞きます(笑)。作演(書く人と演出する人)が違ったり、海外作品の翻訳だったりする場合は「こういうことかな」と話し合いながら進めていきますが、今回のようなパターンとはやっぱり入り口は違いますね。でもどちらも好きです。
――ただ今回は、吉田監督のイメージとは異なる芝居を石原さんが繰り出してくるパターンも多かったと聞いています。そういう意味では試行錯誤しながら作っていったのかなと。
中村:僕は吉田組が初めてなのでこれまでとの違いは分かりませんが、撮影の合間に吉田監督がタバコを吸いながら「面白いな…」とおっしゃっているのは目撃しました。

――石原さんご自身も、自分からどういう芝居が出てくるか分からなかった、とおっしゃっていましたね。そうなるとその場でのセッションが増えてくる気がしますが、芝居を受ける際に「こういうのが来たか」と驚くことは、経験を重ねていく中で減ってきたのでしょうか。
中村:そうですね。プラス、僕が年々自分の台本の読み方ややり方に固執しなくなってきています。だから全く予想がつかない状況でも「やってみます」となってきたし、やってみて「こういうことかな」と判断するまでも早くはなってきました。ただ、そこに溺れないように自分の成功体験や経験則は信用しないようにしています。
――なるほど。メソッドに固執しないといいますか。
中村:正直、固執しちゃうとつまらないんです。「こうすればいいんでしょう?」って僕の中では全然クリエイティブじゃないし、不確定要素が多い中で「これで合ってるかな?」と試すほうが楽しくて。
――となると、いまは意識的に未知の領域を目指している状態でしょうか。
中村:元からそういう部分はありましたが、年齢を重ねていくごとに未知なるものへのがっつき方が変わりました。そう見えないように人知れずやっているところはありますね。オープンにしていくと、それがまた一つのメソッドになってしまいますから。「実は祖父は縁側で囲碁をするのが好きだった」くらいの感じで、こっそりやっていこうかと(笑)。
――前回の『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』のインタビューで、ここ2~3年を振り返って「『楽しい』と『幸せ』しかない」とおっしゃっていましたが、やり尽くした感であったり不安を覚える瞬間はありますか? 個人的な話で恐縮ですが、仕事を続けていく中で「1周した感」と「先々への不安」にずっとさいなまれていまして…。
中村:僕はどちらも楽しんでいます。人としては安定を好んでいますが、表現者としては不安定を好んでいる癖がありますね。その「不安定」は足元が崩れるようなものではなく、首から上の不安定といいますか――体幹や土台は固まっているからぐらつきはしないけど、なんだか落ち着かないな、くらいがちょうどいいです。全部安定しちゃうとそれしかできなくなるから、固まらないように、より「分からない」状態を楽しんでいます。
でも、SYOさんのおっしゃる感覚はよく分かります。僕も『石子と羽男ーそんなコトで訴えます?ー』(TBS系)に出演したタイミングで、『仮面ライダーBLACK SUN』に『宇宙人のあいつ』に舞台『ルードヴィヒ~Beethoven The Piano~』と立て続いて、今まで培ったものは全部出したな、やり切った感があるなと漠然と思っていたのですが、去年『ハヤブサ消防団』(テレビ朝日系)や舞台『OUT OF ORDER』をやったときに「新しい感覚でチャレンジしているな」と自分自身に感じたんです。周りは誰もそんなことを思わないだろうけど、自分の中ではそうした感覚を得ました。ミルクレープの生地が厚くなっていくように、乗せようと思えば乗せられるんだと感じたのは発見でした。
分かりやすく上がっている時のほうが、ステップが明確だから楽だと思うんです。「上がっちゃったな」と思うと、次のステップを探さないといけなくなりますから。でも、実はまだ踊り場だったりするんですよね。そうした気付きは人との出会いでもたらされるものかもしれないし、自分なりの角度で見えるものかもしれないし、画一的なものではないかもしれませんが――人生はその繰り返しじゃないかなと思います。
――この場を借りて人生相談をしてしまい、申し訳ないと思うと同時に、ありがたいお話をしていただいて、ものすごく染みています。
中村:いえいえ。これは僕の話ですが、去年ある風の強い夜に「壁と屋根がある場所で寝られていいな」と感じました。この間も料理をしていて「ガスコンロってすごいな」とふと思ったり、当たり前と思っていたものがそうじゃないと考える機会が増えてきた気がします。つまり、自分の足元をもう1回見つめ直したら幸せがいっぱい転がっているんだと。宮沢賢治ではないですが、土塊を見ながら自分を見返すと新しい空が見えてくるんだと悟りました。きっと、年を取って目が顕微鏡になってきたんでしょうね。
※吉田恵輔の「吉」は「つちよし」が正式表記
(取材・文:SYO 写真:上野留加)
映画『ミッシング』は、全国公開中。