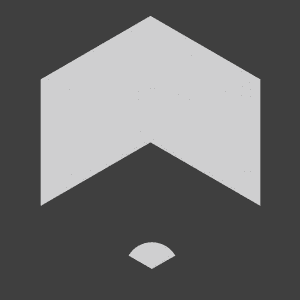6月1日(土)に三重県多気郡明和町で斎王まつりが開催される。今年で41回目を迎える伝統ある祭りで、主役となる斎王役の座を射止めた三田空来(そら)さん(文Ⅱ・2年)。なぜ斎王役に応募したのか、斎王役への意気込み、斎王まつりの魅力などを取材した。(取材・松本雄大)
「地元の魅力を全国へ」斎王役への熱い思い
━━斎王とは
起源は飛鳥時代くらいまで遡るのですが、皇族の未婚の女性が占いで選ばれ、都を離れて伊勢の入り口にあたる斎宮で祈ったり、伊勢神宮で行われていた神嘗祭などの大きな祭りに参加したりする役職でした。その後斎王制度は途絶えてしまったのですが、斎宮跡が明和町で発掘されたことをきっかけに、遺跡の保存や街おこしなどの意味も込めて斎王まつりという祭りが行われることになりました。斎王役はその祭りの主役のようなイメージですね。毎年その代の斎王役が三重県知事に表敬訪問に行くなど三重県内での知名度はあるのだと思います。
━━なぜ斎王役に応募を
父の実家が明和町にあってよく遊びに行っており、その縁で3回ほど小学生の時にも斎王まつりのこども役で出演していました。こども役の中にはこども斎王という役があって、希望はしていたんですけど、抽選に当たらず…。大人になったら斎王役をやりたいなという思いを持っていました。東大の2Sセメスターはかなり時間に余裕があるので、ここしかないと思って今回応募した形になります。
━━斎王役には並々ならぬ思いがあったんですね
斎王まつりでは、斎王役はお祭りの中心的な存在です。お祭り当日に行う群行(斎王が京都から伊勢へと向かう行列を再現したもの)ではみんな斎王役を観にくるくらい、地元では愛されていました。毎年実家でも斎王役が決まると、誰がなったのかという話を絶対していて。その存在の大きさを小さい頃から感じる中で斎王役に憧れを持っていましたね。
また、東大に来て、クラスの友達に斎王まつりの話をした時に、源氏物語に記述があったりして過去の斎王のことを知っている人は結構いたのですが、斎王まつりのことは誰も知らなくて。知名度の非対称性がもったいないと感じることがありました。現在東京に住んでいるという点も生かして、三重県外へのアピールを積極的に行いたいという思いもあります。
━━どのような仕事がありますか
斎王まつり当日まではリハーサル、知事への表敬訪問、新聞社の取材対応などがあります。斎王まつりが終わると地域のお祭りへの来賓としての参加やフォトコンテストの表彰式など、地域のイベントに参加して三重県を盛り上げる一助となるような仕事を任期の1年間行う予定です。

━━芸能人みたいですね
芸能人とまでは行かないですね(笑)。明和町の観光大使みたいな感じだと認識しています。
━━毎回お仕事のたびに三重県に戻られるんですよね
そうですね。ここまで遠い人は今までいなかったのではないかと思います。大体は三重県内に在住している方が選ばれることが多いですし。交通費が出ないのは少し懐事情的には厳しいですけど(汗)、実家に何度も帰れることはうれしいので、必要経費だと割り切っていますね。
━━どのような形で斎王役は選ばれるのでしょうか
意外に思われるかもしれませんが、応募自体は未婚の女性であれば、全国どこに住んでいる方でも可能です。ただ斎王まつりへの想いの強さが選ばれる基準にはあるとのことなので、お祭りとのつながりも作りやすい分、地元の方が選ばれることは多いのかなと思います。
━━選ばれた後はすぐお披露目会を行うとのことですが、初めて十二単を着た感想は
とにかく重いので歩き方が分からず、すごく大変でした。あまりにも重いので、「何枚か抜いてもバレなそうですね」と冗談を委員会の方に言ったら、「すでに3枚抜いてます」と言われて。今までの伝統も受け継いだ重みだと思い、身が引き締まりました。本番ではカツラも付けて、総重量25kgとなるので、しっかり歩けるように練習します。
実際、所作指導も1回あって、その後は自主練を家で行っています。袴を着て作法にのっとった歩き方の練習をしないといけないのですが、一人暮らしの家だと広さが足りず、道端で練習するわけにも行かないので、駒場のキャンパスプラザでも借りて練習しようかとも思っています(笑)。

第39代斎王役 三田さんの素顔に迫る
━━出身はどちらですか
三重県の伊勢市出身です。斎王まつりが行われる多気郡明和町に隣接する場所に住んでいて生まれてから高校まではずっと伊勢で暮らしていました。
━━中高時代の活動は
ずっと吹奏楽部で活動していました。父の影響で野球が好きでソフトボール部に入ろうと思っていたのですが、中学になくて。高校に入った時に野球の応援をしたいと思い吹奏楽部に入りました。中学では朝日新聞社賞といった優秀賞も取ることができて、公立だったんですけど、かなり強豪校でしたね。
高校ではコロナの影響で大会があまりなかったのですが、高1の時に1回だけ甲子園予選の応援に行くことができました。

━━東大を受験した理由は
高1の時のオープンキャンパスで東大の学生と交流したのですが、すごく刺激的な人が多くて、東大受験を意識しました。それと父親が京大だったので、せっかくなら超えたいなと思い東大にした側面もありますね(笑)。
━━東大ではどのような活動を
最初は吹奏楽部に入ろうと思っていて、実際に入部することも伝えていたのですが、公認会計士の資格も取りたかったので、両立は厳しいかもしれないと思い、最終的には入部しませんでした。
今はFairWindという地方の学生の東大受験をサポートする団体に所属しています。地方の高校で、周りに東大志望者がいない中でモチベーションの維持など苦労したこともあり、自分の経験を伝えていきたいと思って入りました。
色とりどりの衣装が祭りを鮮やかに彩る

━━斎王まつりの魅力を教えてください
見どころは禊(みそぎ)の儀という都から斎宮へ向かう前に身を清める儀式になります。明和町の町花にもなっているハナショウブを川に流すシーンは都を離れる斎王の切なさと決意が感じられる感動的な演出になっています。
また地方のお祭りは担い手が高齢化していて、存続の危機を迎えることも多いと聞きますが、斎王まつり実行委員会は今年大きく代替わりしました。しっかりバトンを渡して伝統を受け継ぎながら、若い世代にも刺さるようなパフォーマンスを夜のステージに取り入れるなど柔軟に変化をしており、夜には花火も上がります。どの世代の方がいらっしゃっても楽しめるお祭りだと思いますね。
━━最後にメッセージをお願いします。
実行委員会の方のお力のおかげで、毎年柔軟に企画を取り入れ、魅力が増しているお祭りです。日本史に興味ある方など昔の時代の雰囲気を味わうこともできますし、元々斎王という言葉を知っていたという方もこの記事をきっかけに斎王まつりにも興味を持っていただければうれしいです。ぜひ明和町にいらしてください!!

今年の斎王祭りは6月1日(土)開催。伊勢市や松坂市などの観光地にも近い。1泊2日の小旅行でみなさんもぜひ足を運んでみては。
【公式サイト】
The post 伊勢神宮の巫女 斎王1500年の歴史を紡ぐ 三重県明和町斎王まつり斎王役 三田空来さんインタビュー first appeared on 東大新聞オンライン.