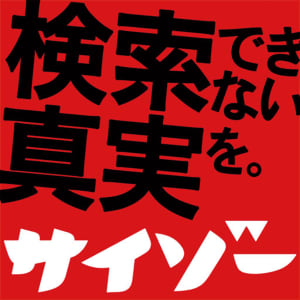──歴史エッセイスト・堀江宏樹が国民的番組・NHK「大河ドラマ」(など)に登場した人や事件をテーマに、ドラマと史実の交差点を探るべく自由勝手に考察していく! 前回はコチラ
前回(第19回)の『光る君へ』では、ついに「長徳の変」が描かれましたが、伊周・隆家兄弟(三浦翔平さん・竜星涼さん)の思慮の浅さが引き起こした偶然の不幸というような描写でしたね。
花山院(本郷奏多さん)が立派な牛車で身分を誇示しながらやってきた部分ですが、当時の貴族社会には身分によって乗ることが許される牛車のデザインに差があって、高い身分の持ち主ほど密会などの際には素性を隠そうと、わざと格式の低い牛車に乗ったりしたものです。史実の花山院ももう少し、普通っぽく見える牛車にしていたのではないでしょうか。
また、昼間から唐突に別室にこもる励む定子(高畑充希さん)と一条天皇(塩野瑛久さん)を不思議に思うまひろ(吉高由里子さん)が事情を察し動揺するシーンにはネットの注目も集まりましたが、天皇の子づくりはまさに「国事行為」でしたからね……。しかし、ドラマではまひろと定子は面識を得てしまっていますから、これから道長(柄本佑さん)が定子に対する“仕打ち”を次々と行う中で、道長とまひろの関係もこじれてしまいそうな気もしました。
さて、今回は、陣の定めでも議題となった「宋人」たちについてお話してみようと思います。史実では長徳元年(995年)8月下旬ごろ、朱仁聡・林庭幹らを含む「宋人」の商人たち70人余りが乗った船が若狭国(現在の福井県西部)に来着したと考えられ、その知らせが朝廷に届いたのが9月初旬のこと。そして9月4日以降、藤原道長の先導で会議が重ねられ、「宋人」一行は越前国(現在の福井県北部)に移動させられることになりました。
移動の理由は、当時の日本は名目上にせよ「鎖国」しているため、太宰府(現在の福岡県)以外では、越前国にて外国人(商人)との交流が行われていたからです。越前国の敦賀港には外国人たちが滞在するための「松原客館」などの名前で呼ばれる施設が設けられ、一説には気比神宮内、もしくは気比の松原にあったといわれていますね。
「宋人」こと中国人商人たちの来日は「986年から1000年までの14年間の状況をみても、15件の宋商に関する記録がある(『図説日本の歴史 5 貴族と武士』)」とのことで、1年に1回くらいのペースですから、都の貴族たちにとってはさほど珍しい出来事ではなく、朱仁聡の来日も永延元年(987年)に続いて、これが2回目でした。
しかし、原則的には中国商人は博多に到着すべきというルールがあったのに、今回の朱仁聡一行の船は朝鮮海峡を越え、日本海を通って(おそらく主要顧客である貴族たちが住む京都に近いという理由で)勝手に若狭国に到着してしまうという強気な態度を見せていました。
朱仁聡はなかなかアクが強い人物だったようで、長徳3年(997年)10月28日には若狭守・源兼澄に対する「凌轢(りょうれき)」――暴力事件で問題視され、長保2年(1000年)には中宮・藤原定子に商品を収めたのに、料金が未払いであるといって訴えを起こしたことなどが判明しています。
定子が何を買ったのかまでは、記録に残る「雑物」という記述からはわからないのが残念ですが、以前の放送で、まひろが藤原宣孝(佐々木蔵之介さん)から「唐物」の「紅」をお土産として受け取るシーンがあったように、化粧品の類か、香木などではないかな……と想像されます。
このような中国からの商人たちを、日本側を代表して接待するのが越前国の国司(越前守)の重要な任務で、漢詩を詠んで饗応するなどの対応も求められていたそうです。思えば花山天皇がまだ東宮(皇太子)だった時代、漢学の才能を評価された藤原為時(ドラマでは岸谷五朗さん)が「副侍読」の職を得たのが貞元2年(977年)のこと。花山天皇はドラマにも描かれたように突然出家し、それによって為時も罷免されてしまいましたから、約10年は具体的な職にはあぶれている状態が続いていました。
ちなみに花山天皇が即位した時、為時は「六位」の官位をもらっていて、その官位に即した給金がいわゆるベーシックインカム的に支払われていたので、ドラマで描かれたような貧しさと史実は少し違ったかもしれません。しかし、「五位」以上の官位を持っているのが「貴族」で、『延喜式』によると「六位」と「五位」の間には倍以上の収入格差があったので、それなりにわびしい日々が10年も続いていたのでしょうね。
そんな為時の運勢が大きく変わったのが、朱仁聡の2回目の来日だったようです。
大臣などの高官は必要に応じ、時期に関係なく任命されるのですが、それ以外の朝廷でのポストは春と秋の年2回の除目(じもく)で決まりました。お正月の除目では「下官(げかん)」、つまり地方官の人事が決まります。また、京都で働く「京官」の任命式は主に秋に行われました。
かくして長徳2年(996年)の1月25日、為時が淡路守に任命された記録があるのですが、28日には「直物」(なおしもの)――つまり先日の決定が覆され、為時が淡路守ではなく、越前守に任命され直しているのです。その経緯をはっきりと語った一次史料は存在しないのですが、鎌倉時代の説話集『古事談』などによると、天皇に仕える女房(侍女)を通じて、為時は自作の漢詩を献上したのだそうですね。
その内容の一部が「苦学の寒夜。紅涙(こうるい)襟(えり)を霑(うるお)す。除目の後朝(こうちょう)。蒼天(そうてん)眼(まなこ)に在り」――私は血の涙を流しながら学問に励んできたのに、ようやく除目で任官されたのは「小国」淡路守で、がっかりして空を仰ぎ見てしまいました……というものだったので、一条天皇が哀れに思って食事も喉を通らなくなり、それを見た道長が間に立ってくれて、自分の配下の源国盛(ドラマでは森田甘路さん)という貴族を犠牲にし、為時を越前守のポストにねじ込むことに成功したという逸話も伝えられています。国司の任国には「大国」、「上国」、「中国」、「下国」の4つがあり、高官たちの覚えがめでたい部下たちほど、実入りの多い「大国」の国司に任命してもらうことができました。
ドラマの道長も「関白にはならない」と一条天皇に宣言していましたが、史実の道長は関白にならないことで、こうした朝廷の人事を決める公卿会議に積極的に介入し、部下たちにうまく恩義を与えることができていました。それゆえ、為時が約10年ぶりに官職に、しかも「大国」である越前の国司に任命してもらえたのは、道長から使い勝手のある男であると認められたにほかならないのでしょう。
もしかしたら、為時の切り札は、すでに文才を発揮していたとしてもおかしくはない娘の紫式部だったのかもしれませんね。史実の道長は策謀家ですから、長女の彰子(ドラマでは見上愛さん)が成長したら天皇の後宮に入内させようと考えていたでしょうし、その際には文学好きの帝をいかにして喜ばせるかの作戦も立てていたでしょうから……。
ちなみに紫式部も為時に付き従って越前国に向かっていますが、越前での暮らしが性に合わなかったようで、わずか1年ほどで京都に戻り、以前からプロポーズされていた藤原宣孝と結婚しています。何人もの妻や子をすでに持つ宣孝との結婚は、条件のよい結婚とは言えなかったものの、それでも越前での暮らしよりは「マシだ」と判断したのかもしれません。いずれにせよ、今後のドラマで紫式部と宣孝(そして道長)の関係がどのように描かれていくのか、興味津々ですね。
<過去記事はコチラ>