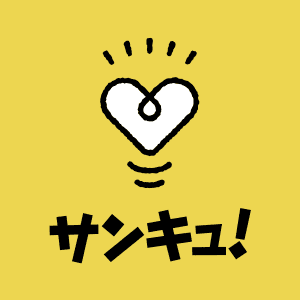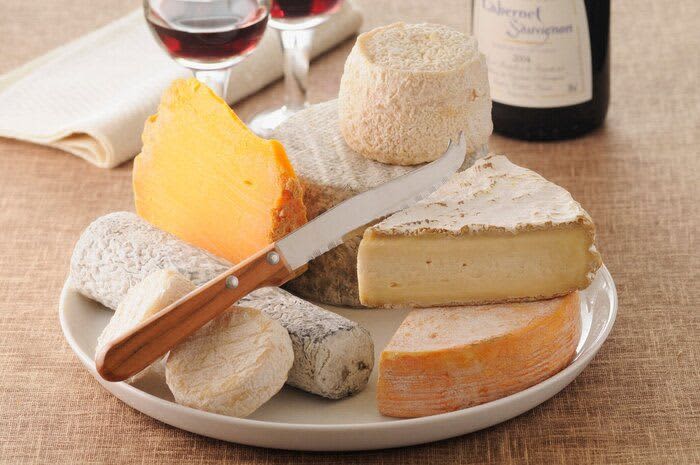
チーズに含まれる栄養素には、健康によい作用を持つものが多い反面、とり方を間違えてしまうと体調をくずす危険性もあるのだとか!
管理栄養士と食生活アドバイザーの資格を持つライターのゆかりさんに、チーズの食べ方によって体にどのような悪影響が及ぶのかと、1日に食べてもいい量の目安について紹介してもらいます。
丈夫な体づくりや代謝アップに!チーズを食べる「メリット」
チーズは、大きく分けると2種類あります。
乳(※)に乳酸菌や酵素などを加えてたんぱく質を固まらせたものが、ナチュラルチーズです。原料や加工法の違いなどで、1,000種類以上もあるのだとか。
それに対し、1種類か複数のナチュラルチーズを溶かし、乳化剤などを加えて固めてつくったものをプロセスチーズと呼びます。国内ではプロセスチーズのほうが多く流通しており、保存性が高いという特徴があります。
そんなチーズには、たんぱく質や脂質が豊富。このほか、次のような栄養素も多く含まれています。
・ビタミンB12
・カルシウム
・リン
・ビタミンA
・ビタミンB2
これらには、貧血を防ぐ、骨や歯を丈夫にする、心臓や腎臓の機能を維持する、免疫機能を保つ、糖質・たんぱく質・脂質の代謝を促進する、などといった働きが期待できますよ。
また、乳に含まれているカゼインは、消化の過程でカゼインホスホペプチド(CPP)という成分に変化します。
CPPは、小腸でカルシウムを体内に吸収しやすくする性質があることから、さまざまな食品の中でもチーズはカルシウムの補給源として優れているといわれるのです。
牛乳などを飲むとお腹を壊してしまう「乳糖不耐症」と呼ばれる人であっても、チーズに加工されると体調不良の原因になる乳糖が1/5程度まで少なくなることから、牛乳よりも安心して取り入れやすいという特徴もあります。
このように、チーズを上手にとり入れることで、健康増進だけでなく美容にもよい影響が期待できるでしょう。
※……国内では牛乳を原料にしたチーズが主流ですが、世界的にはヤギ、ヒツジなどの乳を使ったものもあります。そのため、この記事ではまとめて「乳」という表記にしています。
ミネラル不足やアレルギーのような症状も?チーズを食べすぎる「デメリット」

多くのメリットが得られるチーズですが、過剰に摂取したり体質によっては思わぬデメリットが生じることもあります……。
ほかのミネラルの吸収率が低下する
チーズに含まれている豊富なカルシウムは、とりすぎてしまうと鉄や亜鉛などの吸収を抑えてしまうことに……。
鉄が不足すると貧血によって息切れや疲れやすくなり、亜鉛の不足では味覚障害や下痢、脱毛、免疫力の低下などを招いてしまいます。
それ以外にも、過剰なカルシウムは結石の原因となったり、便秘につながることもあるため、そういった症状が気になる人も食べすぎには気をつけたいところです。
心筋梗塞のリスクが高まる
チーズに含まれる脂質の多くは、飽和脂肪酸という種類です。飽和脂肪酸をとり過ぎることによって、血液中の総コレステロールが増加し、心筋梗塞が起きやすくなるとされています。
チーズの種類にもよりますが、100g食べるだけで1日の飽和脂肪酸の目標量を超えてしまうこともあるのです。
なお、チーズに限らず動物性食品に飽和脂肪酸が多く含まれている傾向にあるため、肉や魚も食べることを考慮してチーズを食べる量に調整するようにしましょう。
血圧が上がりやすい
チーズには、塩分を含むものが多くあります。そのため、食べ過ぎることで塩分のとり過ぎになってしまい、血圧が上がってしまうことが考えられます。
たとえば、一般的なプロセスチーズであれば100gあたりに2.8gの食塩が含まれています。これは1日の食塩目安量の1/3以上に相当。
ワインなどのお酒とも相性がよいチーズですが、チーズに含まれる塩気によってついついお酒も進んでしまい、チーズを食べる量も増えがちなので注意が必要です。
頭痛やじんましんなどが起きる
チーズには、発酵の過程で微生物の働きによってたんぱく質が分解され、チラミンやヒスタミンという成分が含まれています。
チラミンは交感神経に作用する働きがあり、体に直接働きかけてさまざまな変化を与えます。血圧の上昇や片頭痛などが起こることも。一方で、ヒスタミンはじんましん、吐き気、嘔吐といったアレルギーに似た症状を起こすことが知られています。
ただし、食物アレルギーとは異なるため、チーズを口にするたびに必ず症状が起こるわけではありません。
チーズほどではありませんが、ワインやビールなどにもそれぞれの成分が多く含まれているとされています。ワインやビールと一緒にチーズを食べる際は、とくに食べ過ぎに気をつけるようにしましょう。
※……チーズそのものが食物アレルギーの原因となる場合もあるため、少量食べただけでも頻繁に体調の変化が見られる場合は、専門家を受診することをおすすめします。
チーズを楽しむ量とタイミングは?
上記のとおり、チーズに含まれる栄養素にはメリットとデメリットの両方があります。
そこでここからは、安心してチーズを楽しめる量とタイミングについて解説していきます。
健康な成人は1日にどれくらい食べても大丈夫?
検証1:カルシウム量
まずは、1日とっても健康障害が起こらないとされるカルシウムの量(耐用上限量)から、チーズの適量について検証してみましょう。
日本人の食事摂取基準(2020年版)によると、18歳以上の男女ともに2,500mgと設定されています。
プロセスチーズに含まれているカルシウムは、100gあたり630mg。
・プロセスチーズ……およそ400g相当
通常の食事の中で、ここまで多く食べることはあまりないでしょう。
ただし、ほかの乳製品や骨ごと食べられる小魚や缶詰を食べる際には、これよりも少なくするようにすると安心です。
検証2:飽和脂肪酸量
つづいて、1日の飽和脂肪酸の目標量から検証してみましょう。
日本人の食事摂取基準(2020年版)によると、成人以上の男女ともにエネルギー摂取量の7%以下が目標値に設定されています。
これは、自立した生活をしている人(身体活動レベル:ふつう)の18~74歳までのエネルギー必要量から計算すると、男性ではおよそ20g、女性はおよそ15gということに。
つまり、以下の量であれば摂取基準量を大きく上回る心配はなさそうです。
プロセスチーズ100gに含まれる飽和脂肪酸量は、100gあたり13.6g。
・プロセスチーズ……(男性)およそ150g、(女性)およそ90g相当
ただし、肉や魚などの動物性食品からも飽和脂肪酸をとることを考えた場合、それらを食べる量にも左右されますが、これよりも少なくする必要があるでしょう。
検証3:食塩相当量
つぎに、1日の塩分摂取の目安量から検証してみます。
日本人の食事摂取基準(2020年版)によると、成人以上の男性で7.5mg未満、女性では6.5mg未満と設定されています。
プロセスチーズに含まれている食塩相当量は、100gあたり2.8g。プロセスチーズだけで1日の食塩をとることは考えられないので、仮に1/3に相当する量で計算してみることにします。
・プロセスチーズ……(男性)およそ90g、(女性)およそ75g
ただし、塩分を多く含む佃煮、漬物、煮物、塩焼き、麺類などを食べる人は、さらにチーズの量を少なくするのをお忘れなく。
結論
ちなみに、厚生労働省の食事バランスガイドによると、乳製品の1日の摂取目安量はカルシウム200mgに相当する量とされています。この場合、プロセスチーズわずか「32g」でその量に達してしまうのです。
これらの検証結果と、脂質が多くエネルギーが高い食品であることも踏まえると、プロセスチーズの摂取量は32g程度にとどめておくのがよいといえるでしょう。(※)
※……一般的なスライスチーズ2枚分相当。カロリー換算で、100kcal。
どのタイミングで食べるのがいい?
チーズには、たんぱく質や脂質が多く含まれているため、糖質の多い主食などよりも先に食べることをおすすめします。
そうすることで、血糖値の上昇を抑えてくれる効果が期待できるでしょう。
血糖値はすぐに使えるエネルギー源としてある程度必要なものですが、高くなり過ぎてしまうとインスリンというホルモンを過剰に分泌させてすい臓を酷使したり、体脂肪を溜め込みやすくなってしまうのです。
反対に、就寝時間に近い夕食や夜食に食べるのは避けるのが賢明。
眠っている最中は消費されるエネルギー量が減少することによって食べたものが脂肪として溜め込まれやすくなったり、消化活動に時間がかかって睡眠の質を下げやすくなることがその理由です。
正しい量を把握できていれば、チーズはメリットが多い食品です。チーズのメリット・デメッリトを理解し、上手にとり入れていきましょう。
■執筆/監修・・・

管理栄養士・ゆかりさん
管理栄養士、食生活アドバイザー。一女のママで出張料理、料理教室、講演、栄養相談も手掛けるほか、ライターとしても活動。
参考サイト
発酵食品中のヒスタミン及びチラミン濃度の調査及び経口暴露量の推定|農林水産省
※記事の内容は記載当時の情報であり、現在と異なる場合があります。
※記事内容でご紹介しているリンク先は、削除される場合がありますので、あらかじめご了承ください。