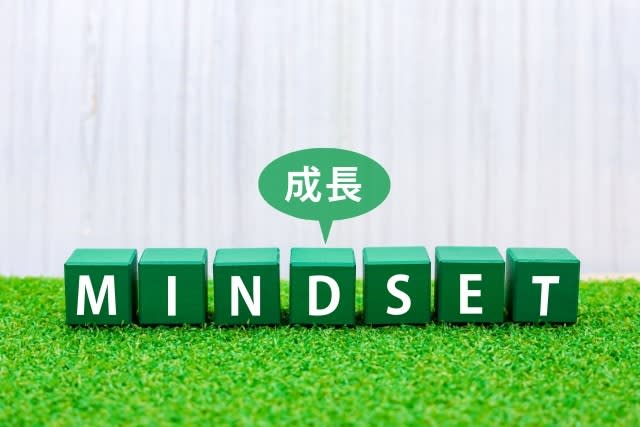
ついにこの越境ECに関する連載も最終回になりました。最初は事例、そして越境ECの基礎知識、応用知識を伝え、前回のマインドの話と続けてきました。今回も成功するためのマインド、成功している人のマインドの続きを書きます。前回とこの最終回は、内容的には非常に厳しいことを書いております。しかし、これは越境ECを志す事業者の支援や公的機関で専門家として数多くの事業者を見てきて感じた結論です。
前回は、越境ECと言っても、国内のECとそれほど変わらないという部分、そして洋の東西を問わず、そこに通底する、商売に関する哲学は江戸時代の商人哲学とまるで一緒だということを書きました。
しかし、越境ECは海外を相手にする仕事です。何から何まで今まで通りで良いというわけでもありません。今回はこれまでの感覚ではうまく行かないという部分、皆さんのマインドセットを変えないと行けないという部分(極端に言えば、別の人格を生み出してくださいといっても過言でない)をお伝えします。
細かいことに気がつく人が仕事のできる人ではない
今まで多くの日本の事業者支援や、個別面談で越境ECを目指す企業の話を聞きました。また、彼らからの問い合わせを聞いてみると、(初めてのことなので、気持ちは理解できますが)こちらの想像以上に恐怖に駆られていることが分かりました。そして、日本人の良いところでもあり、同時に場面が変われば悪いところでもある「細かすぎる」という性格が顕著に表れることが明らかになりました。
PHPの書籍に「日本の社員は「世界最低クラス」…松下幸之助が大切にした熱意が消えた理由」というものがあります。「最低クラス」とありますが、給料の話ではなく、新しいことや変化に対して臆病者が多いという内容です。
PHPの記事中には、2017年に企業を対象にアメリカのギャラップ社が行なった従業員エンゲージメント国際比較調査から、「日本は『熱意あふれる社員』の比率が6%にとどまり、139カ国中132位の世界最低クラスだった。国際比較調査において日本人は相対的にネガティブな回答をする傾向がある…」と記されていました。
スポーツコメンテーターである為末大さんが言われる「なにかあったらどうするんだ症候群」も同じような指摘をしています。
これは昔に伝聞したことですが、海外のとあるブランドは、新作ができると、まず日本市場でテストするという話を聞いたことがあります。一見すると、非常に誉れ高い話のように聞こえますが、実際は、他の国なら問題にならないような小さな傷一つでクレーム案件になるほど神経質な日本人を黙らせられる品質であれば、世界のどこでも問題が起きないからという理由だと聞きました。神経質もここまで来ると病的だなとショックを覚えたことがあります。
実際に類似した話が、インバウンド業界からも聞こえてきました。2023年2月の弁護士ドットコムの記事がまさにそれでした。簡単にまとめると、「外国人観光客が日本に戻ってきたことで、迎え入れるホテルや旅館は、接客対応で忙しそうに見えるが、関係者や従業員は、その多くが『外国人より日本人の対応のほうが大変』と答える」という内容です。
出典:外国人より日本人のほうが大変 宿泊施設の本音、「おもてなし」どこまで?(2023年2月、弁護士ドットコム)
重箱の隅をつつき、細かいことに気が付くと「よく気付いた」とほめそやし、仕事ができると錯覚を起こさせてる日本の労働文化の中ではいいでしょうが、この感覚は越境ECでは足かせ以外の何物でもありません。ごちゃごちゃ御託を並べる暇があったら、さっさとまずやるという気持ちの切り替えが重要です。(逆に、神経質な日本人消費者を相手にしてこれたみなさんなら、海外の消費者対応はラクだと思えると思いますよ(笑))。
また、越境ECで利用することになったツールやシステムが、自分のやりたいと思っていることをドンピシャで実現させてくれないと分かると、システムの問題だと考えて高いお金と長い時間をかけて改修しようとし、納得がいくまで休業にしてしまったりします。しかし、海外の企業なら、改修の必要性は感じつつも、実際に改修に取り掛かるまでは創意工夫して、あるいはアナログな運用をしてでも、事業を止めるということはあまりしません。この創意工夫が足りないというのは、自らで学び、考え、やり抜く自己解決能力が低いということであり、実際このことを示す、EQスコアは世界最下位です。
出典:EQスコア最下位の日本 感情知能EQはこころのインフラになる(PRタイムズ、2019年1月)
遺伝に打ち克つのは厳しい戦いになるが・・・
脳科学者の中野信子さんや、医師の和田秀樹さんがそれぞれの著作で、「日本人は、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの取り込みを阻害するタンパク質を多く持ち、不安に感じやすい遺伝子を持つ人が70~80%いる」と書いています。これを聞いて個人的には得心してしまいました。実際、支援していて、いろいろなことに不安を覚え、その都度動きが止まり、前に進まない人を見てきたからです。例えば、プライバシーポリシーをどうするかといった時、私なら海外でよく使われるテンプレートをコピーしてきて、ハイ終わり! なんですが、そんな安直な方法では怖くて落ち着けないという人が、けっこういるんです。不安に感じるのが遺伝の問題だと言われると、なかなか難しいのですが、全く新しい世界に飛び出すのですから、思いっきり今までの自分とは違う自分になったつもりで飛び出してみましょう。実際のところ、ミシガン大学の研究によれは不安に感じたことの80%は実際に起こらない、残り20%のうちの16%は準備しておけは対応可能だと学術的に発表しております。
出典:老後に楽しみをとっておくバカ(和田秀樹)
リスクは避けるものではなく、取るものである
臆病な人を安心させることは簡単です。良いことばかり言えばいいからです。しかし、それでは詐欺的なので、私はどんなことにもメリットとデメリットがあることを伝え、バランスを意識しています。ここでいうデメリットとは、リスクと言い換えられます。しかし、このリスクを聞いてしまうと急に怖気づいてちゃぶ台返ししてしまう人がいます。
リスクは確かに怖いものです。ただ、リスクは「そうなる可能性もある」ということに過ぎず、当然「そうならない可能性もある」のです。当たり前ですが、私はそうならないように最善の支援をします。しかし、「リスク」を「デンジャラス」と勘違いしてしまう人が少なからずおり、こういう人は新しいことに挑戦すること自体、性格的に向かないので、他の誰かに担当を変わってもらったほうがいいでしょう。
ここまでは、細かいことを気にしすぎて動きが遅い、不安に苛まれて動きが遅いという話をしましたが、これは、世界と戦う上で、The first mover’s advantage(先行者優位)を得られないという大きなマイナスを生みます。
海外の企業は、準備はそこそこにすぐスタートします。そして何かあればその都度運用しながら改善していきます。この差は何を生むのかというと、スピードと消費者の認知度の差を生みます。安心できるまで準備期間とし、スタートしない日本企業のサイトは、この間、消費者に認知されることはありません。この間はもっぱら海外企業の独擅場です。そして不安を解消し、満を持して日本企業がスタートするころには、海外企業が市場シェアの多くを取ってしまっており、日本企業は追いつくことも出来ず(追いつこうとしたら高額なプロモーション予算を組まないとならない)、結局実績を残すことなく撤退…。このパターンが目に見えてしまいます。
細かいことによく気がつくことや、君子危うきに近寄らずという感覚は、国内事業でのみとし、世界を舞台にするときはその意識を変えましょう。
海外では自己過大評価くらいでちょうどいい
前々回の「相手が知りたいと思うことをしっかり拾って伝えたいことを伝えているか」というコラムで、自分自身を英雄とアピールするアメリカの弁護士の話をしました。
オンラインにせよ、オフラインで海外進出するにせよ、日本国内での評価とは関係なく、「自分こそがこの分野の第一人者だ」然として振る舞える人が成功するとよく言われます。
日本国内では、遠慮するくらいが美徳とされ、さりげないアピールをしますが、さりげないアピールはアピールしているうちに入りません。日本国内感覚と比べたら図々しいくらいの感覚でちょうどいいです。
ある英語を教える外国人の講師は「正しい文法で話すことが英語ではない、思いを伝えるようにするのが重要だ。それは学ぼうとする人のマインドセットいかんによる」と言っています。また、私の知人で、ものづくりを支える活動をしている人も、「うまくいく企業は、まず経営者の熱量が高く、その熱量を他のスタッフにもうまく伝え、共有できているところだ」といいます。私も全く同意で、本人のやる気次第(人格を変えるくらいの心構え、マインドセット)です。結局はそれができる人が成功するのです。
テクニックや知識も重要ですが、それを聞いて満足して終わるのではなく、それを血肉化する意識がのほうが重要です。
セミナーの最後にかならず言うのですが、「知識より意識」なのです。
寄稿者 横川広幸(よこかわ・ひろゆき)ジェイグラブ㈱取締役

