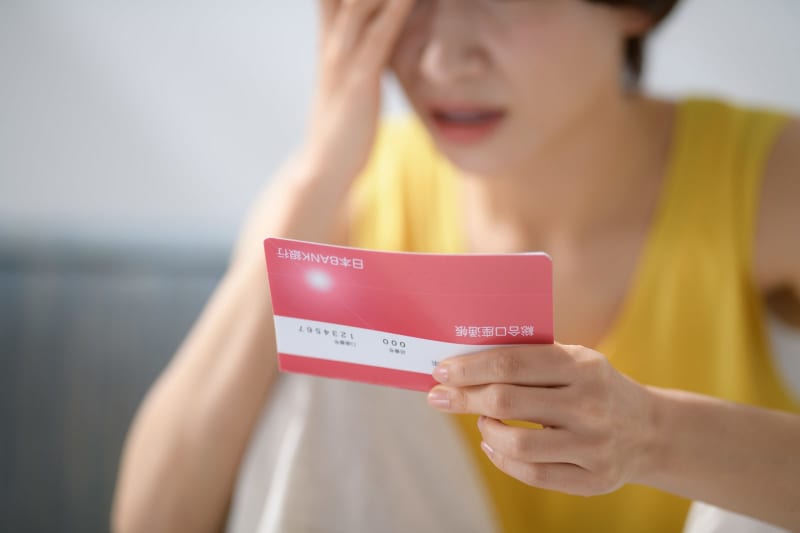
「十分な貯金があるので老後は大丈夫だろう…」そう思っていても、長寿時代のいまは注意が必要です。特に女性は長生き傾向にあり、油断をしていると資金が尽きてしまうリスクがあります。本記事では、一流企業に長年お勤めの加藤陽子さん(仮名・55歳女性)の事例をもとに、老後破産を未然に防ぐ対策についてMimi LIFE PLANNING OFFICE代表のFP村井氏が解説します。
人生100年時代、老後破産が忍び寄る現実
2050年、女性の平均寿命は90歳を超える(※1)との予測があります。そのため現在60代以下の人たちは、リアルに「人生100年」を念頭に老後資金を考える必要があります。
一流企業に長年お勤めの加藤陽子さん(仮名・55歳・独身)は、退職金・企業型DC、そして年金も満額積み立てし、さらに老後資金として金融資産2,500万円をすでに準備できています。
定年にはまだ5年あるし、噂の老後2,000万円問題も貯蓄的にはクリアしたと思ってはいるものの、ほんとうに老後はこれで大丈夫かと、FPにライフプランの相談をすることにしました。
現状の生活水準を維持したうえで、老後の介護費や医療費を見積もったライフプランニングをしてもらったところ、なんと80代前半には預金が底をつき、100歳時点では-3,500万円という現実を突きつけられることになってしまいました。
40代からしっかり貯めてきたのはよかったが…
加藤さんは若い時はそれなりにブランド物や海外旅行などでお金を使っていたようですが、40代になって生活の見直しをしました。生活は平均的な出費で浪費家でもなく、旅行や趣味でお金は使いますが、こちらも散財することなく、コツコツと積み立てもおこない、家計的には問題はありません。
では、なぜ老後赤字になってしまったのでしょうか。
要因1 住居費用の負担増
現在はお母さまが賃貸の賃料や光熱費をすべて支払い、加藤さんが生活費としてお母さまに一部お金を渡しています。ただ、お母さまが近々施設に入ることが決まり、2人暮らしだった加藤さんは今後1人ですべてを負担しなければならなくなります。都心の物件で、2人がゆったり暮らせるよう間取りも広いため、どうしても家賃・光熱費がかさみます。ここが赤字の大きな原因になりました。
50代以降の住居費は、収入があるうちに支出の見積もりをしっかり立てる必要があります。賃料や管理費の値上げ・戸建ての修繕など、今後50年間で集計すると金額が大きく膨らむことも多いため、早めの貯えや対策で老後赤字を防がなくてはなりません。
要因2 60歳以降の預貯金の積み増しができない
大企業の平均賃金は女性55歳~59歳で約298.5万円です(※2)。加藤さんは平均より上ではありますが、退職後は嘱託勤務となり収入は現在の7割程度になる予定です。そのため、賃料も考慮すると預貯金の積み増しは60歳以降難しいことがわかりました。
定年退職後に再雇用される予定の場合、賃金や雇用年数・勤務日数など雇用形態を早めに会社に確認しましょう。受け取る賃金が大きく減れば、預貯金の積み増しが難しい場合もあります。今回加藤さんも会社に確認し、新たに分かったことが多々ありました。
要因3 金融資産の中で預貯金の割合が「9割」以上
加藤さんの金融資産の内訳を確認したところ、90%は預貯金でした。定年時に受け取る予定の退職金を定期預金にしたら、さらに預貯金の割合は増加します。また、NISA、企業型DCも元本保証型や債券が大半で、資金を増やす目的というよりは安心・安全な守りのセレクトでした。
一見安全に感じる預貯金の「インフレリスク」を知る
要因3に挙げた「預貯金の割合が多い」ことは、いったい何が問題なのでしょうか?
数字的に見える額が減らないので、元本保証である預貯金は安心感があります。しかし、預金の利率よりも物価上昇率が高い場合、持っている資産価値が目減りする「インフレリスク」があります。
2024年2月の消費者物価指数(※3)の総合指数は2020年を100として106.9へ上昇。前年同月比は2.8%上昇しています。2024年メガバンクの定期預金も金利が少し上昇したとは言え1年物で0.025%(2024年4月現在)。物価上昇をカバーするには程遠い金利です。
インフレとはモノの値段が上がることです。言い換えると、1年前に1,000円で買えたものが、いまは1,000円を持っていっても買えず、1,000円の価値が下がったとも言えます。元本保証の安全資産のみで40年~50年後も問題なく暮らせるかどうかは、お金の使い方だけの問題でないことがわかるでしょう。
それでは、インフレリスクを回避する方法はあるのでしょうか。株式などは価格変動のリスクが大きく「怖いもの」と感じるかもしれません。ただ、中長期的な視点でみると「インフレヘッジ(インフレの影響を避けるための手段)」の効果があるとされています。
なぜ株を持つことがインフレヘッジになるのでしょうか。
インフレで全体のモノの値段が上昇➡上昇分を価格に反映➡同じ個数なら価格上昇分の売上金額が増加➡利益が増加、という流れになります。株価は企業の業績を反映した動きをするといわれますから、売り上げが上がれば中長期的にはその企業の株価は上昇すると考えられます。
もちろん、短期的には買い控えなどがあるかもしれません。ただ、必要なものは買うほかありませんから、中長期の視点でみると株式や株式が入っている投資信託などは「インフレヘッジ」の効果があると言われているのです。
旅行や趣味をあきらめないセカンドライフを楽しむための資産形成を始めよう
FPに話を聞き、さまざまな改善点が見えてきた加藤さん。ご相談のきっかけとなった住居費については、広さは狭くなっても通勤の便の良いところへという希望もあり、1人暮らしになったら賃料が低いところへの住み替えも視野に入れることになりました。
そして、60歳以降金融資産の積み増しができないので、55歳~59歳の5年間で預金の一部をNISAで積み立てし、75歳頃までは基本切り崩さず運用。65歳~74歳で年金(公的と民間)と足りない部分を貯金から切り崩しを開始し、75歳以降は投資から切り崩しを開始、預金と年金の三つ巴で生活の試算をしました。
また、NISAは年齢やリスク許容度を考慮しつつ、インフレ対策として株式も組み込み、守るだけでなく増やすこともできる配分に変更。預貯金は半分以上手元にしっかり確保し退職金も投資に回さないことにしました。これまで頑張ってきた加藤さんが旅行や趣味をあきらめない、老後もいままで同様楽しめるライフプランです。
加藤さんも「いま行動できてよかった。お金が無いとなった時では遅かったかも」と老後の安心感を持たれたようでし、頑張って働いてきたのですから自由で楽しいセカンドライフを送っていただきたいと切に思います。
人生100年時代、50代での投資はもう遅いということはありません。年金と金融資産だけで生きていけるか心配な方は、一度現在のご自身の資産や生活の棚卸をお勧めします。老後破産にならないよう行動を起こせば、いまなら間に合うかもしれません。
参照
※1:内閣府「令和5年版高齢社会白書」
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html
令和4年度高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状
第1章 高齢化の状況>第1節高齢化の状況>1高齢化の現状と将来像
※2:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査結果の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2023/index.html
(4)企業規模別にみた賃金>第4表企業規模、性、年齢階級別賃金、対前年増減率及び企業規模間賃金格差
※3:総務省統計局「2020年基準消費者物価指数全国2024年(令和6年)2月分(2024年3月22日公表)」
https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.html
村井 美則
ファイナンシャル・プランナー

