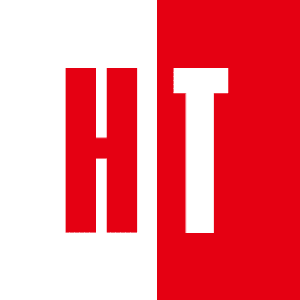人生100年時代を見据え、住宅の残価保証を行う(一社)移住・住みかえ支援機構(JTI)の大垣尚司代表理事は、「金利が上昇していく局面では、アフォーダビリティーという、これまでと全く異なる差別化の軸が必要となる」と話す。

―マイナス金利解除で住宅ローン、住宅業界にどのような影響が出てくると見ていますか。
まず、マイナス金利解除が、住宅ローン利用者に与える影響について考えてみましょう。
銀行は顧客からの預金を受け取り、その預金を元に貸し出しを行います。預金の期間は住宅ローンの期間より非常に短いため、銀行が住宅ローンを貸す場合、預金の金利が上がって住宅ローンの金利より高くなってしまう「金利リスク」と、預金の量が途中で減ってしまって住宅ローンを貸し続ける原資が不足する「流動性リスク」があります。多くの銀行は前者の金利リスクを避けるため、住宅ローンを変動金利建てにしています。これに対して、流動性リスクのほうは、長期にわたり日本銀行が市場に大量に資金を供給する量的緩和政策がとられていたために、あまり誰も意識してきませんでした。
しかし、3月にマイナス金利・量的緩和政策が変更されて変化の兆しが少しずつ現れています。まず、若年層の東京や大都市への集中の結果、親世代が地方銀行等に預けていた預金が相続等をきっかけに都市銀行に移動しています。ネットバンキングの普及によって、少しの金利差でも高い預金金利を提供する銀行にお金を移す人が増えています。
ゼロ金利政策が緩和されたといっても、当面、日本銀行は急激な利上げに非常に慎重ですが、もし今後何らかのきっかけで、市場金利が急激に上昇すると、預金ではなく、マネーマーケットファンド(元本リスクが非常に低い上に高利回りの短期の投資信託)に資金が移動することも考えられます。実際に、1980年代のアメリカで高金利政策がとられたときは、そうした商品に銀行預金が流出し、資金不足に陥った銀行が銀行間市場と呼ばれる市場からの調達に依存することとなり、調達コストが急上昇して軒並み赤字化するという問題が発生しました。住宅ローンをファイニーメイのような政府系金融機関が購入してモーゲージバック証券という政府の信用力に裏付けられた特殊な債券に転換して、証券市場に売却する、公的住宅ローン証券化制度はこうした問題に対処するために生まれてきた金融技術なのです。
本来、預金はいつでも引き出せる非常に短期の資金です。だからこそ銀行は非常に低い利子しか付けません。しかし、実際には、みなさんはすぐ使わない、あるいは万が一のためにお金を預金に預け入れておくわけですから、かなりの金額が長期間「根雪」のように滞留します。表面上は利子がきわめて低い短期資金なのに実際には長期の資金として活用できるという預金の特徴を活用することで、銀行は35年というような非常に長期の住宅ローンを低利で安定して貸し付けることができるのです。
しかし、これは預金が安定して銀行に滞留してくれていることが大前提です。そして、この大前提が最も崩れやすいのが、金利が低利から高利へと変動するときです。特に変化が短期間に起こると、「いつでも引き出せる」という預金本来の特徴が裏目に出て、前述のようにより高い他の銀行の預金や他の金融商品への資金がシフトし、超低利の預金の不足分を高利の市場資金で補てんせねばならなくなり、これを住宅ローンの金利に転嫁できなければ収益が急速に悪化します。
そして、今がまさにその前夜とも思われるわけです。
特に、金融政策変更後の激変緩和のために日本銀行が金利を少しずつ慎重に上げていこうとすると他の通貨との金利差が広がって円の魅力が下がるために円安が進んでしまいます。しかし、これを回避しようとすると金利が想定以上に上がってしまうといったディレンマが生じやすい状況になっています。これを住宅事業者の目から見ますと、金利を低めに誘導すると円安が進んで資材価格の上昇につながりやすくなる一方、円安を回避しようとすると金利の上昇を容認せざるをえなくなって住宅ローンが借りにくくなるというディレンマになりえます。
住宅ローンは儲かっているのか
―金利の上昇局面に入るなかで、変動金利建ての住宅ローンの金利はすぐに上がるのでしょうか。
この記事はプレミアム会員限定記事です。
プレミアム会員になると続きをお読みいただけます。
新規会員登録
(無料会員登録後にプレミアム会員へのアップグレードが可能になります)
アカウントをお持ちの方
ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。