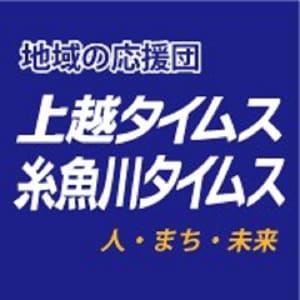上越市の港町1、2町内会は19日、津波からの避難を想定した防災訓練を実施した。元日の能登半島地震での被害や経験も踏まえ、車での避難なども見据えた現実の避難行動に近い形式で行った。
同町内では毎年、防災訓練を実施していたが、コロナ禍でここ5、6年中止しているさなか、元日に能登半島地震が発生。町内に6箇所ある避難所のうち、旧古城小への避難が集中して、周辺道路の渋滞や避難所開設に支障を来すなど、いくつもの課題が明らかとなった。
今回は、訓練当日の午前9時に大地震警報、3分後に大津波警報が発令されたと想定。15分に第一波到達を予想し、住民は必要最低限の物を持ち、最寄りの避難所へと向かった。旧古城小では、グラウンドを駐車場として開放して役員が誘導を実施。20分までの避難行動で、計156人が避難した。
訓練後の意見交換会では、避難の難しさに関する声が相次いだ。港町1の竹内祐子さん(88)は、娘が運転する車で避難したが、足腰が弱っているために屋上まで上がれず。元日の地震では、車で高田の実家まで向かったが、渋滞で2時間かかったという。「車はどうしても必要だし、若い人がいない平日の日中に地震が起きたらどうすればいいのか」と問いかけた。このほか、「体が不自由で逃げられなかった人が近所の人の機転で助かった」「旧古城小の備蓄が少な過ぎて避難所として使えない」などの声が上がっていた。
同町内防災委員会の泉秀夫さん(82)によると、これまでの訓練でも町内の避難所について繰り返し周知したが、元日の地震では住民の80%が古城小へ避難。また、車避難の割合は同校で50%、それ以外の場所で70%に達したという。「建物の屋上など、安全な高さまでの避難も考えると7分での避難完了が理想」と解説。「場所、時間、ルートは繰り返し教え、自分たちで考える必要がある。今回の地震では、わざわざ遠い場所まで避難している人も多かった」と指摘し、「車での避難の効果、より向かいやすい避難所など、検証を継続していきたい」と語った。