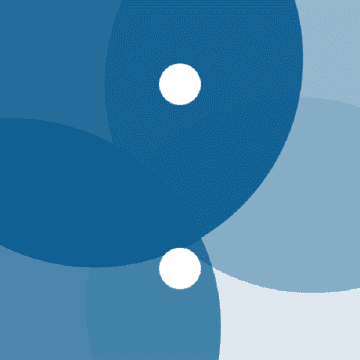Takahiko Wada
[東京 20日 ロイター] - 日銀が20日公表した1990年代半ば以降の企業行動に関するアンケート調査の集計結果で、大企業・中堅企業の製造業を中心に、金融緩和の効果・副作用双方で為替の影響を指摘する回答が目立った。金融緩和については、借り入れ金利の低下などを通じ、幅広い企業の経営や前向きな投資の支えとなったことが確認されたとした。
<大手・中堅製造業は7割超が「為替の安定」期待>
金融政策の多角的レビューの一環で実施した調査で、過去25年間の金融緩和の効果について、業種・規模を問わず借入金利の低下を挙げた企業が最多となり、7割―8割程度に上った。一方、大企業・中堅企業の製造業の3割程度が「為替市場の動向」と回答した。大企業や製造業を中心に、2010年代前半の大幅な円高からの反転を念頭に、輸出競争力の改善や円ベースの海外収益の増加を評価する声が聞かれた。
一方、金融緩和の副作用としては、企業の新陳代謝の停滞や金融機関の収益力の低下との回答が多かった。ここでも「為替市場の動向」との回答が大企業・中堅企業の製造業では5割弱と目立った。近年の円安進行や変動の大きさを念頭に、原材料コストの上昇や事業計画策定への影響に加え、外国人労働者の採用への影響も指摘されていた。
金融政策に求めることとしては「物価の安定」や「景気の安定」への回答が目立つ一方で、大企業・中堅企業の製造業では「為替市場の安定」との回答が7割を超えた。
<物価賃金とも「緩やかに上昇」に圧倒的な支持>
日本の賃金・物価は長らく上がりづらい状況が続いてきた。1990年代に物価上昇率がゼロ%付近まで低下し、コストの価格転嫁が困難になった最初のきっかけは何だったのか聞いたところ、バブル崩壊や金融システム不安を受けて、消費者の低価格志向が強まったことや企業のコストカット意識が急速に強まったことを挙げる企業が多かった。
現在では8割以上がどちらかと言えば価格転嫁がしやすくなっていると回答。その理由として、値上げは「仕方ない」との認識が広がったとの回答が業種・規模を問わず6割以上に上った。
今年の春闘では5%以上の賃上げ率となっている。賃上げスタンスを積極化している理由としては「労働者の確保に支障が出ることへの懸念」との回答が最多となった。
物価と賃金がともに「緩やかに上昇する状態」と「ほとんど変動しない状態」のどちらが事業活動上好ましいかとの質問には、「緩やかに上昇」が圧倒的に多かった。「賃金が増えると家計のマインドや消費にプラス」や、「価格転嫁が容易になり収益を確保しやすい」といった回答が多かった。
現在の設備投資スタンスについては、7割以上の企業が過去対比で積極化していると回答。人手不足対応の投資のほか、大企業を中心に「脱炭素やDX関連投資の必要性」の回答が多かった。
日銀はアンケート結果を踏まえ、企業行動に「大きな変化が生じている途上にある」と分析。こうした変化が広がっていくか、変化した企業行動が今後も定着・持続していくかが先行きの経済・物価情勢を占う上で「きわめて重要な要素になる」とした。
今回の大規模な企業調査は多角的レビューの柱の1つ。昨年11月から今年2月ごろにかけて、大企業から中小・零細企業まで幅広い企業規模・業種の2509社の非金融法人を対象にアンケート調査を実施し、2256社から回答を得た。2256社の半数以上に対し、日銀本支店・事務所の職員が面談してヒアリング調査を行った。