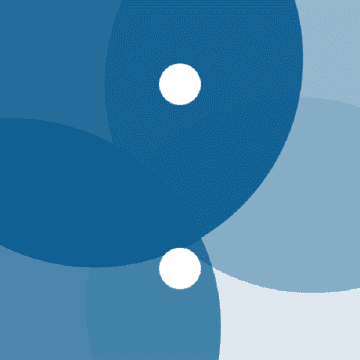東京都が主催する持続可能な新しい価値やアイデアを生み出す国際イベント「SusHi Tech(スシテック) Tokyo 2024」が開催中だ。(期間:2024年4月27日~5月26日)
同月15、16日には、グローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2024 Global Startup Program」が東京ビッグサイトで開かれ、気候変動や脱炭素など世界的課題を解決するテクノロジーやアイデアを競うピッチコンテストのセミファイナル、ファイナルが催された。
コンテストの応募総数は、507社(世界43の国・地域から)。5分間のプレゼンテーション(英語)と質疑応答の内容が審査され、ファイナルには7社が進出した。
優勝は、独自の発酵技術で食料廃棄物をバイオ原料に変えるなど、未利用資源を価値ある製品に転換する「発酵アップサイクル技術プラットフォーム」を提案した株式会社ファーメンステーション(日本、登壇者は同社代表取締役・酒井里奈氏)だ。
アフリカの農家の信用を可視化
残る他6社も斬新な技術や発想を披露。
その中でFNNプライムオンライン編集部が注目したのが、アフリカの貧困問題解決のために起業したDegas株式会社(日本)である。
プレゼンを行った同社CEO・牧浦⼟雅氏は冒頭、自身の経験を語った。
「2013年、大学に入学する前にアフリカのルワンダでしばらく過ごしました。そこで、1日3ドル以下で生活する小規模農家の方々と出会ったのです。
その5年後(2018年)、再びルワンダを訪れると、都市の発展には驚かされたものの、都心以外は何も変わっていませんでした。依然として人々は厳しい生活に苦しんでいたのです」(編集部訳)
この状況を何とかしたいと思い至った牧浦氏は同年、Degasを設立する。
驚くべきは彼の着眼点だ。プレゼンで言及された現地の課題の一つは「農家の資金調達」。
小規模農家に資金を提供してくれる金融機関を探すことは難しい。
なぜなら、金融にとって大切な「信用」が、特に小規模農家において評価されにくかったからである。つまり、金融業者が融資を行いたくても、与信審査が難しかった。
そこで彼は、農家の信用をデジタルの数値に落とし込んだ。「耕作スコアリング」「リジェネラティブ農業指数」などの指標を設けることで「見える化」した。
各農家の「まじめ度」なども可視化し、それを与信に活用、信用の裏づけとし、資金調達を行えるようにしたのだ。
貧困問題の解消+気候変動
耕作への評価が指標になるという話はわかりやすい。
一方で、たとえば、リジェネラティブ農業(=RA)とは、耕作によって生まれる炭素を抑え、土壌の有機物を増加させ、再生力を高める農法を指す。
彼は、その実施状況もスコアに落とし込んだ。各種データは、地上と衛星の両輪を用いて収集、アプリで見られるようにしている。
しかも、土壌に炭素を隔離するなどして温室効果ガスの排出削減に貢献した小規模農家には追加収入も提供される。
この仕組みによって、状況は変化した。
「去年、私たちは2万6000軒以上の小規模農家に資金提供を行い、会社設立以来、マイクロファイナンスや銀行からの借り入れが過剰な4万6000軒以上の農家への資金提供を実現しました」
「去年、97%の農家が収入を倍増させました」
貧困問題の解消だけではない。先に述べたRAの推進により、脱炭素化も進め、気候変動にも対応しているのだ。
さらに牧浦氏は、新たなモニタリングプラットフォームについて言及した。
衛星データをすでに活用している同社だが、AIによる画像学習を用いて、より高品質なデータを取得できるモデルを構築。
これにより、農業や炭素をモニタリングすることに加え、洪水などの検知をより精度高く行えるようにした。この仕組みは、国全体への活用も期待できるだろう。
問題が落ちていたから、拾っただけ
Degasは現在、ゲイツ財団をはじめ多くのパートナーと共に事業を展開している。
牧浦氏のモチベーションの源はどこにあるのだろうか。ルワンダの経験は何をもたらしたのか。プレゼン後、彼は率直に語った。
「目の前にゴミが落ちていたら、拾うじゃないですか。それと同じです。問題が落ちていて、拾ったら、それが『6億人のアフリカ小規模農家の所得向上』だった。だからやっているんです」
本気で世界を変える起業家のマインドに直接触れられる。こうした出会いは「SusHi Tech Tokyo」が提供する大きな意義と言えそうだ。
その他、ピッチコンテストのファイナルでは、ハエの生態を活かして廃棄物を資源に変えるEntomal Biotech Sdn Bhd.(マレーシア)、「水冷方式」を用いた冷蔵技術でフードロス削減に貢献する株式会社クールイノベーション(日本)。
「自然に還るペットボトル」の開発でプラスチック汚染の解消を目指すBUYO Bioplastics Co. Ltd.(ベトナム)、「腫瘍アバター」等を用いて抗がん戦略を開発しているCancerFree Biotech Ltd.(台湾)。
海事に関わる業務のデジタル化で温室効果ガス削減を目指すE-Port Pte. Ltd.(シンガポール)がピッチを行い、聴衆の好奇心をかき立てた。
「SusHi Tech Tokyo 2024」は5月26日まで開催される。時代の最先端を肌で感じる機会を得てみてはいかがだろうか。