
お笑い芸人や俳優として活躍するかたわら、小説家や絵本作家としての顔をもつ鳥居みゆきさん。2024年3月上旬と中旬に「児童発達支援士」と「発達障害コミュニケーションサポーター」の資格を取得したことをインスタグラムで報告しています。鳥居さん自身、小学校や中学校時代には、自分のこだわりが強いがゆえに“生きづらさ”を感じていたそう。そこで、自身の幼少期について、また、こだわりをどう克服していったのか、発達障害を抱えるママやパパたちに向けて伝えたいことを聞きました。
全2回インタビューの2回目です。
芸人・鳥居みゆき、Eテレの番組出演をきっかけに、子どもの発達支援の資格を取得!母でも支援員でもない私だからできること
笑えなかった、苦しい小学校時代。先生のサポートや、無理強いしない両親に支えられた
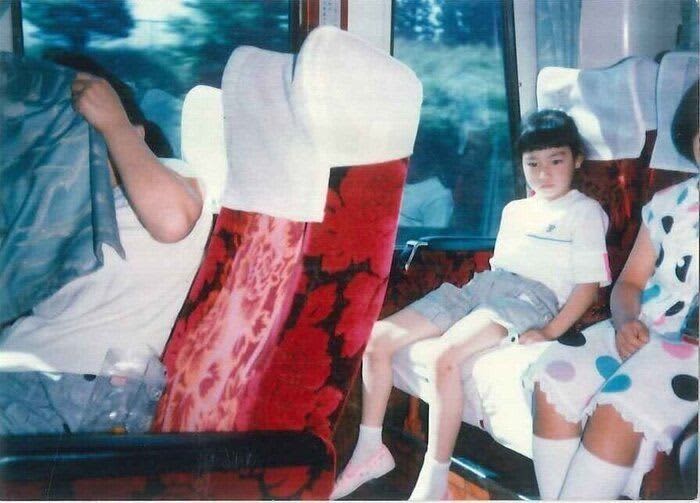
――鳥居さんは小さいころ、どんな子だったんですか?
鳥居さん(以下、敬称略) 私は小さいころから、あまり友だちがいませんでした。自分でも、友だちにどう話しかけていいのかわからなかったんです。それに、ずっと笑わない子でした。“笑う”ということを知らなかったんだと思います。
でも心の中では、「本当はもっと、みんなと普通に話ができたらいいのにな」と思っていました。それで、友だちから話しかけてもらうために、小学校で集団予防注射をするときには、一番に率先して注射を打ちに行っていたんです。みんな注射を嫌がるので、「大丈夫な人から打ちに行って」と先生から言われていて。一番に注射を打つと、後に並んでいる子たちから「痛かった?」「どうだった?」と話しかけられるんですよ。その日だけちょっとヒーローになれる、みたいな感じです。
あとは、中学生になって、スピーカーから問題が流れるリスニングのテストがあったんですが、それが全然できなかったのをよく覚えていますね。聞き取れないからあせってしまって、「わ〜〜〜!!」とパニックになってしまって、流れてくる音が余計に大きく聞こえてしまうんです。パニックになることでみんなの邪魔をしてしまって、「鳥居さん、あとで受けましょうね」と先生が落ち着かせてくれたりしました。みんなからは、「うるせえな」とか「なんなの、あの人?」と言われて、あのときは気まずかったし、すごく苦しかったですね。
――そんなとき、だれかに助けを求めていましたか?
鳥居 私、先生にはとても助けてもらったなと思うんです。たとえば、学校の机って時々不安定なものがあるじゃないですか。自分の机には、紙を挟んでガタガタしないようにするんですが、別の机に座る機会があって、その机がガタガタしていると、それだけで「わ〜〜〜」とパニックになってしまうんです。そのときにも先生が助けてくれて、「大丈夫だからね」「あとでやろうね」と言ってくれました。
それから、私は偏食がとにかくひどくて、食べられないものがあっても許してもらったり、お弁当を持参させてもらったりしていましたね。
それと、うちの家はすごく自由な家庭で、両親にも助けられました。父も母も、嫌なことはやらなくていいよ、という方針。代わりに、好きなことをとにかく突き詰めなさいと言われてきました。だから私の場合は、できないことを無理にやったり、やらされたりということもなかったです。
まわりの反応を見てどうすればよかったかを考えて対応することで、自分なりの成長も

――こだわりが強いことで、つらい経験もたくさんあったようですが、鳥居さん自身が変わっていったところもあったんですか?
鳥居 小さいころの私は、『ウォーリーをさがせ!』の本の中でウォーリーを見つけると、丸をつけちゃうクセがあったんですよ(笑)。ほかの子からしたら当然、「何やってんの!」ってなりますよね。それで、「何でみんな怒っているんだろう」「どうして怒られているんだろう」と考えてみたんです。その結果、ペンで書いていた丸を鉛筆で書くようになりました。
こんな感じで、まわりの反応を見ながら、私も少しずつ変わっていきました。大人になってからは、こういった変化は顕著に出ましたが、子どものころから少しずつ成長していたと思います。ただ、強いこだわりに関しては大人になっても変化はないです。嫌なものは嫌!たぶん、そこは変わることはないですね。
これは最近気づいたのですが、私は、耳で聞いたことは理解できないようなんです。中学生のときに苦手だったリスニングは、あせりが原因で聞き取れないのだと思っていました。でも、大人になってあらためて考えてみると、耳で聞くだけでは人の名前を覚えることができなくて、名刺などで目で見て初めて覚えることができるんです。
だから、人と話していても、相手が何を言っているのか理解するのに、すごく時間がかかります。そのせいで、だんだんと話がかみ合わなくなってしまって…。これは大人になって治ったわけではなくて、「こうやってやればいいんだ」と思うものを実践しているだけなんです。
私が人と話すときに実践しているのが、人の話の序盤を聞いた段階で、後半にその人が言いそうなことを予測しちゃうんです。そして、その予測したことを頭の中で文字にして、それを読んでしゃべるという作業をしているわけです。大人になってからは、その作業がかなりスピーディーにできるようになったから、会話が成立するように見えるんです。作業が早くできるようになって、自分の苦手を少し克服することができたことで、自分でも何とか頑張れるものなんだと思いました。
――困っていることも、それを克服する術をだんだんと身につけていったんですね。
鳥居 ただ、本当に無理なことは、何回やっても無理なんです。私、リボン結びやヘアアレンジがまったくできないんですよ。そこで、靴ひもや衣装のリボンは、マネージャーさんにお願いするようにしています(笑)。髪型は、結んだりアレンジしなくても、かわいく見えるスタイルに。もちはもち屋というように、「できないことは、頼れる人に頼ればいいじゃん!」って思っています。何度もトライして努力したなら、それでいいんですよ。あとは、頼るときに、「おねが〜い!」って言える愛嬌(あいきょう)を持つこと。これは、自分の努力でなんとかするしかないです。
だれしも、長く生きてきて、大人になっていくにつれて、これは不便だなと感じることが必ず出てきますよね。私は、ストレスがたまってしまうと、すべての音が同じレベルのボリュームに聞こえてきちゃうことがあるんです。そのときは耳せんをして、すべての音をシャットアウト。自分の中で、ゼロにはならないけれど、折り合いをつけて生活しています。
大人になれば、私のように、折り合いをつけたりして学んでいくんですが、子どものころは、もがきまくるしかないんです。「何でこんなに苦しいんだ」と、訳がわからない状態。本人じゃないと、その苦しさはほかの人には感じ取ることはできないかもしれないけれど、「今、困ってます」の顔をすれば、だれかは気づくはず。だから、子どもたちの“顔”を見ることって、すごく大事だなって思います。
ママやパパの変なプライドは取っ払って、まずは、子どもの表情を見てほしい!
――ママやパパが子どもたちと接するにあたって、大切にしてほしいという鳥居さんの思いはありますか?
鳥居 「障害」という言葉がついていると、様子見をしてしまう保護者が多いそうです。「うちの子、ちょっと話すのが遅いけど、様子を見ていれば治るんじゃないか…」というママ・パパも多いと聞きます。でもまずは、子どもの顔や表情を見てほしいんです。
様子見って、実は一番難しいんですよ。「様子を見て、必要そうなら療育に行こうかな」と思っていても、「障害がある」と言われたくない気持ちやプライドがママ・パパに少しでもあるなら、そこは取っ払ってほしいなと思いますね。
自分の思い込みや願望を強化する情報ばかりに目が行ってしまい、そうでない情報を軽視してしまう、そんな確証バイアスに惑わされて、「どうせ大丈夫だろう」とか「こうだから、大丈夫だろう」と親の都合のいいように判断しちゃわないで、公平な目で子どものことを見てほしいです。まずは、相談に行くだけでもいいと思います。少し様子見をするのであれば、どこまで様子を見るかをきちんと決めておくのもいいのではないでしょうか。
2023年にアメリカ疾病予防管理センターが発表した調査結果によると、自閉スペクトラム症の子ども(8歳児)の割合は、36人に1人はいるそうで、実はめちゃくちゃ多いんです。発達障害自体は、これはもう個性だと思うんですよね。ただ、その個性によって生じてしまいやすい、二次障害に気をつけてあげることがとても大事です。
――二次障害というのは、どんなことなんでしょうか。
鳥居 強い個性によって生じる、うつ病、いじめ、不登校、引きこもり、対人恐怖症、自殺念慮などです。これらは、自己肯定感が低下してしまうがゆえに起こってしまうことが多い。だから、自己肯定感の低下を防ぐことがとても大切です。
発達障害どうこうでこだわっているのは親の問題であって、その後に引き起こされる二次障害が、子ども自身にとっての大きな大きな問題。学校でいじめにあってしまい、それによって本人が攻撃的になってしまう、そのほかの健康被害が出てしまうなどの二次障害に、ぜひとも目を向けてほしいんです。発達障害は個性であるいうことへの理解や、二次障害についても多くのママやパパたちに向けて広めるために、自分も少しは手助けができればいいなと思っています。
――診断が早くつけば、その後の発達は変わるのでしょうか。
鳥居 診断は早ければ早いほどいいと思います。でも、診断が早くついたからと言って、症状や特性が劇的に変わるわけではないというのは知っておいてほしいですね。発達障害の診断は、本当に難しいんです。というのも、障害は一つだけではなくて、ADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)、LD(学習障害)などがちょっとずつ入っていることが多いんです。こういう特性は、実はみんなに当てはまることでもあるんですが、その濃度が違うだけなんですよ。
社会がこれだけ多様化しているので、特性を持った子どもたちがこれからもっと生きやすい社会になっていくんじゃないかなと期待しています。
大人になってから診断がつく人もいますよね。今まで、まわりから「変」って言われていたなという人で、その答え合わせをしたい人や、大人になってからも困っているという人は、診断をつけるのもありですよね。でも私はむしろ、困っていないので(笑)!これは個性であって、そして仕事にもつながっているので、私のこの個性は“ありがたいもの”だと思っています。
お話・写真提供/鳥居みゆきさん 取材・文/内田あり(都恋堂)、たまひよONLINE編集部
黒柳徹子、『窓ぎわのトットちゃん』の続編が42年ぶりに。戦争が起こっている今こそとアニメ化も。あの時代の空気を伝えていくのは私の使命
小さいころは、こだわりが強く、友だちとの接し方もわからなかったという鳥居さん。生きづらく苦しかった経験の中でも、まわりの反応を見て考えながら、その解決策を模索していったようです。そして今は、自分なりの対応力と愛嬌で、“個性”として受け入れ、さらには“ありがたいもの”と前向きにとらえています。
●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。
●記事の内容は2024年5月の情報で、現在と異なる場合があります。
鳥居みゆきさん

PROFILE
お笑い芸人・俳優。1981年、秋田県生まれ、埼玉県育ち。2008年、2009年の『R-1ぐらんぷり』で決勝に進出し、白いパジャマ姿で両手にはマラカスやくまのぬいぐるみという“マサコ”のキャラクターで人気に。日本テレビ系ドラマ『臨死!!江古田ちゃん』では主演を務めるなど、女優としても活躍。2009年に小説『夜にはずっと深い夜を』、2012年に『余った傘はありません』、2017年には絵本『やねの上の乳歯ちゃん』も発刊。
