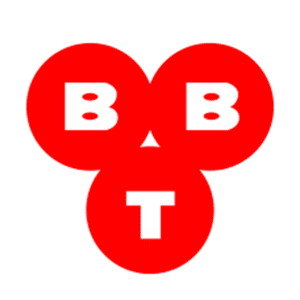ベニズワイガニやシロエビの漁獲量減少と能登半島地震の因果関係について調べる富山県の調査が進んでいます。
富山湾で先週、始まった調査は、20日から調査の範囲が沿岸部の比較的浅い海域に移りました。
これまでの調査で、地震で発生したと見られる海底地すべりの痕跡も見つかっています。
調査は、県水産研究所が13日から実施していて、先週は富山湾の沖合、水深300メートルから700メートルの漁場で、大型の調査船を使った海底の堆積物の採集が行われました。
20日からは沖合約5キロの沿岸部を調査範囲とし、小型の調査船を使って水深15メートルから300メートルの海底49地点で堆積物を採集します。
*県水産研究所 藤島陽平研究員
「しっかり今回採取した堆積物を分析し、数値化することによって、実際にどういう影響があったかを科学的に証明できれば」
今年元日の能登半島地震以降、富山湾ではシロエビやベニズワイガニの漁獲量が大幅に減少しています。
県水産研究所によりますと新湊や滑川、魚津など県内の漁港で地震発生後の3カ月間に水揚げされたベニズワイガニは例年の3割ほどに留まっています。
*県水産研究所 三箇真弘さん(5月14日放送)
「海底地すべりによりカニが生き埋めになったり、カニが別の場所に移動した可能性が考えられる」
漁獲量減少の要因として懸念されているのが、地震で発生した海底地すべりの影響です。
今回の調査では、先週、水深300メートルより深い海域の調査で、海底地すべりが起こったと見られる形跡が確認されたということです。
*県水産研究所 藤島陽平研究員
「大体8センチの深さの所に、表層の色をした堆積物が見られたので、8センチよりも上の所に新たな堆積物が流れ込んだような痕跡が見られた。もしかしたら、地震の海底地すべりの可能性もあると感じた」
地震による海底地すべりで、富山湾の漁場はどのような影響を受けたのか。
県は今回の調査で採集した海底の堆積物を分析し、カニやシロエビなどのエサとなる生物の数など複数の項目について地震発生前の調査結果と比べることで、変化の状況を取りまとめます。
小型船の調査は予備日を含め25日までにすべて終わる予定です。
県水産研究所の調査。
富山湾の何を調べることで、どんなことが分かるのかまとめました。
まず、調査範囲は富山湾全域70地点で、先週は水深300メートルから700メートルの比較的深い海域の21か所が対象でした。
この調査で、海底地すべりが発生したとみられる形跡が見つかったということでした。
そして、20日から今週末にかけて行われるのが沿岸部の水深15メートルから300メートルの海域49地点です。
これらの調査地点では、採泥器と呼ばれる機械を沈めて、海底の堆積物、泥を採集します。
そして、その泥の中にベニズワイガニやシロエビのエサとなる海底生物がどの程度、含まれているかを調べます。
ゴカイやイソメなど海釣りでもエサとして使われるような小さな生き物の種類や個体数です。
さらに、魚などの糞や死がいなどの有機物の量も調べます。
どちらも、水産資源となる魚介類の栄養となりますが、多ければ多いほど良いというわけではなく、適切な量が保たれているかがポイントです。
また、海底に堆積した泥の粒子の大きさや性質などを調べることで、地震前の調査結果と異なる点があれば、海底地すべりなどで他の場所の堆積物が流れ込んできた可能性があるということです。
県水産研究所は、これら主に3つの項目で分析することにしていて、調査結果は概要を約2カ月でとりまとめ、今年度末には最終報告として発表するとしています。