朝ドラ『虎に翼』では、高等試験を目の前にして、男爵令嬢・桜川涼子(演:桜井ユキ)が法律家の道をあきらめ結婚を選びました。
父親の出奔後「母を見捨てることはできない」と言って婚約を決めた涼子様でしたが、なぜ彼女は志半ばで不本意な結婚をしなければならなかったのでしょうか?
今回は、華族令嬢の結婚事情について解説します。
目次
華族とは?

画像. 華族たちの洋館建設ブームに影響を与えた有栖川宮邸. public domain
華族は、明治2年(1869年)から昭和22年(1947年)まで存在した日本の貴族階級です。
明治2年(1869年)、それまで「公卿」と「諸侯」といわれた身分を統一し、新たに「華族」が創設されます。
「公卿」は公家、「諸侯」は大名のことで、一般的に公卿出身の華族は「公家華族」、諸侯出身の華族は「武家華族」と呼ばれました。
さらに明治17年(1884年)には華族令によって五爵制が制定されます。華族は爵位の高い順に「公爵」「侯爵」「伯爵」「子爵」「男爵」と序列化されました。
公爵・・・五摂家、徳川宗家、維新に勲功のあった公家や旧藩主など。
侯爵・・・旧清華家、徳川御三家、15万石以上の旧藩主、維新に功のあった藩士など。
伯爵・・・公家の大臣家、徳川御三卿、5万石以上の旧藩主。
子爵・・・大臣家以下の公家、5万石未満の旧藩主
男爵・・・公家、諸侯の分家、大社の神官や大寺の僧侶など。
華族になれたのは身分の高い元公家や武士、国家に大きく貢献した人々であり、華族令制定とともに504家の華族が誕生しました。
昭和22年(1947年)に華族が廃止されるまでの63年間に存在した華族の総数は1011家。彼らは「皇室の藩屏(はんぺい)」として位置づけられ、さまざまな特権が与えられていました。
財産面では、第三者から差し押さえられない華族世襲財産がありました。世襲財産とは、華族の体面を保つために必要とされる資産のことです。
教育面では無試験で学習院や女子学習院に入学できたり、学習院高等科を卒業した子弟は、無試験で東京帝国大学、京都帝国大学に入学できたりといった特権がありました。
その他にも爵位の世襲や貴族院議員への就任といった特権をもっており、華族とは天皇を補佐するために作られた特権階級だったのでした。
華族の相続人は男系男子のみ
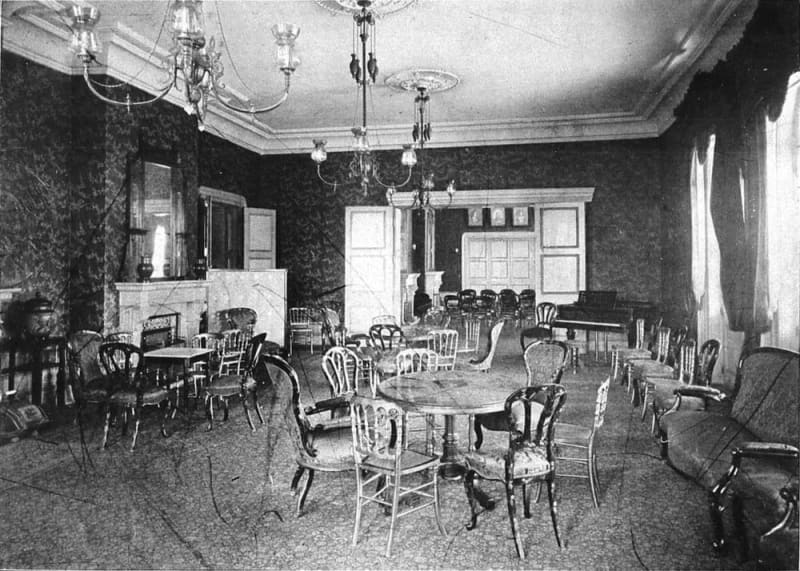
画像.華族会館の内装 (1912年東京). public domain
特権階級である華族の相続は男子に限定されており、女子しかいない場合は宮内大臣の認許のもと婿養子をとることになります。
女性は華族家の戸主になることはできましたが、爵位を継ぐことができませんでした。女子継承者のみの華族家は、婿や養子を取らなければ、爵位を返上し家を廃絶することになったのです。
皇族が男系を維持するように華族も男系であるべきとされ、養子は「男系の六親等以内の血族」が原則とされました。
宮内大臣から養子相続の認可を受けるための条件には、男系六親等以内のほか、「本家または同家の家族もしくは分家の戸主または家族」、「家族の族称をうくるもの」がありました。
つまり、「男系六親等以内で、同じ先祖をもち、華族の身分をもつもの」だけが華族家の養子となれたのです。
こうした男系重視の継承規定などから、華族は同族結婚や養子縁組をして家を存続させたのでした。
『虎に翼』の涼子様はひとり娘ですので、父親の出奔によって戸主を失った後、桜川家を存続させるには婿を取るしかなかったのです。
華族令嬢の結婚相手選び

画像.鹿鳴館 public domain
華族は世間から一挙手一投足を見られる存在であり、不品行は家名を汚すだけでなく、爵位の返上につながるものでした。
華族のお嬢様の結婚についても自由恋愛は認められず、家の格式、爵位、年齢などが考慮され、本人のあずかり知らぬところで縁談が進められました。
なによりも親たちが娘の幸せを第一に願い慎重に相手選びが行われ、昭和戦前期には結婚前に相手との交際期間が設けられ、気に入らなければ断る機会も与えられていました。
『虎に翼』の涼子様と同じく華族のひとり娘だった京極典子さんは、宮内省の許可が必要なため結婚相手選びに苦労したそうです。
武家の名門、旧峰山藩主家、京極高頼子爵を父に持つ典子さんは、早くに兄弟を亡くし京極家の跡取りとして大切に育てられました。
彼女の結婚相手は京極家の家督相続者となるため、宮内省の承認を得られる人物でなければならず、相手選びは難航します。
父親が奔走する中、加藤男爵家五男の鋭五氏の自薦をきっかけに結婚話は進み、まず鋭五氏が京極家の養子となることが宮内省より認許され、次いで典子さんとの婚姻が認許されました。
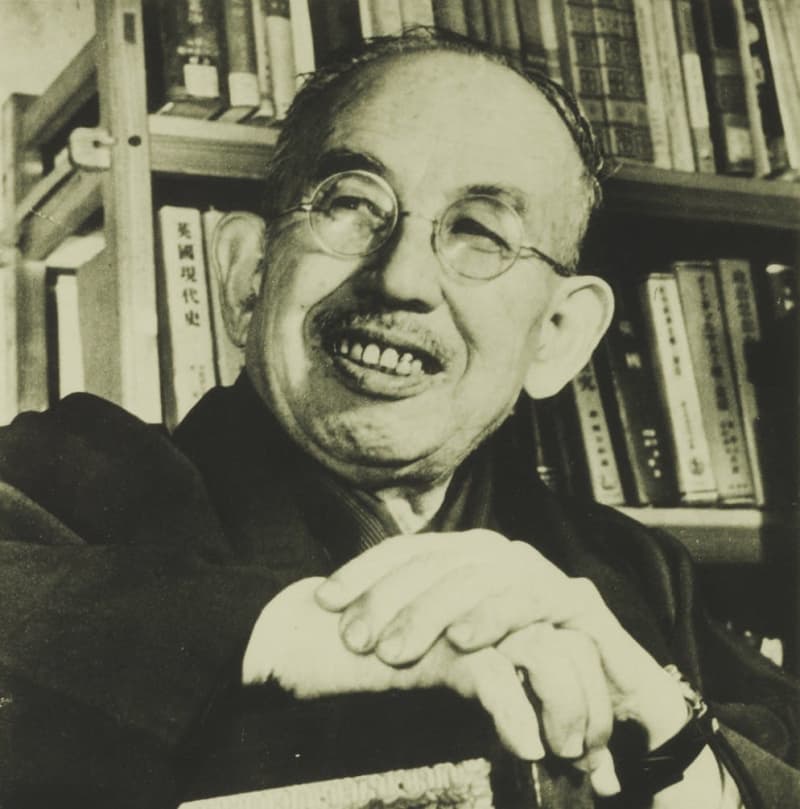
画像. 穂積重遠. public domain
結婚式は華族会館で行われ、媒酌人は男爵の穂積重遠氏が務めています。ちなみに穂積重遠氏は、『虎に翼』の寅子の恩師・穂高教授のモデルで渋沢栄一の孫です。
また華族の結婚では、公家、武家、勲功の気風の違いから、公家は公家との、武家は武家との結婚が望まれました。
徳川宗家第17代公爵・徳川家正の二女・敏子さんは、上杉謙信を祖にもつ上杉伯爵家の隆憲氏と結婚しています。隆憲氏は上杉家第16代目にあたり、大名華族同士の結婚でした。
お見合い後、結婚前提でのお付き合いを経て結婚に至った敏子さんは、自身の母親が結婚した明治時代とは異なり、運命に縛られることもなかったと語っています。
敏子さんの母・正子さんは、最後の薩摩藩主である島津忠義氏の九女。第13代将軍家定夫人・天璋院(篤姫)の命令で、生まれる前から結婚相手が決められていたそうです。
資金獲得のために娘を嫁がせる華族
幸せな結婚がある一方、華族のお嬢様の結婚は資金獲得の手段になることもありました。
経済力はないけれど伝統的な名声のある公家と、金はあるけれど名声がない資産家とのマッチングが進み、特に明治末から大正期にかけて、貧乏公家が露骨な金銭目的で娘を成金に嫁がせる事例が多く見られました。
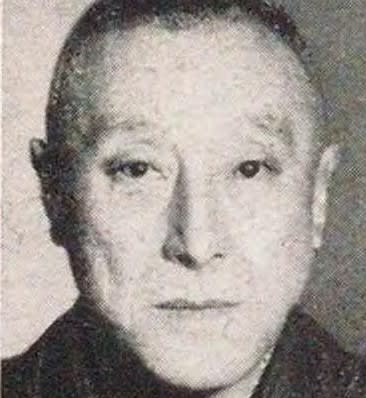
画像.久我常通. public domain
一例をあげると、事業の失敗から屋敷を差し押さえられた清華家の久我常道(こが つねみち)侯爵は、長女・三千子さんを北海道の多額納税者・五十嵐佐市氏と結婚させています。
当時「華族社会の生血を吸って太る高利貸し」と揶揄された五十嵐氏は70歳。三千子さんは39歳で、年の差31歳のこの結婚は、持参金目当てに娘を売り渡したのも同然といわれました。
華族の中には「せっぱつまって娘に売り物札をつける殿様」(山口愛川『横から見た華族物語』)がおり、こうした醜聞はマスコミの格好の餌食となりました。
さいごに
有馬男爵家の子息と結婚した涼子様は、どのような結婚生活を送っているのでしょうか。戦後、華族廃止という苦難を彼女がどう乗り切るのか、再登場に期待したいと思います。
参考文献
小田部雄次『華族家の女性たち』.小学館
華族資料研究会編『華族令嬢たちの大正・昭和』.吉川弘文館

