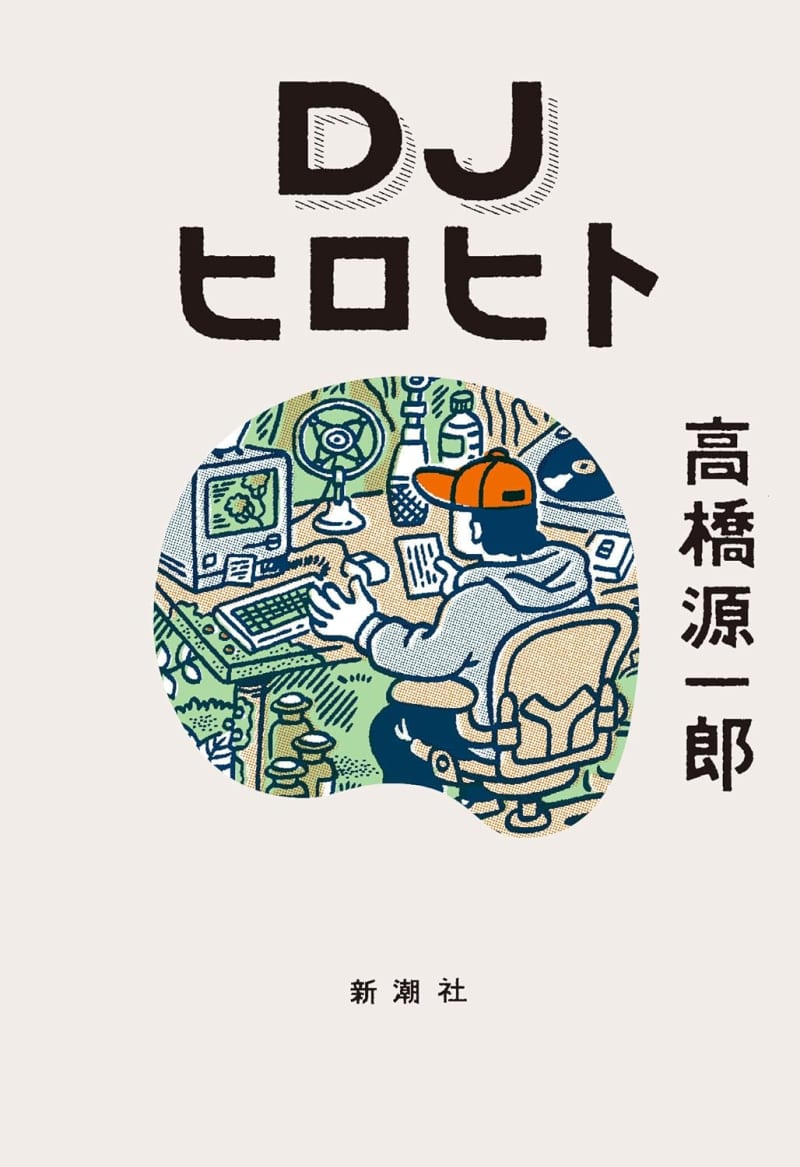
〈そして私が話す番になった。〉(高橋源一郎『虹の彼方に』1984年)
いまから123年前の1901年4月29日、日本に「裕仁」、いわゆる昭和天皇が誕生する。そのほんの数ヶ月前の1900年12月23日、カナダの技術者レジナルド・フェッセンデンの手により、世界初の音声の無線放送が成功し、いわゆる「ラジオ」の原型が誕生する。ほとんど同じ時代に、遠く隔たった場所で生まれたそれらは、半世紀近い年月が流れた1945年8月15日、ようやく公式に初めて「対面」を果たすことになる。その前日深夜に宮中で録音された裕仁の肉声がラジオを通じて放送され、ポツダム宣言の受諾、つまりは終戦が国民に広く知らされた、いわゆる「玉音放送」がそれである。
そうした裕仁とラジオの、現実とはまったくちがう、だけどあり得たかもしれない(?)「対面」を描こうとする前代未聞の試みこそが、高橋源一郎により6年ぶりに上梓された全648ページもの大長編擬似歴史小説『DJヒロヒト』である。ある深夜、裕仁、いや、「ヒロヒト」は、マイクに向かい、このように話し始める。
〈コンバンハ、ラジオノ前ノリスナーノミナサン、オ元気デスカ、日付ガ替り、新シイ日ガヤッテキタ、夜ハコワイ、デモ夜ハ素敵、ナゼナラ、夜ニハ、昼トハチガウモウヒトリノアナタガ目覚メルカラ、サア今夜モ続キヲ始メヨウ、長イ長イオ話ガマダマダ続クヨ、ボクガ見タコト、東ノ小サナ国デ起コッタタクサンノ出来事、確カニソウダッタ話、ソウダッタカモシレナイオ話ヲ、ボクノオ話ノ中ニハ、イロンナモノガ混ジッテル、コノ世ノスベテガソウデアルヨウニ、デモトットキノオ話バカリサ、ボクニデキルノハオ話ヲスルコトダケ、今夜ノ電離層ノ具合ハドウダロウ、モシカシタラオカシナ電波モ飛ビコンデ来ルカモシレナイ、ボクノ話が途切レテシマウカモシレナイ、ソレデモカマワナイ、ラジオハナニガ起コルカワカラナイ場所ナンダ、ダカラ、ボクノ話聞イトクレ……D……J……〉
いちおう言っておくと、この「終戦の詔書」さながらに漢字カタカナ混じりの言葉の主は、かの昭和天皇・裕仁では当然なく、高橋が想像を交えて作り出した、いわば「昼トハチガウモウヒトリノ」ヒロヒトである。その上でいま、冗長になるのを承知で、本書冒頭にエピグラフ的に置かれたこの一文を丸々引用したのは何を隠そう、この分厚い長編で起きようとしていることのほとんどすべてがここで明かされてしまっているからにほかならない。すなわち、深夜のラジオDJとなったヒロヒト(!)が「見タコト、東ノ小サナ国デ起コッタタクサンノ出来事、確カニソウダッタ話、ソウダッタカモシレナイオ話」のすべてを自由にミックスして、ときには「オカシナ電波モ飛ビコンデ来ル」のさえ歓迎しながら語り続けた、歴史のような、小説のような、「長イ長イオ話」。ただひとつ、本書はそういう構えのお話なのだ、というこの一点だけ踏まえておけば、本書の分厚さに過剰に怯える必要はないし、なんなら規則正しく前から順番に読む必要さえなく、気になった部分から読み始めてみるのでいいと思う。
とはいえ、いちおうの職務としてストーリーに触れておくと、その「長イ長イオ話」は「6・1と8・6」という副題を持つ「プロローグ」から始まる。そこでは、1929年6月1日、ヒロヒトと生物学者のクマグス(南方熊楠)の和歌山県・神島での邂逅、そして日本の原爆開発にも関与した科学者・仁科芳雄の1945年8月6日の回想が描かれたのち、以下全4章にわたり途方もないと言うほかないスケールで、ヒロヒトと「昭和」という時代を生きた、歴史上に名を残す数多の人々の姿が代わる代わる語られていく。
ところで、なぜか積極的には宣伝されていないものの、かつて高橋は、批評家・東浩紀と行なった対談「歴史は家である」(『ゲンロン10』2019年)で本作について、長編小説『日本文学盛衰史』(2001年)、そして『今夜はひとりぼっちかい? 日本文学盛衰史 戦後文学篇』(2018年)と彼が続けてきた一連のトライの、第3部に当たる作品なのだと語っていた。じつは(もちろん、本書単独でも読めるが)、本作はある種の続編なのだ。そこで高橋は、これらの作品群に通底する「歴史感覚」の回復という問題意識に触れながら、前2作では「明治」、「戦後」がそれぞれテーマであったのに対し、今作では「昭和(天皇)」、つまりは裕仁が作品の軸になるのだ、と明かしていた(ちなみに、本書の連載中のタイトルは、ただ「ヒロヒト」だけだった)。
けれども、失われた「歴史感覚」を前にして「小説」家に、何ができるのか。そう煩悶しながら書き連ねられたのが、この『DJヒロヒト』という作品である。最も「公」的とさえ言える「天皇」という存在を語り部としながら、むしろその「私」的でパーソナルな声を想像し、それに耳を傾けることで、こともあろうか読者の共感までも誘ってしまう。本書がやっているのはそのようなアクロバティックな芸当なのである。たしかにそれは、これまで何度も(ときに失敗しながら、それでも)ある種の「タブー」を描き続けた高橋が「令和」の現在に挑むのに申し分ない題材であるかもしれない。
だが念のために確認しておけば、そのときに語られるのは(高橋源一郎の「小説」なのだから当たり前だが)、間違っても「正しい昭和史」などではない。高橋にとって「歴史」とはむしろ、次のようなものだからだ。
〈わたしは、この本の中で、「過去」の小説を、その「評判」から取り戻そうと思いました。陳列されているガラスの棚から脱走するよう、説得してみることにしました。要するに、「過去」で眠っているのを止め、起きて、現在に遊びに来るようにいったのです。/そして、「現在」の小説には、その逆に、「過去」に行って、「過去」の小説と遊んでくるよう命じたのでした。/「歴史」というものは、鑑賞するために壁にかけられた絵ではありません。なんというか、それを使って、誰も考えたことのないヘンテコなものを作り出せるオモチャみたいなものではないでしょうか。いや、そうであるべきなのです。〉(高橋源一郎『大人にはわからない日本文学史』2009年)
高橋にとり「歴史」とは「評判」に従い「大人」しく鑑賞される「陳列」物ではなく、触って「遊び」ながら、「誰も考えたことのないヘンテコなものを作り出せるオモチャ」のようなものだ。だからたとえば、「過去」の文学史上の登場人物たち(夏目漱石、石川啄木、田山花袋……)と、90年代当時=「現在」の流行(たまごっち、伝言ダイヤル、アダルトビデオ……)を「評判」度外視で互いに遊ばせ、「過去」と「現在」への批評を同時にやってのけた『日本文学盛衰史』、そしてその「戦後文学」版たる『今夜はひとりぼっちかい?』などは、まさにそうした高橋の「歴史感覚」に基づく実践であると言える。へんに距離を取ってしまうくらいなら、まずは一度直接に歴史と遊んでみること。そうして「楽しく」戯れているうちに、気づけば「歴史感覚」のようなものが身に付いている。高橋が掲げるのはそのような「理想」である。
そうした理念から、単行本化に際してタイトルに付け加えられた「DJ」という設定についてもある程度説明できるのではないだろうか。巻末で高橋が明言するとおり、本書が参照する膨大な資料は、大小の改変が加えられている場合もあれば、資料に擬態した虚構、あるいは逆に嘘のような事実を伝える資料である場合もある。あらゆる資料は高橋によりバラバラにされ、そして再度繋ぎ合わされ、まるで「DJがレコード音源を自由にリミックスするように」使用されている。デビュー以来、カルチャーの硬軟を問わず、さまざまな「断片」を自らの小説に散りばめてきた高橋の本領発揮と言わんばかりに、本書『DJヒロヒト』では、「大日本帝国憲法」や「教育勅語」から、本多猪四郎/中村真一郎・福永武彦・堀田善衛『モスラ』(1961年)や宮崎駿『風の谷のナウシカ』(1984年)まで、多様な「昭和」の「言葉」が参照され、解体され、再び接合されることで「現在」の響きで再生されるのである。それこそがなにより、「正しさ」より「楽しさ」を優先する、という本書の姿勢の現れではないだろうか。かつて高橋はこう書いた。
〈なぜ、断片でなければならないのか。二十世紀の「小説の中興の祖」ガルシア・マルケスの代表的作品は、よく読むと、むすうの断片によって成り立っている。かれの作品は、現代文学ではなく民衆の古い記憶や伝承の上に物語を構築していったとされるが、厳密にいうならそれは過ちである。たとえば、マルケスの読者は音楽を聞くようにかれの作品を読むが、それは古いメロディーが再現されているからではない。マルケスは、現在の読者の耳がすでに過去の音楽を楽しめないことを熟知している。だから、かれは音楽を一度、ひとつひとつの音にまで分解してから再構成する。そしてその音はサンプリングマシンによって人工的に作られた音である。〉(高橋源一郎「「文」の運命」『文学じゃないかもしれない症候群』1992年)
ここで高橋はマルケスの文学を引き合いに出しながら、「現在の読者の耳」ではストレートに「楽しめな」くなった「過去の音楽」を「断片」、つまりは「ひとつひとつの音にまで分解してから再構成」された音、「サンプリングマシン」により「人工的に作られた音」を肯定する。それはまさにこの小説の方法そのものであるだろう。
むろん、それは「大人」が「歴史」にとるべき態度として、いささか楽観的過ぎる、という非難は至極もっともである。歴史意識の欠落した時代、あるいは「間違った歴史」の氾濫した時代にあって、「正しい歴史」より「楽しい歴史」を優先するのは、軽薄で「子ども」じみている。かりにそのような批判があるとして、それもまた正鵠を射たものであるだろう。だが、こう思うのだ。この『DJヒロヒト』という「小説」から学ぶべきは、たぶん「正しい歴史」との付き合い方ではない。本書がわれわれに教示しようとしているのは、むしろ「間違った歴史」との接し方なのではないか。「歴史家」ではない「小説家」という存在が、それでも「歴史意識」について考えるとしたら、おそらくはそうした方向性においてであるだろう。少なくとも本書は、そうしたベクトルから「歴史」に肉薄しているように思う。本書中に出てくる戦後文学作品のタイトルを借りて言えば、それが「歴史」という友人に対し、「小説家」という『悪い仲間』がただひとつ担い得る役割なのだ、とでも言うように。
(文=竹永知弘)
