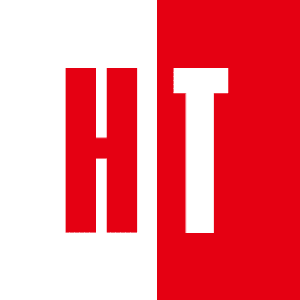AIが徐々に住宅業界のビジネスモデルにも浸透しつつある。果たしてAIは、住宅業界に何をもたそうとしているのだろうか―。AIを用いた概算見積システムを構築したウッドステーションの塩地博文会長と、千葉県で住宅事業を行う住工房スタイルの野口浩社長に話を聞いた。
―ウッドステーションでは、AIを用いた概算見積システムを開発したそうですが。
塩地 PDFの図面をアップロードするだけで、拾い出しと概算見積の作成をAIが自動で行うものです。一般的なDXツールとは異なり、ソフトなどを販売するのではなく、Web上でデータをアップすれば、パソコンの性能などに関係なく、瞬時に拾い出しと概算見積までを行います。
PDFになった図面データには、目には見えませんが様々な情報が書き込まれています。我々が開発したシステムを簡単に説明すると、こうした情報をもとにして、AIが平面図から3Dデータを生成し、そこから構造材の拾い出し作業を行おうというものです。
構造材の拾い出しから先行して開始しましたが、既に断熱材の拾い出しについても可能になりました。今後はサイディングや開口部などにまで広げていく方針です。そのうち、釘の本数まで拾い出すことも可能になりますよ。
正直に言うと、まだまだAIの学習が不足している部分もありますが、試行的に多くの工務店や設計者の方々に使ってもらいながら、その有用性の確認とAIの学習を進めているところです。
住工房スタイルさんが手掛けた住宅についても、既にデータを入力しており、概算見積額についても実際のものとそれほど差がないことを確認しています。
野口 そもそも拾い出し作業というのは、工務店や設計者でも正確にできる人は限られています。また、設計変更などが生じると、その都度、見積も出し直すことになるので、何度も拾い出し作業を行うことになります。その部分がAIで自動化できるようになると、業務負荷は格段に減りそうですね。

―概算見積ができるのは、ウッドステーションさんの大型パネルだけですか。
塩地 本当はそうしたいのですが(笑)、ユーザーの方々の利便性を考え、在来工法も概算見積を出せるようにしました。図面のPDFデータをアップロードし、仕様情報入力フォームというページで、柱・梁などの基準サイズ、土台・大引き、梁桁、柱、羽柄材などの樹種を選択していく形になっています。
できるだけ入力作業などを省力するために、プルダウン形式で選択できるようにしています。将来的な構想としては、「国産材ナビ」のような機能を追加し、建設地から最も近い場所で調達できる国産材を用いた場合の概算見積も出せるようにしていきたいと考えています。
野口 概算見積の根拠となる木材の価格は、市場変動に伴って変わっていくのでしょうか。
塩地 ある木材関係の会社に協力を仰ぎながら、木材の実勢価格を定期的に更新していく仕組みになっています。だからこそ、概算見積としてはかなり高い精度のものを提供できます。
野口 これまでもCADソフトと連携して拾い出しと概算見積を行うツールを使ったことがあるのですが、単価などを自分であらかじめ入力する必要がありました。そのため、木材の価格が大きく変わってしまうと、イチから自分でデータを入力し直す必要がありました。なかなか効率化にはつながらないなという印象がありました。それだけに、木材価格が自動で更新されるというのは魅力的ですね。
塩地 CADと連携したツールだと、結局はCADソフトに縛られてしまうという問題もありますよね。我々のシステムは、どのようなCADソフトで作成した図面であってもPDFデータさえあれば問題なく使えます。

受発注機能を備えてツールとの連携も
―野口さんにお聞きしたいのですが、実際に拾い出しから概算見積という作業は、どのくらい業務を圧迫しているのでしょうか。
野口 当社の場合、概算見積であれば1~2時間で拾い出す作業を行います。ただ、あくまでも概算なので、高い精度で拾い出しているわけではありません。プランが確定していく段階で、より正確な拾い出しを行い、金額を確定していくという作業を行っています。当社の場合、40社程の取引き会社に見積を依頼し、それらを集約してお客さまに提出する見積を作成していくので、多くの時間と労力が必要になることは間違いないですね。
概算見積もプランが変更になると、再度、拾い出すが必要になることもあります。当然ながら、何度も概算見積を出したにも関わらず、受注できないケースもあります。
塩地 我々のシステムは、定額の料金で何度も使用できるようにしたいと考えています。そのため、プラン変更の度にPDFデータをアップロードするだけで概算見積が作成できるというわけです。
これによって、拾い出しから概算見積を制作するまでの作業を大幅に削減できるわけですが、我々のシステムはもうひとつ大きな役割を果たします。それは、見積のロジックを共通化できるということです。
何度も見積を作成していると、途中でロジックが変わることがあります。例えば、初めの段階で漠然とした坪単価で概算見積を出してしまうと、いよいよ詳細の見積を行おうという段階で、プラン変更などの影響で当初の坪単価では利益が確保できないという状況が発生してしまう。
我々のシステムは、何度も使うことができるのでロジックが変わることはありません。また、木材の単価なども実勢価格を参考にしているので、漠然とした坪単価よりは正確に概算の見積額を把握できます。
―予実管理の機能も果たすわけですね。
野口 できれば概算見積だけでなく、発注までのロジックが統一できるといいでね。木材については、柱や梁のプレカット材については、一括で発注できますが、羽柄材などについては着工してからも追加注文などが発生してしまいます。
現場、建物規模、さらに言えば施工者によっても使用する材量が変わってしまうので、施工中に現場監督や大工の判断で追加発注するということが多々あるのです。材木屋さんもそのことが分かっていうので、一括して発注するのではなく、その都度発注して欲しいようです。
そうなると配送料なども増えてきますし、なにより予実管理が難しくなります。
塩地 我々のシステムで作成した概算見積のデータを活用して、例えば電子受発注機能があるツールと連携させることで、発注まできるようにすることは可能だと思います。
結局、色々な局面でロジックが統一されていないから、最終的には工務店さんの利益が圧縮されていくという状況が発生しているのではないでしょうか。もしも、AIがはじき出した価格で発注を行い、受注する側はその価格で責任を持って資材を供給していくという世界が実現できれば、こうした状況はなくなるのでしょう。
ある意味ではAIが裁判官になるようなイメージですね。
野口 工務店側からAIが算出した価格を提示して、その価格で受注できるサプライヤーとマッチングしていくということも可能になる可能性がありますね。
塩地 チーム「住工房スタイル」のようなグループを概算見積システム上で構築して、サプライヤーや協力業者の方々と情報を共有していくことができれば、もっと効率的になるはずです。
さらに言えば、工程管理などを行うツールと連動していけば、施工費なども含めた見積額を把握できるようになると思います。そうなると大型パネルの有用性も分かりやすくなるでしょう。
野口 ハーフ住宅との相性も良さそうですね。内装の見積までを行おうとすると、さすがに難しい部分があるでしょうから。
塩地 そうですね。さすがにタオル掛け1本まで含めてAIが拾い出しを行うというのは現実的ではないかもしれません。
その点、ハーフ住宅は大型パネルを用いて、内装を仕上げる前の状態で引き渡してしまおうというものです。内装は施主が住みながらゆっくりとDIYで仕上げていくことができます。もちろん内装の仕上げまで含めてプロに依頼してもいい。
このハーフ住宅であれば、内装の細かな部材の拾い出し不要ですから、AIでカバーできる範囲は広くなります。

―AIを活用した拾い出しと概算見積の作成によって業務負荷を大幅に減らすことができるだけでなく、見積を作成するロジックを共通化することで予実管理を行いやすくなることがよく分かりました。本日はありがとうございました。