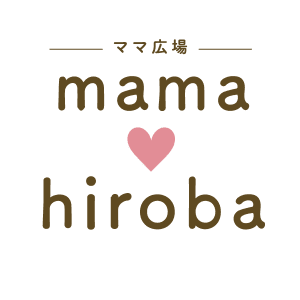子どもの友人関係がうまくいかないと悩むママさんが増えています。悩むお子さんによりそってあげるにはどうしたらいい?そんな悩みについて、メディアでもご活躍中の臨床心理士である大阪カウンセリングセンターBellflower代表、町田 奈穂さんにお伺いしました。
そんな悩みが増えている?
「〇〇ちゃんが急に話してくれなくなった」「ほとんど話したことはなかったのに、最近急に親友認定されて驚いている」といったお子さんのお悩みや、「先生や相手の親御さんに聞いても、うちの子が原因ではない、と言われた」「うちの子は小さい頃から好き嫌いが激しくて、一度嫌いになったら絶対に受け入れられないからごめんね~、と言われた」など、お相手きっかけの友人関係の悪化にどうしたら良いか悩む親御さんの相談は増えています。いじめでもないし、先生から注意を受けているわけでもない。でも、子どもは悩んでいて、なんとか声をかけてあげたくてモヤモヤしてしまいますよね。
友人の好き嫌いが激しい子の特徴で考えられること
・過敏に反応しやすい ・強いストレスによって精神的に不安定になっている ・人間関係の築き方や距離感の測り方が苦手 ・依存傾向が高い
その子の性格だけではなく、周囲の環境の影響を強く受けた結果、好き嫌いの激しい特徴が見られることがほとんどですので、お子さんひとりで解決や対処をすることは難しいです。
意図しなかった形で言葉が受け取られてしまうことでさらなるトラブルに発展する危険性が高いです。

対処法
(1)距離を取る
あらかじめ距離を取っておいて、深い友人関係にならないようにすることが考えられます。もちろん、子どもは良いも悪いもさまざまな人間関係の中で多様な経験を重ねることが大切です。しかし、好き嫌いの激しすぎる子との関係は、日々の生活の安全が脅かされるリスクがあります。多様な経験をするためには日々の生活基盤が整っていることが大切です。長い目で見て、一定の距離をおく選択も時には必要です。
(2)話をするときには最低3人で話をするように設定する
意図しなかった形で言葉が受け取られてしまいトラブルに発展することが多く聞かれます。お子さんが「そんなつもりじゃなかったのに・・・」といくら説明しようとしても、受け入れてもらうことはなかなか難しいという場合もあります。その結果、お子さんが傷つき、人間関係に不信感を持ってしまったり、自信をなくすきっかけにもなってしまいます。
このような状況に陥ったときに大切なことは、事実確認することです。1対1で話をしているとどちらが本当のことを言っているのかわからず、味方をしきれない親のジレンマもあるかもしれません。
ですので、そのような時こそ最低でも3人で話すことで複数の視点からの状況確認ができ、大人も状況の把握がしやすくなります。
大切なこと
・必ずしも皆と仲良くする必要はないということを学ぶきっかけとする
小学校に入学を機に「友達100人つくる」や「みんなと仲良く」と教えられることがほとんどです。
しかし、実際は私たち個人にも好き嫌いや、相性もあります。自分自身の好みや相性の良い人、悪い人を知るきっかけとなったりするということや、無理に人と付き合い続けなくてもいいということを伝えてあげてください。
・距離の取り方を学ぶ
特にすぐに親友認定しようとしてくるお友達の特徴として、距離が近すぎる場合がよく見られます。そのような場合には、無理に我慢する必要はなく、「嫌なときには嫌と言ってもいいよ」と教えてあげることで、自分の思いを伝える練習のきっかけにもなります。
・急な友人関係断絶があったとしても親は味方であることを伝え続ける
辛いお話のひとつが、意図していなかったのに急に関係を切られてしまって言い訳もできずショックを受けている、というお話です。問題が相手の特性により生じている場合は、「伝え方が特に難しい子もいるんだよ。今回は残念な結果になってしまったね。でも、お母さん(お父さん)は〇〇くん(〇〇ちゃん)と話をしていてとっても楽しいよ。いつでも味方だからね」と寄り添い、安心を与えてあげることが大切です。
執筆者

町田奈穂
臨床心理士・公認心理師
経歴
同志社大学大学院 心理学研究科修了。
在学時より滋賀医科大学附属病院にて睡眠障害や発達障害に苦しむ人々への支援や研究活動を行う。
修了後はスクールカウンセラーやクリニックの臨床心理士を経験。
2020年、父の病気を機に父が経営する機械工具の卸売商社へ入社。
そこで多くの企業のメンタルヘルス問題に直面し、大阪カウンセリングセンターBellflower(大阪府寝屋川市) を設立。
現在は、父の後を継ぎ機械工具の卸売商社の代表を務めるほか、公認心理師・臨床心理士として大阪カウンセリングセンターBellflowerを新規事業とし、支援者支援をテーマとした研究や臨床活動を行っている。
大阪カウンセリングセンターBellflower
https://counseling-bellflower.com/