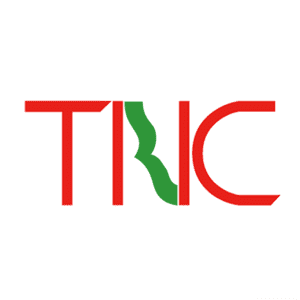電子書籍やネット通販が普及するのに伴い、各地で街の書店が次々と姿を消しています。
こうした中、50年以上ほとんど姿を変えず、地域の人に愛される「町の本屋さん」や、福岡市にオープンしたユニークな書店を取材しました。
話を聞いたのは、福岡市中央区にある「金修堂書店」のオーナー・安永寛さんです。
◆金修堂書店 安永寛さん
「そこの信号渡って左、ビルがあるでしょう。その1階に本屋さんがあった。それと、この六本松の交差点のところにも1つ。それから近くのスーパーに1つ。今ね、3つなくなった。この辺だけで。競争相手がいなくなっても万歳じゃない。競争相手がいるから強くなる」
1966年に開店した店舗は50年以上ほとんど姿を変えず、地域の人に愛される「町の本屋さん」。
この店もまた、来店客の減少に悩まされていました。
◆金修堂書店 安永寛さん
「来店客数が減った。極端に減った。売り上げが3分の1くらい。半分じゃないよ、3分の1」
町の書店が次々と姿を消している理由ー
それは、スマホひとつで手軽に読むことができる電子書籍や、注文した本が次の日には手元に届くネット通販の普及です。
全国市区町村のうち、書店が1店舗もない自治体は今年3月末で482市町村。
福岡県でも60市町村のうち19の自治体で「書店ゼロ」、「1店舗のみ」という自治体も11あります。
この店では、裁判所が近いという地理的な特徴を活かして、裁判官や弁護士のための実務書などを充実させ、固定客を掴むことで、営業を続けられているといいます。
◆金修堂書店 安永寛さん
「どの本屋を見ても、同じものが並んでいるという言われ方をする。やっぱり特徴をつけないかんね、個性をつけないかん、それを各店舗が変えないかんと思う」
書店にも「個性と特徴」が必要な時代に。
こうした中、今年4月、福岡市博多区にユニークな書店がオープンしました。
天井高く積み上げられた本の山に、ディスプレイとして置かれているのは、レトロなラジカセ。
昭和の雑貨店に来たかのような雰囲気の中、出迎えてくれたのは、店主の山田孝之さんです。
山田さんは、実は、ユーモアを交えた浮世絵風のイラストで「あるある」ネタを発信し、インスタグラムのフォロワーが100万人を超える人気イラストレーターなんです。
時代の最先端で活躍するインフルエンサーがなぜ、今の時代に書店を開いたのか?
◆ふるほん住吉・店主 山田孝之さん
「AIがすごく進化ていまして、イラストの仕事がもう誰でも簡単にできる。結構、危機感は感じている。実際の空間を作るというのは、今のAIには難しいと思いますので、本屋さんっていう空間に行って、空間を楽しむとか表紙を楽しむとかそういう需要はあるので、今後もそういう感じの流れは来ると思う」
「いるだけでワクワクする」そんな書店を目指し、まず、ディスプレイに力を。
店内には、手に入りにくい絶版の書籍のほか、昭和20年代に発刊された雑誌など1万5000冊以上を揃えています。
さらにー
◆ふるほん住吉・店主 山田孝之さん
「古いハガキとか、こういうものも置いてます。お土産として売られているような絵葉書のセットで見てみると、小倉城の横にジェットコースターがあった時代のハガキですね。『懐かしい』って見られる方もいらっしゃいますし、僕のようにこの世代を知らない世代は発見があったり、いろんな楽しみ方があったりします」
そんな発見を求めて店を訪れる人も増えています。
◆来店客
「仕事が終わったら、ここに来るようにしている。見て良いのがあったら買おうかなって」
◆来店客
「ディスプレイとか可愛くて、駄菓子屋さんに来たみたい」
◆来店客
「昔、子供のころ読んだ本とかあって、すごく懐かしい、嬉しかったです。また読んでみようかな」
「町の本屋さん」が次々と消える中、求められる新たなカタチとはー
◆ふるほん住吉・店主 山田孝之さん
「ネットとかAIでは見つけられない、楽しめないものを提供できる場所になれば、情報をただ得るだけじゃなくて、こういう空間を楽しんだり、今風に言うと、エモい感覚みたいなものを味わえるような場所とか、そういったものが求められているのかなと思います」