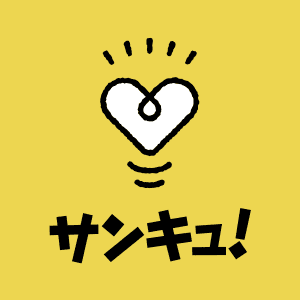「気象庁は今日、関東甲信地方が梅雨に入ったとみられると発表しました」…そんな報道を聞くような季節になりました。毎年、風物詩のようにニュースや天気予報で聞く梅雨入りのお知らせですが、そういえばどうやって決めているのでしょうか。
また、梅雨に入っても意外と晴れている日が多いような年もありますが、「梅雨って言ったのになんで今日晴れてるの?」と子どもに聞かれたら、答えられるでしょうか??
今回は、気象予報士・防災士・野菜ソムリエとして活躍する植松愛実さんに、身近だけど意外と知らない「梅雨入り」について教えてもらいます。
曇りや雨が続きそうなら「梅雨入り」

気象庁で予報を担当する人には、今日明日の天気といった直近の予報をする人と、週間予報のように少し長いスパンの予報を考える人がいます。「梅雨入り」を発表するかどうかを決めるのは後者、週間予報を担当する予報官で、このさき曇りや雨の日が続きそうだなと思ったら発表を決断します。
曇りや雨の原因は、なんでもOKです。つまり、梅雨前線の影響でも、低気圧でも、台風でも、とにかく曇りや雨が続きそうなら梅雨入りを発表します。
「え?梅雨前線じゃなくてもいいの?」と思った人もいるかもしれませんね。これには、梅雨入りを発表する「理由」が大きく関わっています。
影響範囲が大きい「雨の季節」

日本では毎年6~7月にかけて曇りや雨の多い日が続き、農業や小売業、流通業など、幅広い業種に影響を与えます。また、とくに梅雨末期となる7月前半には毎年のように災害を引き起こすような豪雨が発生しています。
このように梅雨の時期に降る雨は、ほかの季節の雨と比べて、一般の人にとっての影響が格段に大きいのです。
そのため気象庁では、「今年もそろそろ気をつけないといけない時期になりましたよ」という注意喚起のために「梅雨入り」を発表します。目的が注意喚起なので、梅雨前線のような科学的な要素はさておき、とにかく影響が大きくなりそうなら発表する、というスタンスなのです。
梅雨入りしても雨が降らないことがある?

じつは、「梅雨入り」の発表があったあとでも、晴れの日がけっこう続くことがあります。というのも、もともと気象庁の考えている「梅雨入り」自体が、“移り変わり”の期間だとされているのです。
どういうことかというと、「梅雨入り」を発表した日からとつぜん雨の季節に入るわけではなく、雨がそんなに降らない季節から降りやすい季節へとだんだん移り変わっていく移行期間が「梅雨入り」の発表日を含む前後5日程度、とされているわけです。
そのため、「梅雨入り」を境に一気に毎日雨ばっかりになるのではなく、少しずつ少しずつ雨が降りやすい状態に移っていくのです。
「梅雨入り」が発表されたらどうする?

梅雨が始まると、湿度がなかなか下がらない日が続き、家のなかもカビやダニが発生しやすくなってしまいます。そのため、クローゼットの整理や水回りの掃除は、いつも以上しっかりしてやっていきましょう。
梅雨時期の後半にかけては毎年災害が起きやすくなるため、今のうちに家のなかの防災グッズがちゃんと使えるか確認したり、非常食の賞味期限が切れていないか見たりすることも必要です。
また、意外と忘れがちなのが、エアコンの試運転。一番低い設定温度で10分くらい動かしてみて、変な音がしないか、異常を示すランプがついていないか、確認しましょう。
というのも梅雨は例年、だいたい1カ月~1カ月半で終わって、梅雨明け後は一気に強烈な暑さに見舞われることが多いです。暑くなってからエアコンの不具合がわかっても修理の業者の予約は取りづらくなりますから、今のうちにやっておきましょう。
■執筆/植松愛実さん
気象予報士と出張料理人の両面で活動中。気象・防災に関するヒントのほか、野菜ソムリエ・食育インストラクターとしておいしい食材のおいしい食べ方を発信中。インスタグラムは@megumi_kitchen_and_atelier。
編集/サンキュ!編集部