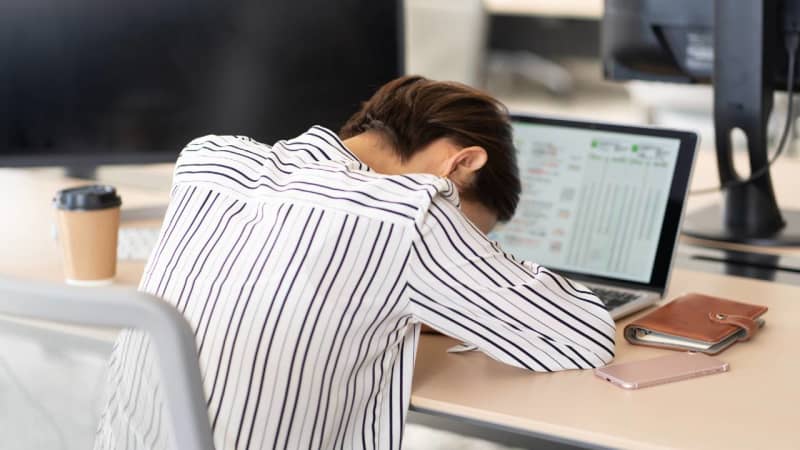
起業と聞くと「特別なスキルや才能、資産がなければ成功しない」と考える人は少なくありません。しかし、日本では1日におよそ400社近くの法人が設立されています(東京商工リサーチ:2022年「全国新設法人動向」調査より)。そこで、普通の会社員が“あるきっかけ”から起業を決意し、成功させた事例について、経営コンサルタントの鈴木健二郎氏が解説します。
「アイデアがある人」ほど抱えるフラストレーション
愛子さん(仮名)は、都内の中堅企業の人事マネージャーとして、採用、研修、人材育成など多岐にわたる領域で実績を上げてきた45歳のビジネスパーソンだ。月収は手取り30万円ほどと決して高いものではなかったが、自身の専門知識と経験を活かせるポジションに不満はなかった。
ある日、愛子さんは「社員のエンゲージメント強化のための施策」を上層部に任された。最近、優秀な人材の退職が続いており、以前から改革の必要性を感じていた彼女は、さっそく従業員の能力開発とモチベーション向上のために、メンターシップとキャリア開発を組み合わせた新しいプログラムを考案。このプログラムは、若手社員が経験豊富な上級社員から直接学び、個々のキャリアパスに沿ってスキルと知識を習得できるよう、入念に設計されていた。
しかし、彼女の提案は最終的に上層部から却下されてしまう。理由は、短期的なコストと実施の複雑さによるとのことであったが、それだけではどうも判然としない。何度か対話を重ねるうちに、上層部は、エンゲージメントの課題を感じながらも、コストと手間をかけてまで、現行のやりかたを根本から変えるようなアプローチは望んでいなかったようだった。
この決定に深く失望した愛子さんは、これでは自らのビジョンと能力が十分に生かされないと感じてしまった。世代や役職のギャップを超えて、社員同士がもっと柔軟に、協業で成果を出せるような環境に変えなければ、いま会社が抱えている課題が本質的に解決されることはないと思っていたのである。
愛子さんはすでに40代後半に差し掛かり、新卒から勤め上げた会社に骨をうずめるつもりだった。しかし、上層部の保守的な姿勢に深く失望した愛子さんは、ふと「このままでいいのだろうか」と感じるようになった。
現状に不満はなく、会社にも感謝している。しかし、会社に決められた枠から解放された世界で、自分の力を試したいという熱い思いは日に日に増していき、最終的には「独立して自身で企業のHR(人材管理)をサポートするコンサルティング事業をはじめる」という決意を固めた。
なんで上手くいかないの!? 愛子さんを待ち受けていた試練
どんなに素晴らしいアイデアがあるからといって、昨日まで企業の人事部のマネージャーだった愛子さんが新しいビジネスを立ち上げても、そう順調にことが進むものではない。特に、顧客の獲得には大きな困難が伴った。
HR業界は、すでに確立された大手コンサルティングファームが市場を支配している。そのため、一個人としての愛子さんが短期間で収益を獲得できるものではない。彼女は「HR関連の専門知識と経験」という強力な無形資産をもっているが、ビジネスを展開するうえで求められる「信頼」という名の無形資産を新たに築く必要があったのだ。
最初は知り合いのつてから初期のクライアント開拓を進めたが、自身の価値を理解してもらうことは難しく、ほとんどの提案が拒否されてしまった。
そこで愛子さんは、自分の専門性を生かし、一個人だからこそ価値が出せるサービスを模索し始めた。
まず、HRコンサルティング市場における既存のサービスと市場とのギャップを把握するため、広範なリサーチを行った。その結果、独自性のある提案だと思っていた自分のモデルが大手ファームも類似した提案をしていること、しかも、すでにその種のサービスは大規模に標準化されており、特に大企業向けに設計されていることが多いことに気づいた。
対照的に、中小企業はもっと具体的でパーソナライズされたアプローチを必要としていたが、これを提供できるサービスは限られていることが分かった。
この調査結果に基づき、愛子さんは自身のビジネスモデルを中小企業に特化。カスタマイズ可能なHRサービスへとシフトすることにした。
彼女は個別性の高い課題に対応するため、戦略的人材育成プログラムと組織改善に焦点を当て、中小企業向けに「オンデマンドHRコンサルティング」というコンセプトを開発。これにより、顧客は特定のニーズに応じて柔軟にサービスを選択し、利用することができるようになった。
感触をつかむため、愛子さんは無料セミナーやワークショップを積極的に開催。その場で具体的なアドバイスを提供することで、やがて参加した中小企業経営者からの信頼を少しずつではあるが勝ち取れるようになってきた。
さらに戦略を実証するため、愛子さんはワークショップに参加した数社の中小企業とパイロットプロジェクトを実施。彼女のアプローチが実際に顧客の問題解決に役立つことを示すことができた。参加企業の一部が本格的なコンサルティング契約を結ぶようになり、徐々に顧客基盤が拡大していった。
口コミと業界内のネットワーキングを通じて、さらに新たな顧客を獲得し、いつしか彼女のパーソナライズされた人材育成プログラムは“愛子メソッド”と呼ばれるようになった。気がつくと彼女の年収は会社員時代の3倍超に。月収100万円を超えていたのである。
愛子さんの起業“成功のカギ”は
本事例が教えてくれるのは、自分の持つ専門知識や経験といった「無形資産」を市場価値に変換する方法の重要性である。無形資産は目に見えないため、その価値を認識しにくいかもしれない。しかし効果的に活用できれば、ビジネスの競争力を大きく向上させることができる。
愛子さんは会社員時代の経験を活かすだけでなく、中小企業向けのカスタマイズ可能なサービスを提供することで、市場における自分なりの「ニッチ」を見つけ出した。彼女の成功のカギは、市場のニーズと自己の能力を精密に分析し、その2つが接合するように戦略を練ったところにある。
愛子さんは特に、大手コンサルファームでは満たされない中小企業特有のニーズに注目し、その解決策を提供することで顧客からの信頼と市場での地位を確立した。彼女のアプローチは、柔軟な思考がいかにして既存のビジネスモデルを超え、新たな価値を生み出すかを示す好例といえる。
このケースは、個人が自らの専門知識を活かして市場に新しい風を吹き込む方法を教えており、多くの起業家やビジネスリーダーにとって大きなヒントとなるだろう。
鈴木 健二郎
株式会社テックコンシリエ
代表取締役
