
サブカルの街として全国的にその名を知られる、東京・下北沢。近年は再開発によって雑多な印象からスマートな街へと様変わりしているこの地で、ミツバチを飼育する養蜂が行われていることはご存じでしたか?ミツバチたちがさまざまな場所から集めたハチミツは「シモキタハニー」と名付けられ、シモキタの新たな名産品としても注目されています。
市街地の建物の屋上でミツバチを飼う都市養蜂。ミツバチが蜜を集める過程で花粉を媒介し街の緑化も推進されるというメリットもある養蜂は、2006年に東京・銀座でスタートした「銀座ミツバチプロジェクト」をはじめ全国にも広がっています。また、高いところから蜜源へ一直線に飛んでいくというミツバチの習性もあり、人口密集地でも安全性を保ちながら行うことができるのです。
そんな都市養蜂は、渋谷や新宿からもほど近い東京都世田谷区の下北沢、通称「シモキタ」でも行われています。サブカルの聖地としても知られ、雑多さが醸し出す独特のカルチャーが多くの人たちを惹きつけてた街ですが、近年は地下化した小田急線の線路跡地をはじめとする再開発が進み、街の雰囲気も一変しています。
街の再開発を機に、シモキタを舞台にスタートした「養蜂」。ミツバチたちを飼育することで、天然非加熱ハチミツの「シモキタハニー」も生まれました。この事業を立ち上げたのは、ハニージェイプロジェクト株式会社代表の杉山直子さん。自身が生まれ育ったのも、この下北沢の街だといいます。

「今も昔もですが、コンパクトな街なのでどこにでも歩いて行けるんです。それでいて開放的な雰囲気で、普段着で歩いていても恥ずかしくない気楽さがありますね。大好きな自慢の街です」
虫嫌いが出会ったミツバチ
杉山さんが、地元の下北沢で養蜂をスタートさせたのは2021年の冬。フリーランスで請け負う翻訳業の傍らに行っていた出張料理の仕事の際、ロックバンドThinking Dogsのギタリスト、JUNさんと出会ったことがきっかけです。
杉山さんがミュージックビデオの撮影現場で知り合ったというJUNさんは、静岡県の出身。地元では、日本在来種のミツバチであるニホンミツバチを飼育していた経験があったといいます。今でも初めてハチミツを採取して食べたときの感動が忘れられず、「またいつか養蜂をしたい」と考えていたときに出会ったのが杉山さんでした。
「JUNさんと何回か会って話をするうちに、『どこかでニホンミツバチの養蜂ができないか』と相談されたんです。話を聞いているうちに私も養蜂に興味を持って、ひとまず親族の家がある鎌倉の山間部に巣箱を置いてみることにしました」

こうして採れたニホンミツバチのハチミツの美味しさに感動したという杉山さん。しかし、集める蜜量はセイヨウミツバチの約10分の1ほどと言われているニホンミツバチ。少量のため販売につなげることも難しく、巣箱の維持費がかさむばかりだったといいます。
未経験から始めたニホンミツバチの養蜂を経て、杉山さんとJUNさんは思いきって知人の養蜂家に弟子入りすることを決意します。家畜として長い歴史があるセイヨウミツバチの飼育について学び、養蜂をビジネスとしても続けていきたいと考えたからです。弟子入り後は巣箱も自分たちで手作りするなどし、約2年の歳月をかけ養蜂のイロハを身につけました。
地元・シモキタで始めた都市養蜂

「それまでは虫が大の苦手だったのですが、何度も見ているうちにミツバチたちがかわいく思えてしまって(笑)。料理人として働き、おいしいものには目がなかったということも、本格的に養蜂を学びたいと思ったきっかけですね。当時は養蜂場がある埼玉まで毎週通っていたのですが、ふと『都市養蜂(市街地のビルの屋上などで行う養蜂)として、住んでいる下北沢でもできないものか』と思ったんです。そう考えていたときに地元の同級生が教えてくれたのが、シモキタ園藝部の存在でした」
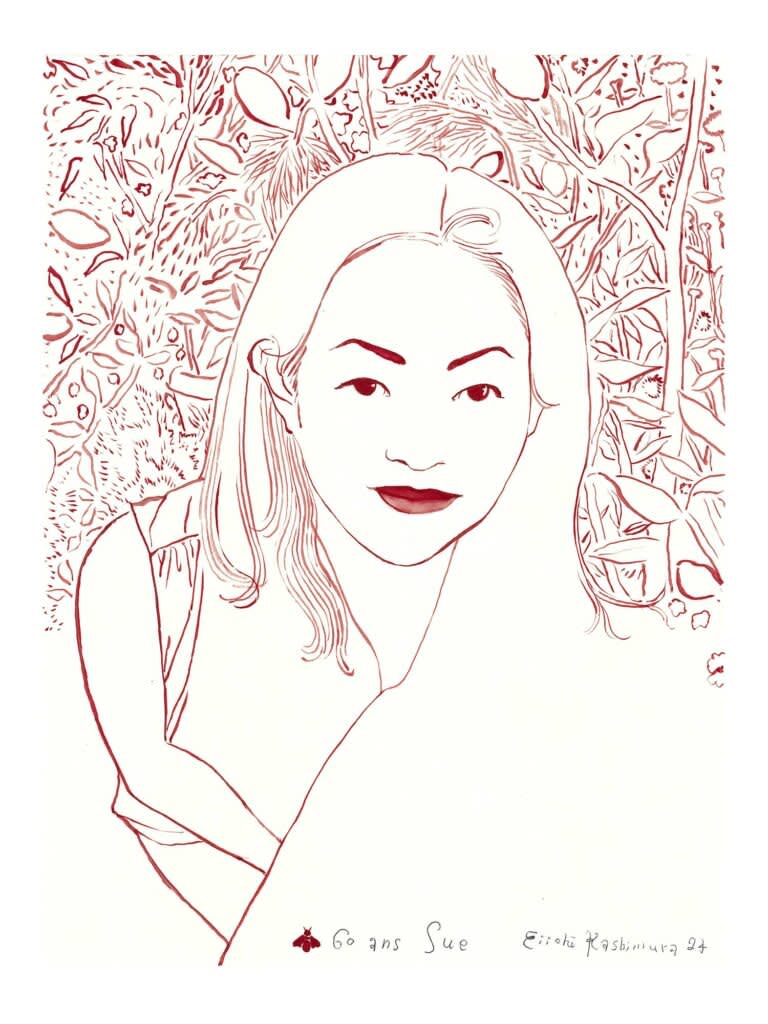
シモキタ園藝部は、小田急線の線路跡地に生まれた「下北線路街」で植栽管理を行っている地域コミュニティ。自然豊かな広場や遊歩道など、シモキタの街の植物を守り育てていくことを目的としています。
地元の同級生が在籍していた縁もあり、自身もシモキタ園藝部への入部を決めた杉山さん。半径約2kmの範囲にある花々から蜜を集めてくるというミツバチの特性をふまえ、ミツバチの花粉媒介によって緑がより豊かになり、街の空気もきれいになるという、シモキタで都市養蜂を行うことの意義を部員たちに語りました。こうして、都市養蜂のサステナブルな魅力と杉山さんの熱意が伝わり、シモキタ園藝部の養蜂チームとして活動できることになり、巣箱を設置する場所も見つけることができました。
ミツバチたちが目指すのはビルの屋上

「シモキタ園藝部の方々には『養蜂が始まってから、緑地の花や実の付きが目に見えて良くなった』と言っていただいています。私たちは大規模な養蜂をしているわけではありませんが、街の緑を豊かにすることに少しは役立っているのかなと思っています」
ミツバチは比較的おとなしい性格で知られ、むやみに人を刺してくることはありません。毒針を刺すと内臓ごと引きちぎれて死んでしまうこともあり、攻撃は自身の命と引き換えにした最後の防衛手段。しかし、巣箱に近づくなど、自身や仲間に危害が及ぶと感じた場合には刺してくることもあります。
人気のスポットとしてだけでなく、閑静な住宅街という一面もあるシモキタ。多くの人が集まる街で、人を刺す可能性もあるミツバチを飼うことに危険性はないのでしょうか。
「みなさんに必要以上に不安を感じさせてしまわないよう、巣箱は人が普段立ち入らないビルの屋上に設置し、安全上の理由で場所も非公開としています。ミツバチたちは巣箱から出てしまえば単独行動で、1匹で飛んでいる際はほとんど視認できないような大きさ。外で人と接する機会は多くなく、巣箱の周辺以外での危険性はほとんどないんです」

巣箱が置かれているのは、とあるビルの屋上。蜜を探しに行くミツバチにとっても、高いところから低いところに飛ぶ方が移動が容易というメリットがあるといいます。巣箱を開ける際はさすがのミツバチも攻撃してくることがあるため、杉山さんたちも養蜂用の防護服を着用し採蜜の作業を進めます。
この日は天気が良かったこともあり、巣箱の前で仲間に蜜のありかを知らせる「8の字ダンス」を披露するなど、ミツバチたちも活発に活動していました。
一方で、ミツバチにとって最も脅威となる存在が、同じハチの仲間であり捕食者のスズメバチ。その攻撃性の高さゆえ、人間にも毎年多数の死者が出ている危険生物です。
襲いかかってくる天敵のスズメバチに対し、在来種のニホンミツバチは一斉に飛びかかり熱で蒸し殺す「熱殺蜂球」と呼ばれる防衛手段で対抗します。これは1995年に玉川大学農学部の小野正人教授らが世界で初めて発見したもので、その後の研究ではセイヨウミツバチも稀に蜂球をつくることがわかっていますが、ほとんどの場合は有効な対抗手段を持ちません。つまり、セイヨウミツバチは養蜂家の助けなくして生き残ることはできないのです。
「幸いなことに、今のところ私たちの巣箱はスズメバチに見つかっていないようです。ですが、春から夏にかけて地上ではスズメバチが狩りを行っている時期。油断はできないため、巣箱の周りにもスズメバチが通れない大きさの穴が開いたネットを被せるなどの対策をしています。ミツバチたちを守りたいという気持ちはもちろんですが、養蜂家にとってもスズメバチの存在は命に関わる脅威ですから」
地元住民に愛される名産品に

人との共生を目指して見つけたビルの屋上で、我が子のように大切に育てている40万匹以上ものミツバチ。こうして彼女たち(働きバチは全てメス)がシモキタ周辺のさまざまな場所から集めてきた花蜜を元にできるハチミツが、いわゆる百花蜜。「シモキタハニー」としてシモキタ園藝部が運営する店舗「ちゃや」などで販売されているほか、商店街が行うアンケートやキャンペーンの景品としても採用されています。
35gが500円、125gが1700円、230gが3000円で販売されているシモキタハニー。125gと230gはリターナブル瓶(詰め替えで繰り返し使用可能な瓶)を採用し、2回目の購入の際には同じ瓶の使用で500円引きで販売されています。ゴミの削減というエコな観点も意識しつつ、事業を継続させていくためのマーケティング戦略としても機能していると杉山さんは話します。

「休日は観光客でごった返すシモキタですが、長年この地に根ざして生活しているという人も多いんです。そこでハチミツを販売するなら、まずは住民に受け入れてもらうことが不可欠。そのため、最も小さい35gは手に取りやすいワンコインの500円にしました。そして、一度試してみて気に入ったら、リターナブル瓶のサイズを買ってもらう。次からは500円引きの特典が受けられる常連になってもらうという、循環も意識した戦略で事業を進めています」

シモキタハニーは、世田谷区のふるさと納税の返礼品にも選ばれています。また、区にゆかりのある商品から選ばれた「世田谷みやげ」にもなっているなど、シモキタを代表する商品としても少しずつ知名度を上げています。
「なかには『シモキタの名産品になっているよね』と言ってくださる方もいて、農業や畜産業がないこの街で、新たな一次産業を始めることができたという自負はあります。もちろんハチミツそのものがおいしくなければ話になりませんが、いつ採蜜しても本当においしいんですよ。それは、シモキタ園藝部が大切に手入れをしている下北線路街の緑地をはじめ、近隣の住宅や公園に美しい草花がたくさん咲いているおかげもありますね。採蜜日を書いたラベルは蓋にも貼っていますが、その時に咲いている花などの種類によって味が変化していくのがシモキタハニーの特徴。季節の移り変わりとともに味比べもできる、地元産の自慢のハチミツなんです」
