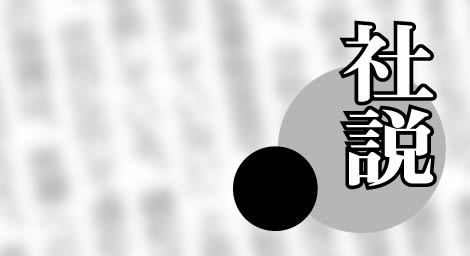
検察が、この期に及んで自らの体面を優先させたとしか思えない。
1966年に静岡県で起きた強盗殺人事件を巡り、死刑が確定した袴田巌さんの再審公判が、きのう静岡地裁で結審した。最初の再審請求から実に42年たった昨年3月に東京高裁が裁判のやり直しを認め、10月から審理していた。
検察はなお袴田さんの有罪立証の方針で臨み、死刑を求刑した。全く理解できない。
再審は、無罪を言い渡すべき明らかな証拠が新たに見つかった時に開かれる。確定判決の誤りを正し、冤罪(えんざい)の被害者を救済する手段だ。再審開始の決定では、有罪にした唯一の証拠と言っていい5点の衣類を巡り、弁護側の主張を認め、「捜査機関による証拠捏造(ねつぞう)の可能性が極めて高い」と厳しく批判した。
再審開始の意味は重い。無罪を前提にした迅速な審理こそ求められていたはずだ。
袴田さんは、ずさんな捜査や裁判所の判断にほんろうされるうち88歳になった。10年前に釈放されたが、長い収監や死刑の恐怖による拘禁反応で意思疎通が難しい状態だ。
最大の争点は、犯行時の着衣とされた5点の衣類に付着した血痕の「赤み」である。
衣類は事件発生の1年2カ月後にみそ工場のタンクで発見された。弁護側は長期間みそ漬けされたら血痕は黒く変色するはずで、赤みがあるのは発見直前に袴田さん以外の誰かが入れたからとした。
検察側は新たな専門家の共同鑑定書を基に「赤みが残るのは不自然ではない」とした。しかし長年の主張と違いはなく、衣類の調べはほぼ尽くされている。いたずらに時間を費やしただけだ。捏造の可能性が指摘され、意地になっただけと疑ってしまう。
本来、検察側が真っ先にすべきなのは、袴田さんへの自白強要の有無や、証拠捏造の疑いなど、長い裁判で示されてきた問題点の検証である。
再審では、これら問題点を省みることはなかった。組織防衛に走らず誠実に向き合ったなら、求刑をしない判断があり得た。法廷で事件の被害者遺族による「真実を明らかにしてほしい」との意見陳述書を、検察側は読み上げた。だが現行の姿勢のままでは、求められた捜査機関の役割を果たせないままになる。
現行の再審制度が、救済の機能を果たしていないのは明らかだ。袴田さんの場合、2014年に静岡地裁が再審開始を認め、釈放したにもかかわらず、検察の即時抗告によって取り消され、再審開始が確定するまで9年かかった。
再審手続きは、現行の刑事訴訟法に具体的な規定がほとんどない。審理の進め方は裁判官の裁量に委ねられ、長引く要因の一つになってきた。また過去の冤罪事件で警察や検察が不利な証拠を隠していた例は少なくない。
袴田さんの裁判では、第2次請求中の10年にようやく衣類のカラー写真などが開示され、再審開始につながった。検察に全ての証拠開示を義務付けるのは必須である。
著しい人権侵害を見逃さないよう制度改正が急務だ。
