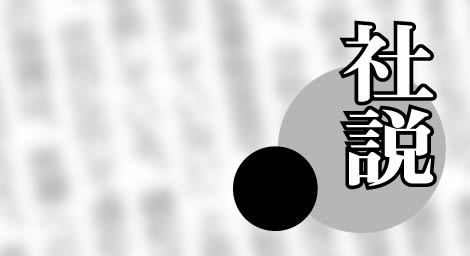
米国の企業家イーロン・マスク氏は先日、2年以内に人工知能(AI)が人間より賢くなる、と豪語した。その通りになるかどうかはともかく産業、教育、医療・福祉など多様な分野で、日進月歩のAI技術が従来のありようを変えていくのは確かだろう。
AIが暮らしを支え、世の中の利便性を増す。そうした有益な点ばかりなら心配はない。しかし、ここにきて世界で規制する動きが出てきた。自在に文章や映像などをつくる生成AIの登場がきっかけだ。遅れていた日本政府が、ようやく法規制の検討に着手したのも必然と言えよう。
AIの負の側面とは何か。瞬時にデータを集め、加工したものが悪用され、人権侵害や詐欺行為、偽情報拡散などに至ることがまず懸念されている。また医療機器や自動車が誤作動する可能性もなくはないだろう。開発の加速に合わせ、こうした問題に事前に手を打つ法的な枠組みが求められている。
世界の潮流は先を行く。この21日には欧州連合(EU)が民主主義と人権の尊重を旗印に、世界初のAIの包括規制法を制定した。具体的なリスクを4分類し、選挙などで個人の潜在意識を操作するようなAI利用、人種や政治志向を生体認証データで推測することなどを禁じる。そして違反に巨額の制裁金を科す。
EU域外でも適用されるだけに日本企業を含めて影響は大きい。米国でも法規制の議論は本格化するとみていい。
日本政府も無関心だったわけではない。1年前の先進7カ国首脳会議(G7広島サミット)を踏まえ、日本が主導して生成AIに関する国際ルールの枠組み「広島AIプロセス」が立ち上げられた。
一方で、国内では開発と活用を優先してAI規制に消極的だったのは否めない。4月に決定したAI事業者向けの指針も自主的な対応に任せる形だった。世界の動きに押されて方針を一転し、法規制にかじを切ったことになる。
企業活動に制約が生じる面もあるため政府には慎重論も残ると聞く。開発者らを対象に法整備を想定するというがAIのリスクをどう定義し、どんな手法で法の網にかけるかの議論はこれからだ。
忘れてはならない論点は、幾つもある。まずは知的財産権の侵害の恐れだ。現状では生成AIが芸術、映像、研究成果、報道などの著作物を勝手に使いかねない。なのに政府は2018年の著作権法改正では逆に、著作物を許可なくAIに学習させることを認めた経緯がある。今こそ法的な歯止めを図るべきだ。
もう一つは兵器への転用防止である。ウクライナ、ガザの戦場では、既に殺傷兵器や作戦でAIが使われているとされる。さらに人間の指示なしにAIが敵を殺傷する「自律型致死兵器システム」の規制も国連の大きな懸案となっている。平和国家をうたう日本も当然、無縁ではない。
AIを名実ともに人類の味方とし、将来にわたって憂いなく活用するためにも今こそ立ち止まり、その功罪を徹底的に検証してもらいたい。
