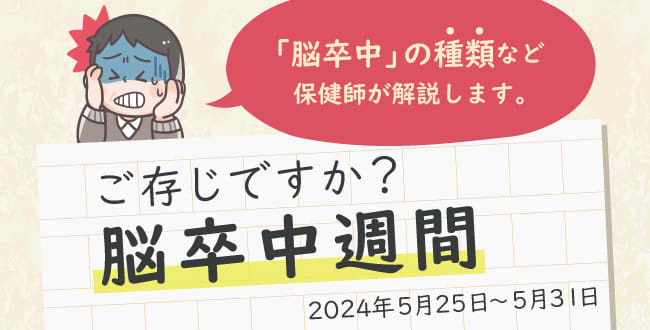
5月25日から31日は脳卒中週間です。
2022年の人口動態統計の死亡数を順位別にみると、第1位は悪性新生物、第2位は心血管疾患、第3位は老衰、第4位は、脳血管疾患となっています。脳血管疾患は、1970年をピークに低下傾向にあり、全死亡者における割合としては、6.8%となっています。
死因としては減少傾向にあるものの、脳卒中の予防に関する知識の普及啓発はまだ充分とは言い切れない状況です。
米国では脳卒中月間、英国では脳卒中週間を設定して、啓発活動等を行っています。
脳卒中のなかで多くの割合を占める脳梗塞の発症は、春に少なく6月から8月から増加することが明らかになっています。
日本では、2002年から5月25日から31日を脳卒中週間と定め、日本脳卒中協会主催、厚生労働省後援で、啓発活動を行っています。
脳卒中ってどんな病気?
脳卒中とは、脳の血管が詰まる、破れるなどが原因で脳の一部の働きが悪くなり、それによって身体の働きに悪影響を及ぼす疾患であり、介護が必要となる原因疾患としても知られています。
症状としては、片方の手足・顔半分の麻痺やしびれが起こる、言葉が出てこない、呂律が回らない、立てない、歩行が困難、などがあげられます。自分ではわからなくても、他人が見て気が付くこともあります。
脳の血管が詰まる、破れる最大の危険因子は、加齢と高血圧です。
高血圧は、脳の血管の大きな負担となるため、血圧を適正値にコントロールすることは、脳卒中の予防につながります。
脳卒中には種類があります
脳卒中には、脳の血管が詰まる脳梗塞と、血管が破れて出血する脳出血があります。
脳梗塞
脳梗塞は、脳卒中の過半数を占める疾患です。
脳の血管が詰まり、血流が十分にいきわたらなくなり、脳細胞の働きが悪くなります。
その結果、半身麻痺などの症状が出て、血流が滞る状態が数時間継続すると、脳細胞は壊死してしまいます。
早い段階で治療ができれば脳細胞の壊死は回避できます。程度はさまざまですが、多くの方が後遺症を残す疾患です。
脳出血
脳の細い血管が破れて出血し、その部分の神経細胞が障害される疾患です。
脳梗塞よりも後遺症が残ることが多く、死亡率も高い怖い疾患であり、原因の多くは高血圧です。
くも膜下出血
くも膜下出血は、脳の表面を覆う膜のひとつである「くも膜」の下に出血がある状態をいいます。この部分の出血は、脳や髄膜を刺激して、激しい頭痛や嘔吐を引き起こします。
原因としては、脳の血管の膨らみである「脳動脈瘤」の破裂によります。
予防と検査
脳卒中の大きな原因のひとつ、高血圧を予防しましょう。
高血圧はサイレントキラーと呼ばれており、自覚症状のないままで、血管に負担を与えています。
定期健康診断での値の確認、高めの方やご家族に高血圧の方がいらっしゃる方は、家庭血圧を測定しましょう。
高血圧は、体質のほかに生活習慣も影響しています。塩分摂取、喫煙、飲酒、肥満等の改善を心がけましょう。
また、検査でリスクを調べることもできます。脳ドックは、脳の状態を直接調べる専門のドックで、脳の疾患や異変を検出します。
基本的な脳ドックでは、頭部MRI/MRA、頸動脈エコー検査が行われます。
必要に応じて追加していただくオプションの検査になりますので、受けたことのない方はご検討ください。
