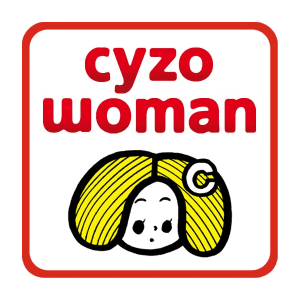5月15日、STARTO(旧ジャニーズ)から新グループ、Aぇ!groupが「《A》BEGINNING」でデビュー。グループの代表曲ともいえるデビュー曲について、語りたくなる名曲をライター・太田サトルがつづります!
目次
・Hey!Say!JUMPのデビュー曲が持ってしまった意味
・歌いだしまで36秒の“もったいつけ”
・「Ultra Music Power」持つ不思議な運命
Hey!Say!JUMPデビュー曲が持ってしまった意味
2007年11月14日に発売されたHey!Say!JUMPのデビューシングル「Ultra Music Power」。
念願のデビュー曲の歌いだしは<喜び悲しみ 受け入れて生きる>。
記念すべきデビュー曲の歌い出しなのに、「喜び」とともに「悲しみ」も、しかもそれらを「受け入れ」るよう歌わされた彼ら。しかも、そのあとに<誰でもみんなが 孤独な戦士>なのだと続く。
実際、Hey! Say! JUMPのデビューは、どこかいろんなものを受け入れ背負うかのような一面もあったことは確かだった。
そして、ジャニー喜多川氏の性加害問題を受け、この曲は「今後歌わない」という判断がくだされ、YouTubeのグループ公式チャンネルから動画も削除された。昨年12月から開催された全国4カ所で開催されたドームツアーにおいても、この曲は披露されていない。彼らの16年の以上にわたる活動の中で、コンサートツアーで歌われなかったことはおそらく初めてのことだろう。
しかし、Hey!Say!JUMPはグループのこれからのために「歌わない」ということを受け入れて生きることを選んだのだ。
事実上「消えたデビュー曲」となってしまったこの曲。しかしこの曲が名曲であることは間違いない。その記憶をとどめておくためにも、幻となったデビュー曲を振り返っておきたい。
歌いだしまで36秒の“もったいつけ”
デビューシングル「Ultra Music Power」は、同年開催されたバレーボールワールドカップのイメージソングとして採用された。V6、嵐、NEWSという豪華な先輩グループに続く4年に一度の大型デビューグループとして注目を集め、サプライズ要素が強いメンバー構成には期待度の高さもうかがわれた。
作曲は「DAYBREAK」や「勇気100%」「笑顔のゲンキ」「愛されるより愛したい」、「A・RA・SHI」「浪花いろは節」「NEWSニッポン」など、数々のジャニーズ名曲、そしてデビュー曲をこの世に送り出してきた馬飼野康二によるもの。
そんなデビュー曲「Ultra Music Power」は、もしかしたら全く別の曲のアイデアだったかもしれないような、バラエティに富んだフレーズが、これでもかというぐらい、4分ちょっとの中にてんこもりで詰め込まれたような印象を受ける。
まずは重厚な銅鑼(どら)の音とともに響く、彼らのまだ少年ぽさを残した声質の「ララララ〜」というコーラス。一転、軽快なファンファーレのようなシンセサイザーのフレーズとともに、名刺代わりに「JUMP」の頭文字を引用した単語を歌いあげる。
さらにイントロは続き、もう一度「J・U・M・P」の頭文字となる別の単語を歌ったところで、ようやく歌い出す。ここまでだいたい36秒。もったいつけられてる感、すごい。
もしかしたら、上記のどれかのパートをごっそりなくしても成立するかもしれない。しかし、その瞬間に「いい」と感じたものを全部入れるーーそれこそ喜び、悲しみもすべてを投入したのだろう。それら素材をシェフの熟練の技で繋ぎ合わせ、ひとつの料理に仕上げたような楽曲という印象だ。
「Ultra Music Power」持つ不思議な運命
しかし、Hey!Say!JUMPは大切な宝物を封印するという、あまりにも大きな決意をした。今後実施されるかはわからないが、複数のグループによって披露される「デビュー曲メドレー」といった類いのパフォーマンスが実施された場合、Hey!Say!JUMPは何を歌うのだろうか。
この先、ジュニアたちによって歌い継がれる名曲群からも「Ultra Music Power」は外されるということでもある。今後、この曲を聞きたいと思った人も、同曲が収録されたCDやコンサートDVDなどを所有していなければ、かなわないことも事実だ。
そのひとつのフレーズだけで、と感じる人は今も多いだろう。しかし、そのひとつのフレーズが、たったひとつのフレーズが、あまりにも重かったということだ。
奇しくも前回の15周年を飾るツアーでメンバーが笑顔で肩を組んで歌うという、多幸感に満ちあふれたパフォーマンスが、現時点で最後のパフォーマンスとなったこと。これもまた、この曲の持つ不思議な運命、できすぎた最後だったようにも感じられる。