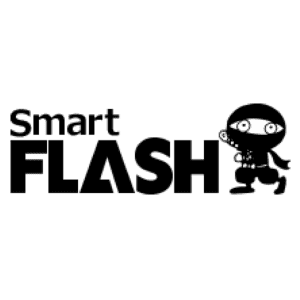経済財政諮問会議で議長を務めた岸田文雄首相
5月23日、岸田文雄首相が議長を務める経済財政諮問会議が開かれ、ウェルビーイング(身も心も満たされた状態)社会の実現に向けた方策が議論された。
民間議員は、高齢者の健康寿命が延びていることを踏まえ、現在は65歳以上とされている高齢者の定義について「5歳延ばすことを検討すべき」と指摘。その上で、全世代のリスキリング(学び直し)推進を提言した。
時事通信によると、岸田首相は「誰もが活躍できるウェルビーイングの高い社会を実現しないといけない」と強調。リスキリング強化の方策を6月ごろに策定する経済財政運営の基本指針「骨太の方針」に盛り込む考えを示したという。
リスキリングは社会保障の強靭化と一体となって議論されている。この点で参考になるのが、自民党の茂木敏充幹事長が語った持論だ。
5月12日、茂木氏はYouTubeチャンネル『ReHacQ-リハック-』に出演し、こう語っている。
「これから人生100年時代ですから、ある程度の年齢まで生きると90歳以上、生きます。もうすぐ100歳、生きますよ。
大学を卒業したら就職して、同じ仕事をずっとして定年を迎えるシングルパスでなくて、大学を卒業しても、いったん勤めてから学び直すとか、ある程度、勤めてから、ハーフリタイアして、半分は仕事しながら、半分は趣味に使う。いろんな人生のマルチパスを選べる時代になっている。
50歳、60歳が高齢ではない。50年前と違うんです。1950年代に日本の社会保障制度はできるんです。いまの医療保険や年金の制度ができるんですけど、そのころは男性の平均寿命は58歳。当時は定年が55歳だった。つまり人生60年、70年時代。その時代に医療保険制度や年金制度を作っているから、なかなか財政的にも厳しくなる」
すでに厚生労働省は、自営業者らが加入する国民年金の保険料について、納付期間を現在の「60歳までの40年」から「65歳までの45年」に5年間延長した場合の試算を検証する方針を固めている。
長期的な年金財政を点検する「財政検証」で試算し、2024年夏に検証結果を公表。年末までに実施の可否を決める方針だ。単純計算をすると、5年間納付期間が延長されれば、1人100万円の負担増となる。
4月18日、衆院本会議で、岸田首相は、納付期間の延長について厚労省が試算することに対し、こう答弁した。
「年金制度改正の検討の参考とするために、2019年の制度改正の際と同様の試算をおこなうものであり、方向性についてなんら予断を与えるものでもなければ、私の意思が反映されているものでもない」
だが、茂木氏が語った持論から考えれば、医療保険や年金などの社会保障において、高齢者の定義を「5歳延ばす」ことは十分ありうるということだろう。
実際、高齢者の定義について「5歳延ばすことを検討すべき」と諮問会議で提言されたことに、Xでは、社会保障への不安を吐露する声が多く上がっている。
《岸田内閣、高齢者の定義5歳引き上げ画策?…これって、年金支給を70歳からにしたいって魂胆・布石だよね》
《はいはい70歳からの年金受給開始のためにね。そもそもすでに60歳から開始年齢5歳引き上げて今に至ってるのに。65歳で一体何人が健康や足腰に不自由なく働けると思ってるのか》
《高齢者の定義を70歳に上げる。後期高齢者を80歳に引き上げる。今のうちに早く65歳になって、年金の権利を取得してしまわないと、70歳まで働かされる》
《現在64歳です。この歳で働こうと思っても体がうまいこと動きません。働いたところでまともに生活できるお給料はもらえません。 65歳から高齢者と言われても致し方がないと私は思っていますが、70歳から高齢者と言われるように設定されると困ります。年をとっても働け働けと言われるけれども働けない人間だっているんです》
リスキリングを建前に、年金支給年齢を引き上げられたら、たまったものではない。