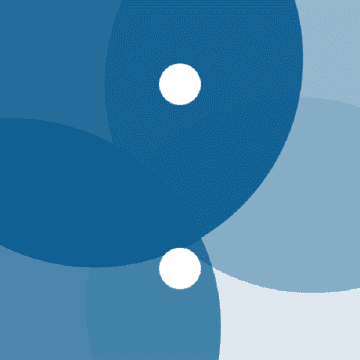耳が聞こえない人にとっての言語の1つである「日本手話」を巡り、札幌聾学校に通う児童らが道を訴えている裁判。24日、札幌地裁は原告の訴えを退けました。
原告の母親)
「娘の第一言語は日本手話。第一言語で学ぶ難しさを感じる判決だった」。
訴えを起こしていたのは生まれつき耳が聞こえない小学5年の男の子と中学2年の女の子です。2人は道立の札幌聾学校で幼いころから使っている「日本手話」で授業を受けられず、「教育を受ける権利」を侵害されたとして道に対しそれぞれ550万円の損害賠償を求めていました。
小学生の男の子)
「授業が受けられなくて苦しい」。
中学生の女の子)
「通じない分からないところが多かった」。
2人が使う「日本手話」とは、一体どんなものなのでしょうか。東京にすべての授業を日本手話で行うろう学校があります。
明晴学園・榧陽子先生)
「日本手話はろう者の中で自然に生まれた言語であり、視覚言語です」。
日本手話とは、日本語とは異なる独自の文法を持つ言語で、生まれつき耳が聞こえない人たちが主に使っています。一方で日本には「日本語対応手話」と呼ばれるものもあります。
これは日本語の語順に合わせて手話の単語を当てはめたものです。
日本手話で表現)「生徒/が/違う/席/に/座って/びっくり/しました」。
同じ文を日本手話で表現すると…
日本手話で表現)「生徒が違う席に座ってびっくりしました」。
その違いは一目瞭然です。日本手話は日本語とは違います。札幌聾学校でも、2007年に日本手話を活用した指導を開始。今回裁判を起こした2人も、日本手話での授業を希望して学校に通っていましたが、担任になった教師が日本手話ができず授業が受けられなくなったと訴えています。和解交渉も決裂し、道は訴えを退けるよう求めていました。
そしてむかえた24日の判決。札幌地裁の守山修生裁判長裁判長は、「日本手話で授業を受ける権利が具体的に憲法上保証されたものとはいえない」、「日本手話以外の表現方法でも教師と児童が一定のコミュニケーションを取ることは可能」などとして原告の訴えを退けました。
原告の父親)
「(学校に)もうだまされた」。
バイリンガル教育が専門の立命館大学佐野愛子教授)
「判決理由の中には、日本手話が1つの言語であるという理解が全く欠けているということを言わざるを得ないと思います」。
24日の定例会見で鈴木知事は判決についての受け止めを聞かれ、こう答えました。
鈴木直道知事)
「詳しい内容は承知していない」、「道内すべての特別支援学校において、学習指導要領に基づく適切な教育を提供していただきたいと思う」。
「自分の言葉」である日本手話で学びたい。そう願い訴えを起こした子どもたち。原告側は、控訴するかどうかを今後検討するとしています。