
フランスの子ども家庭福祉を研究し、『一人ひとりに届ける福祉が支える フランスの子どもの育ちと家族』の著書がある安發明子さん。安發さんは、フランスで妊娠・出産し、現在は7歳の娘を子育て中です。フランスの取り組みを伝えることで、日本の子育て支援や福祉の発展に貢献できるのではないかと考えている安發さんに話を聞きます。
全3回のインタビューの1回目です。
フランス人の夫と国際結婚。育休3カ月目に「いつ仕事復帰するの?」と聞かれ、日本とフランスの違いを痛感【体験談】
人と比べないスイスの小学校。だからコンプレックスを感じたことがなかった

安發さんは父親の仕事の都合で、小学校4年間をスイスで過ごしました。その後、日本の学校を卒業し、福祉の仕事につきました。
――スイスの小学校生活について教えてください。
安發さん(以下敬称略) 小学校2年生から6年生の途中まで、スイス・ジュネーブの小学校に通いました。1988~1991年のことです。スイスは幼稚園と小学校が一貫教育でクラス替えがないので、クラスメイトはきょうだい、先生は親のような関係でした。私が娘をフランスで出産したときにも、スイス時代の担任の先生が会いに来てくれました。今でも悩んだときには、その先生に相談することが多いです。
クラスメイトは今では、世界中バラバラに散らばって活躍しているけれど、定期的に集まっています。
――スイス時代でとくに印象に残っていることは?
安發 人と比べられることが1度もありませんでした。背の順で並ぶこともなければ、男女で分けることもない。コンプレックスを感じることがないから、ゆっくりしていたように感じます。
授業は自分の住む地域のことを学ぶことから始めて、スイスのこと、世界のことと、理解力に合わせて学ぶ範囲を広げていきます。今、戦争をしているのはなぜなのか、宗教が違うってどういうことなのかなど、子どもが抱く疑問に答える形で授業が進められたので、今でもよく覚えています。知識が身につくとおのずと興味が広がっていき、国のこと、世界のことへと好奇心が広がっていく。学ぶことは楽しいことなんだと、スイスの小学校は教えてくれました。
困っている子どもを助けてくれない日本の大人に、不信感を持った高校時代

――1991年に帰国して入った日本の学校については、どのように感じましたか。
安發 日本の小学校に転校した初日、クラスの女子に「○○さんのことをシカトしないと、あなたのこともシカトするからね」と宣言されました。なんていうところに来てしまったんだろうと、心配になりました。
中学受験のために通った塾は、お弁当を食べる時間はたった15分!子どもなのに夜遅くまで勉強する、休みの日も朝から晩まで塾に行く生活でした。
その後入学した中高一貫校は、教科書通りに学ぶ授業スタイルで、学内イベントはすべて先生が決めて、生徒はそれに従うだけ。
ジュネーブの小学校では、校外学習の計画は子どもたち自身が考え、出かけていましたから、日本の学校生活は与えられたものをそのまま受け入れていかなければならない、そのように感じていました。
――周囲の大人に不信感を持つことが多々あったとか。
安發 子どもたちが苦しんだり、のびのびと過ごしたりできない状況があったとしても、助けてくれる人がいないということへのひっかかりが、大きくなっていきました。
小学校時代はまわりに、ストレスで髪の毛を引き抜いている子、リストカットをしている子、拒食傾向がある子、宗教施設で暮らしていて学校に行っていない子たちもいて、それらのことを大人たちに質問をしても、子どもたちのために何かをしようと動いているようには感じられませんでした。
車上生活をしていた小学校時代の友だちがいて、結局2年間学校に行かなかったのですが、先生もだれも迎えに来なかったと言っていました。すごく優秀で活発な友だちがとても苦労しているのを見て、彼女の苦労は決して彼女のせいでも親のせいでもない、大人たちが助けないからだと思っていました。
私立の中高一貫校に入ってからも、助けを必要とする子どもが助けられていない状況は同じでした。毎朝学校に到着をすると、登校時の痴漢行為について怒りをはき出し合うのが日課でしたが、大人たちは「気をつけなさい」としか言いませんでした。
また、母と姉にいじめられている友だちがいたのですが、彼氏ができて喜んでいた矢先、退学させられてしまいました。退学にしたところで何の解決にもなりません。
困難な状況を生きる子どもが幸せに生きられる支えとなるような仕事がしたいと、自然と考えるようになっていました。
困っている親をサポートしたかった。でも方法がたりず無力感からうつ病に

――大学時代に、施設で暮らす子どもたちの学習ボランティアをしていたとか。
安發 18~21歳のころ、児童保護施設に出向いて勉強を教えるボランティアをしていました。その施設に、成績優秀で進学を希望していたのに、結局進学できなかった子がいました。学費減免などの対象とならないか、大学へ一緒に相談しに行きましたが、親の死亡も天災も失業も該当しないので、対象にならないと言われました。
その子は「家族に頼れない自分が、奨学金という名の借金を背負って生きるのは荷が重すぎる」と話していました。折しも新聞奨学生が過労死したというニュースもあったころでした。
日本は先進国であるはずなのに、こんなことがあるのはおかしい!すべての子どもに機会がある世の中でなければいけない、という思いを強くしました。
――その後はどのような活動をされたのですか。
安發 最初に日本の施設で衝撃を受けてからというもの、学生時代は日本全国とスイスの施設や少年院をめぐる旅行ばかりしていました。
そして、日本とスイス、同じような事情で子どもが施設に来ても、制度が違えば子どもたちの世界観も将来の見通しも違うということを、子どもたちの語るライフヒストリーをもとに『親なき子』(ペンネーム島津あき)という本にまとめました。2008年のことです。
――卒業後、生活保護ワーカーの仕事を選んだのはどうしてでしょうか。
安發 日本では子どもの選択肢は親の経済力や考え方の影響を強く受けるのであれば、親を支える仕事をしようと思ったんです。
でも、14歳の母親から生まれた新生児が1人で日中過ごしていても、「虐待ではないから支援の対象にならない」と言われるようなことがあり、使えるサポートが本当に少なかったです。子どものニーズに最大限応え、よりよい状況をめざす福祉ではなく、緊急性が高いと認められなければサポートの枠組みにさえ入れない状況がありました。
さらに、子どもから親への暴力に悩んでいる家族、病気の母親と障害のある妹を若者が経済的に1人で支えている状況などをみて、スイスだったらあんな方法もこんな方法もあるのに・・・と、感じることがとても多かったです。
夫のDVから子どもとともに逃れてきた女性は、「仕事をしなければ」と、子どもと過ごせる時間が短くなりました。母子ともに大変な経験をしたことへのケアはたりず、子どもが調子を崩してしまう状況を目の当たりにしました。
福祉を利用することで生活が改善され、親子が幸せになっていくようなソーシャルワークができる枠組みにはなっていないと感じました。無力感からうつ病になり、2年で退職しました。
日本の親子支援をする実務者と工夫やアイデアを分かち合いたい
――29歳のときに渡仏したとか。フランスを選んだ理由とは?
安發 スイスは福祉の予算がたくさんあり、人口が少なく、日本とは違いが大きすぎました。
一方、フランスは1960年代までの家族の暮らしは、今の日本とそう変わりません。70年代に多くの女性が立ち上がり、女性と子どもが守られるための改革が続けられてきました。日本と同じような課題に、フランスはどのように立ち向かっているのかを学ぶことは、意義があると思いました。
とくに専門職が誇りを持っていて、「自分たちが権利と尊厳を守る福祉を実現するんだ」「人が守られる社会を作るんだ」という意気込みで取り組んでいるところが大好きで、会いたい人がたくさんいます。調査のたびに感動し、夢中で通い続けている状況です。
最初は飲食の仕事をし、その後はフリーランスで通訳などをして働きながら、フランスの大学院に入学しました。フランスでは授業料が無料であることを知り、入学した部分もありました。
外国から来た私でも、学費無料で大学院に行くことができたから今の活動ができていて、無料で体外受精を受けることができたから子どもに恵まれ、うつ病も過去のこととなり、元気に暮らしています。
「一億総活躍」というモットーが日本にはあります。これがかなうように、具体的に人の暮らしを支える手だてを用意してほしいと願っています。
――安發さんは現在、フランスの子育て支援についての情報を日本に発信する活動をしています。
安發 すべての子どもが幸せな子ども時代を過ごせる社会を作ることをめざしています。もちろんフランスにも課題はいろいろありますが、福祉の現場は女性が非常に多く、頼もしいマダムがたくさんいるので、どこか安心感があります。「この状況を今すぐ解決できないなんて福祉国家として恥ずべきこと!」と怒りながら、決してあきらめることなく、たたかっています。すべての人が居心地よく生きられる社会を作ろうとしているんです。
フランスの福祉の現場にかかわっている専門職たちは、自分たちのことを「ミリタン」と言います。ミリタンとは「信念を貫きたたかう」という意味です。子どもの幸せが親しだい、地域しだい、出会いしだいにならないよう、私も日本でミリタンとしてたたかい続けたいです。
70年代にフランスで保健大臣を務めた女性を描いた「シモーヌ」という映画はおすすめです。考えを堂々と言うシモーヌの姿に励まされます。
お話・写真提供/安發明子さん 取材・文/東裕美、たまひよONLINE編集部
日本でのいくつかの活動を経て、フランスに渡り、フランスの子育て支援策を日本に向けて発信している安發さん。「外からの視点があることで、当たり前と思っていたことについて、よりよい方法を模索することができると思うのです。みんながよい子育て経験をすることができ、すべての子どもが幸せな子ども時代を過ごせる社会を実現することをめざしています」と話します。
安發明子さん(あわあきこ)
PROFILE
フランス子ども家庭福祉研究者。一橋大学社会学部卒業。フランス国立社会科学高等研究院健康社会政策学修士、社会学修士。大学時代に日本全国とスイスで児童保護分野の機関のフィールドワーク調査を行い、日本とスイスの子どものライフヒストリーを描いた『親なき子』(ペンネーム:島津あき 金曜日発行)を出版。卒業後、生活保護ワーカーとして働いたのち2011年渡仏。フランスの子ども家庭福祉分野の調査をしながら日本に発信。フランスで妊娠・出産し、日本人の夫、7歳の娘と暮らす。
●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。
●記事の内容は2024年5月の情報であり、現在と異なる場合があります。
『一人ひとりに届ける福祉が支える フランスの子どもの育ちと家族』
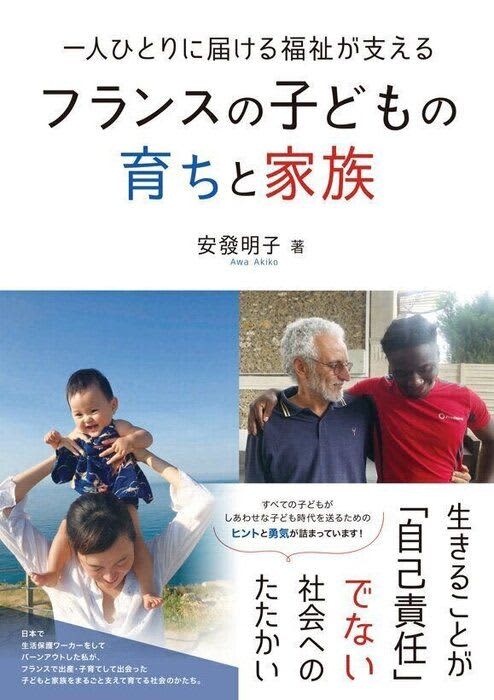
自身も経験したフランスでの妊娠・出産、子育て。そこには子どもと家族を丸ごと支えて育てる、社会のかたちがあった。「親をすることは簡単ではない」という考えをベースにしたフランスのさまざまな取り組みを、援助職・研究者のまなざしと親の立場で紹介。安發明子著/1800円+税(かもがわ出版)
