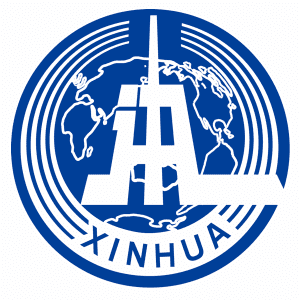浙江省金華市浦江県の上山考古遺跡公園。(2021年5月12日、ドローンから、浦江=新華社記者/黄宗治)
【新華社杭州5月24日】中国科学院地質・地球物理研究所などは24日、浙江省金華市浦江県にある新石器時代上山文化に属する複数の遺跡を対象に実施した水稲起源に関する研究で、野生から栽培にいたる10万年の進化史を解明したと発表した。今回の研究により、中国が世界の水稲の起源であり、約1万年前の上山文化が世界の農業に起源において重要な地位を占めることがさらに確認された。関連論文は同日、国際学術誌サイエンス電子版に掲載された。
同研究所の呂厚遠(りょ・こうえん)研究員のチームを中心に、浙江省文物考古研究所、臨沂(りんぎ)大学、浦江県上山遺跡管理センターなど国内13の大学、研究機関などが研究に参加。発表によると、野生の水稲と馴化した水稲を効果的に区別する基準を確立し、考古学発掘調査を踏まえた複合領域研究により一連の重大な発見を得たという。
研究によると、長江下流域では10万年前に野生の水稲が既に分布し、先住民が利用、馴化する条件を備えていた。約2万4千年前の最終氷期最盛期に人類は新たな食料を求めて野生水稲の採集、利用を開始。約1万3千年前に意図的また意図せずに栽培するようになり、約1万1千年前になると馴化稲が登場し、東アジアの稲作農業の起源となった。専門家は、人類発展史の重要な里程標だと指摘。稲作の起源と、西アジアのチグリス・ユーフラテス両河流域における麦作の起源は同時期だったと言えると述べた。
上山遺跡は2000年11月に発見され、2006年11月に同遺跡に属する文化が上山文化と命名された。これまでに発見された上山文化遺跡は24カ所で、いずれも浙江省にある。これらは現時点で、中国国内さらには東アジアで規模が最も大きく、分布が最も集中する初期新石器時代の遺跡群を構成している。