
政府が、「異次元の少子化対策」の一環として打ち出した「こどもファスト・トラック」について、出演している番組でも、賛否が話題になりました。これは、公共施設や商業施設などで、妊娠中やこども連れの方を優先するという取り組みで、大型連休にあわせて、国立の公園や博物館など全国20か所あまりで実施され、今後、スポーツ観戦や民間のレジャー施設のほか、郵便局や銀行などにも導入を働きかけていく方針とのことです。
実際の現場からの声では、小さなお子さんを連れたご家族から「とても助かる」という声が聞かれた一方で、長時間並んでいる方からは不満の声も聞かれ、施設側は「公平性が担保できない難しさを感じている」といったお話もありました。
私は、今回の政府の方針は、民意についての理解や政策の方向性がズレていて、そのことが、本来招かなくてよい社会の中での分断や反発を招いてしまっていると思いますので、ヨーロッパで出産・子育てをした経験も踏まえ、考えてみたいと思います。
ポイントは、
・子どもだけではなく、高齢者や障がいのある方なども対象とし、「広く社会が受け入れられる」内容にすることが肝要
・「ハンディのある方には皆で配慮をする」という意識の広まりが、寛容な社会を作る。押し付けではうまくいかない
・「こどもファスト・トラック」は「少子化対策」にはならないし、してほしくない。
・政府の「子育て支援」は、「子どもを生ませるため」ではなく、それ自体が必要なことだからやるべき。
・配慮される側も、「当然」ではなく、感謝の気持ちを持つことが大切
…といったことです。
対象がズレてる
フランスでは、公共施設やタクシー乗り場、美術館などで、広く「優先レーン」が普及しています。ただし、その対象は子どもや妊婦に限らず、高齢者や障がいのある方、ケガをしている方など、「長時間立って待つことに困難がある方」すべてで、すなわち「『一定の配慮が必要な方』に対して『必要な配慮をする』」という、社会通念上、至極当然のことが具体的に形になったもので、日本の電車の優先席と同じといえると思います。
私は、これが望ましいと思います。例えば、高齢者や障がいのある方、ケガで松葉杖をついた方などは、長時間立って列に並ばなくて済むようにした方がよい、と考える方は多いと思いますし、当然、妊婦さんや小さいお子さん連れの方も対象になります。
社会に広く受け入れるかどうかは、「たとえ炎天下に自分が並んでいても、『この人たちは、もっと大変そうだから、先に行ってもらおう』と、多くの方が思えるかどうか」だと思います。電車の優先席が広く受け入れられ、普及しているのと同じです。
また、「こどもファスト・トラック」の具体的運用は各施設に委ねられていて、「小学生以下」と設定しているところが多いようですが、これも、不公平感を生む一因であったかもしれないと思います。
自分の子どもを思い返しても、小学校高学年になれば、元気で体力があり、「待っていることが大変」ということもあまりないと思われ(もちろん「見えにくい障がいをお持ちの方」等には、配慮が必要)、むしろ、電車の優先席などでも、「高齢の方や小さいお子さん連れの方に譲ろうね」という「他者への思いやり」や「社会のルール」を実践する年齢だと思いますし、保護者としても、そうしてほしいと思う方が多いのではないでしょうか。
したがって、「こどもファスト・トラック」の対象は、未就学児か小学校低学年までとした方が、子ども自身にとっても望ましく、社会の理解も得やすいのではなかったかと思います(ただ、ごきょうだいで対応が分かれてしまうのは不合理なので、その場合は、小さいお子さんにあわせる、という運用がよいのではないかと思います)。
岸田総理は、「社会全体の構造や意識を変え、『こどもまんなか社会』を実現するため、『こどもファスト・トラック』等の施策を多面的かつ積極的に展開する」とのことですが、子育てしている側からすれば、別に「必要がない場面でまで、子どもを“特別扱い”してくれ」と要求しているわけではないですし、社会で反発を受けては逆効果です。それぞれの年齢や状況に応じたきめ細やかなサポートが大切、ということではないでしょうか。

コンセプトがズレてる
政府は、「こどもファスト・トラックで、待ち時間を短縮し施設を利用しやすくすることで、『こどもや子育て中の方々にやさしい社会』を目指します。」と言っています。
もちろん、「子育てにやさしい社会の実現」は「ぜひお願いしたいこと」なわけですが、子育てのいろいろなことが本当に大変な中で、「これで、そんなに胸を張られても…」というか、ワンオペ育児や、仕事との両立や、成長するにつれて増大する教育費や、高騰する生活費の負担等など、「“やさしくしてほしい”と切望するところ」は、ほかにもたくさんあります。
「こどもファスト・トラック」は「公費がかからず実現できて、政府に労無くして、大きなアピールになるからかな…」と邪推したりします。
昨年6月に連載に書いた「子育て負担を軽減→子どもが増える…政府の方針は“幻想” 『今を生きる人』を幸せにできない国が、少子化対策などできるのか」でも述べた通り、様々な子育てにかかる国民の負担軽減は、決して「子どもを産ませるために」行うべきものではありませんし、「何らかの対策を講じれば、子どもがバンバン増える」という考えは、幻想にすぎません。当事者の真情を理解しない、政府の押し付けがましさや、あるいは選挙対策かのようなおもねる姿勢を、国民はシビアに見ていると思います。
インタビューでは、「早い列に入れるからって子どもを産もうとは思わない」「そこじゃない。教育無償化や医療の負担軽減をしてほしい」という声もありました。
日本は子育てのしにくい国?
「自国は子どもを生み育てやすい国だと思うか」との問いに、スウェーデン97.1%、フランス82.0%、ドイツ77.0%が「そう思う」と回答しているのに対し、日本では「そう思わない」が61.1%となっています(内閣府、2021年3月、20~49歳の男女1372名回答)。
私は、初めての出産・子育てを、赴任中の欧州で行い、あちらの環境が基準になっていました。ですので、帰国した直後の日本の空港で、子どもと荷物を両手に抱えて(ベビーカーは、搭乗前に預けていて、まだ無く)、空港スタッフの方に「優先レーンはどこにありますか?」と聞いたところ、「そんなものはありません。あちらに並んでください」と長い列を指さされ、「そうか、日本はそういう国だったか~」と、ハッとし、その後も随所で、(聞いてはいましたが)「日本は子育てに厳しい国」であることを、実感しました。
「子連れだと肩身が狭い」などの声もあり、「日本社会の意識・雰囲気が子供を生み育てることをためらわせる状況にある」ともされています(「こども未来戦略方針」(2023年6月13日))。
実はこの「社会の意識・雰囲気」というのが、大きなポイントです。

人々や社会の意識や理解が、非常に重要
法律や制度があっても、人々の意識が伴わなければ、実質的な意義は大きく損なわれます。例えば、少し前までの「育休制度はあるけど、取れる雰囲気じゃない」といったことが典型です。
例えば、私が霞が関勤務の若手だった頃は、「育休を取るなんてとんでもない」という雰囲気で、異動先の部局で「保育園に子どもを迎えに行くために早退する職員の方」を初めて見た時には、率直にびっくりしました(そういう時代だったんです…)。
その頃に比べたら、時代は大きく変わり、育休も時短勤務も利用されているようですが、一方で、今も日本では、「職場に子育て中の人がいると、周囲に迷惑がかかる」といった、いわゆる『子持ち様論争』が話題になっています。
これについては、負担の不平等が生じている状況では不満が出るのは当然だとも思いますので、仕事をカバーした方に対して手当を支給する、といった何らからの対応策が求められると思います。また、産休・育休期間だけではなく、子どもが一定の年齢になるまでは、発熱した等の理由で早退や欠席をしなければならない時期がかなり続くことを考えれば、問題はもっと長期的であることにも気付きます。近くに手伝ってくれる親族がいない場合(私もそうでした)には、職場の人に迷惑をかけることはできないし、そもそも休むなんてできない、と必死で、病児保育を利用するなど、本当に「毎日が綱渡り」になります。
一方で、ジュネーブ赴任時代、他国の政府代表部には女性が多く、外交官として仕事をしながら出産している人も多かった(一方、当時の日本政府代表部では、基本的にはダメ)ので、「どうやったらそれが可能になるのか」聞いたところ、「上の世代にとっては『自分がやってきたこと』、下の世代にとっては『これから自分がやること』だと思っているから、当然に協力し合う」、「普段から、属人的ではなく、チームで仕事をしているので、カバーし合える」と言われ、「なるほどなあ」と思いました。
そこにあるのは、法律や制度を超えた、「実際に行われてきた歴史と、そこから生まれる納得感や理解、そして、仕事の仕組みの工夫」でした。
制度や環境が意識を変えるという面もある
「制度や環境を整えることで、理解と機運が醸成される・意識を変えていく」という面もあると思います。欧州での「優先レーン」のような仕組みが、当たり前に社会に普及してくると、「ハンディのある人には、サポートをするのが当然」という意識が浸透し、小さい頃から自然に身に付き、自分もそうしよう、という人生全般における行動にも反映されていっているように見受けられました。
また、ハード面が十分でなくても、それをソフト面がカバーするということもあります。例えば、パリの地下鉄の駅(歴史的に古く、エレベーターがないことが多い)や、バスの乗降の際は、必ず、周囲の方が何人も寄って来て、ベビーカーを運んでくれました。子ども連れや高齢者や障がいのある方に対して配慮をする、ということが、社会全体で極めて自然に行われている印象を受けました。
―――――――――――――――――――――――――
誰もがかつては子どもであり、誰もがいつかは年を取ります。かつて通ってきた道、これから通る道、です。そして、「配慮される側」にも周囲への気遣いや感謝が大切だと思います。
寛容は寛容を生み、不寛容は不寛容を生みます。
―分断ではなく、相互の配慮と社会の理解に変えていくー
そうした観点からも、政府の方針には、もう少し、民意の正確な理解と精緻な検討とをしてほしいと思います。
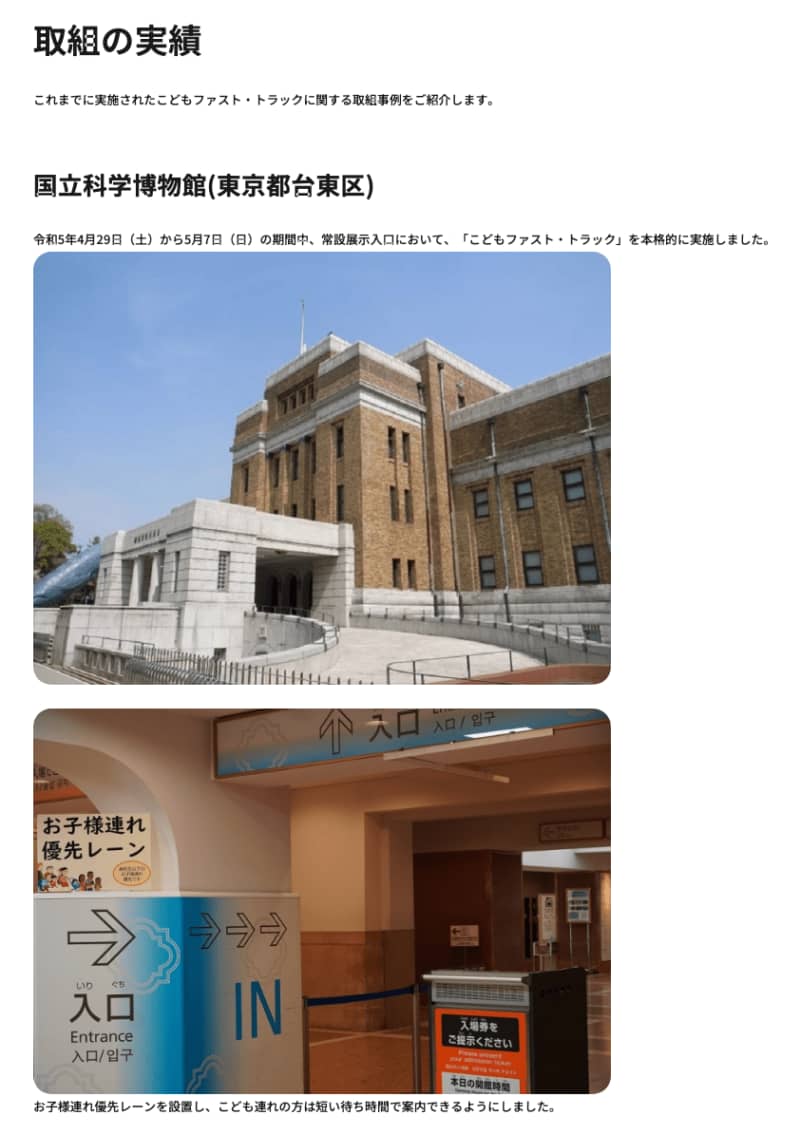
◆豊田 真由子 1974年生まれ、千葉県船橋市出身。東京大学法学部を卒業後、厚生労働省に入省。ハーバード大学大学院へ国費留学、理学修士号(公衆衛生学)を取得。 医療、介護、福祉、保育、戦没者援護等、幅広い政策立案を担当し、金融庁にも出向。2009年、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官として、新型インフルエンザパンデミックにWHOとともに対処した。衆議院議員2期、文部科学大臣政務官、オリンピック・パラリンピック大臣政務官などを務めた。
