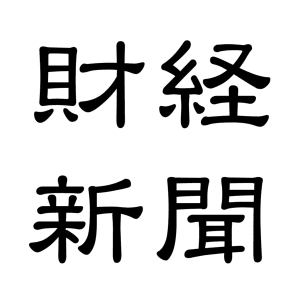●東京海上が政策株式を29年度末までにゼロに 東京海上ホールディングスは20日、非上場株などを除く政策株式を、29年度末までにゼロにすると発表した。
同時に発行済みの株式の3%である6000万株・1000億円を上限とする自己株式の取得を決議した。
これらの動きが好感され、加えて25年3月期の連結純利益が連続最高益との見通しもあり、株価は大幅高となり、上場来高値を更新した。
東京海上の政策株式解消が、マーケット全体にも影響を与えるのだろうか?
●政策株とは?これまでの慣習も 政策株とは、取引先との関係を強化・維持するために保有している株式のことである。長期的に保有することで株価が安定すること、現在のように好調な株式市場であれば売却により、利益計上することができるメリットがある。
一方で、企業の成長性や競争力を阻害しているという批判もあり、資本効率が低下するというデメリットがある。安定株主で固めることに「物言わぬ株主」という批判があった。
戦後、旧財閥系の企業グループが買収対策などで始めたと言われているが、現在までその日本独自の慣習が根強く残っている。
2022年から東証は区分見直しとなったが、流通株式比率にも厳格な数値基準が適用された。
●市場からは好感? 昨年末、企業向け協同保険料調整問題で金融庁から行政処分を受けた東京海上を含む大手損保4社。
この時に政策保有株が適正な競争を歪めたとして、売却の流れが加速していた。
東京海上はこれまで、大手4社の中で唯一ゼロにする計画を発表していなかった。損保各社は政策保有株売却により、過去最高益を更新しており、株価も上昇するなど好感されている。
4月26日には世界の機関投資家が参加するアジア・コーポレートガバナンス協会(AGCA)が日本企業に政策保有株縮減を加速し、ゼロにするよう提言をまとめた。
損保以外にも政策保有株の売却が加速することは間違いなく、その売却益を自社株買いや成長分野への投資に向けるなら、相乗効果でさらに市場からは好感されるだろう。