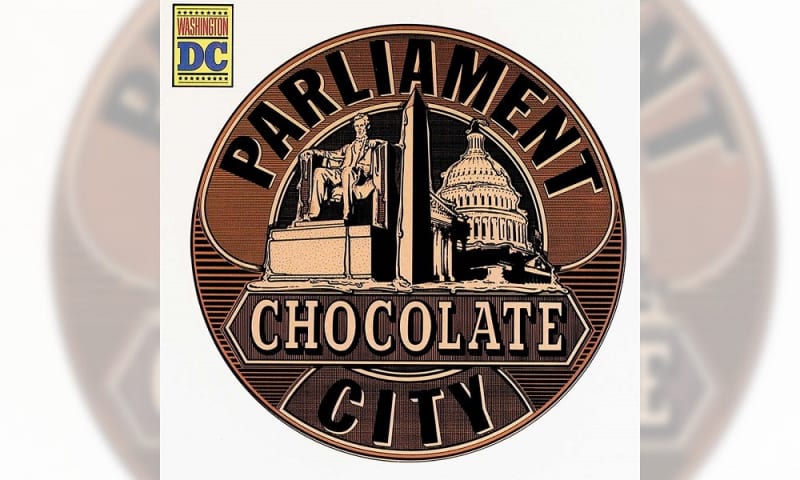
パーラメント(Parliament)のサード・アルバムにして、彼らがカサブランカ・レコードから発表した2作目のアルバムに当たる『Chocolate City』は、ゆっくりとアルバム・チャートを上昇したが、結果的には91位止まりだった。また、このアルバムから生まれた2枚のシングルも、それを超えるような成績を収めることはできなかった。
しかし、ヒット・チャートにおける成績にいったいどんな意味があるというのか?
1975年4月8日にリリースされた『Chocolate City』は紛れもなく名盤である。ファンキーで小生意気な同作には、冷静さと情熱、陽気さと苛立ち、無邪気さと政治性、シンプルさときらびやかさ、攻撃性と朗らかさ、複雑さとファンキーさ、それらすべてが共存しているのである。
このアルバムには、”ファンキーでない世界”の根幹を揺るがす、真にファンキーな生き方が表現されている。この”チョコレート・シティ”とやらに、ぜひとも移り住みたいものだ。
きわめて過激な楽曲
『Chocolate City』はオープニングを飾るタイトル・トラックからアルバムの末尾のフェード・アウトまで、すべてが強烈な印象を残すアルバムである。
より具体的に述べるなら、タイトル・トラック「Chocolate City」はきわめて独創的な構成の楽曲になっている。とりわけめずらしいのは、この曲がドラムやビートに頼ることのないファンク・ナンバーだという点だ。この曲には、1975年当時のアメリカにおける黒人の地下社会の考え方が表れている。ここでパーラメントは、人口に占める黒人の比率が高いワシントンD.C.を、黒人たちの都市だと主張しているのである。しかも、それが選挙日の開票結果によるものだと言わんばかりの口ぶりなのだ。
ニューヨークも俺たちのものになったらしい
We just got New York, I’m told
モハメド・アリがホワイト・ハウスにいても驚くなよ
Don’t be surprised if Muhammad Ali is in the White House
と語り手は言い放つ。しかも、ホワイト・ハウスという名も”ほんの一時的なもの (just a temporary condition) “だと言う。そもそも彼らはその街を”D.C.”ではなく、”C.C. (チョコレート・シティ) “と呼んでいるのだ。
彼らはふざけているわけではない。ふざけたフリをしてはいるものの、彼らはいたって真剣なのだ。とはいえ1975年当時、その思想は非常に過激なものだった。この前年には、ウォーターゲート事件の余波でニクソン大統領が辞任。そのため、アメリカ全体が平穏な日常を取り戻そうともがいている最中だったのだ。しかし、『Chocolate City』では、タイトル・トラックの過激なメッセージを理解しようとしている矢先に「Ride On」が追い討ちをかけてくる。
「Ride On」は、スライ&ザ・ファミリー・ストーンの手法をそのまま応用したようなドラム・マシンのビートが特徴的な1曲になっている。そこではオペラ風ともゴスペル風とも取れる、Pファンクならではの風変わりなバック・ヴォーカルを、重厚なグルーヴが支えている。そんな「Ride On」に込められたメッセージはシンプルだ。つまり、「言葉を濁している暇はない、ダンスフロアで自分自身を解放しよう」ということである。
続く「Together」は、 (疑う人がいればの話だが) パーラメントが本格的なファンクも演奏できることの証左である。いまとなってはそんなことは分かり切った話だが、この当時、ジョージ・クリントン率いるグループは成長の途上にあった。そのため、彼らがどれだけ力強いビートを刻めるか分かっていないリスナーも多かったのである。なお、愛を赤裸々に歌った同曲は、これ以前にブーツィー・コリンズとその兄のフェルプス、ゲイリー・”マッドボーン”・クーパーの3人によってレコーディングされていた1曲である。
奥深いグルーヴと好戦的な姿勢
刺激的かつヘヴィな「Side Effects」は、彼らが1970年代前半にファンカデリック名義で発表した諸作を想起させる1曲である。しかしながら、この曲に施された見事なホーン・アレンジは、その当時であれば敬遠されていたに違いない。
続く「What Comes Funky」は、ドラッグの使用を賛美する内容の1曲だ。パーラメントの面々は、もちろん一貫してドラッグ肯定派だったのである。また「Let Me Be」は、バーニー・ウォーレルによるクラシック風のピアノとシンセをフィーチャーしたナンバー。そのサウンドは、バッハの音楽にこの上なく大胆な電子的アレンジを施したような趣である。同曲は至ってシリアスな曲調のバラードだが、かといって悲惨に思えてしまうほどではない絶妙なバランスの上に成り立っている。
そんな「Let Me Be」から一転、軽快な曲調の「If It Don’t Fit (Don’t Force It) 」は、小気味良いリズムが特徴のアップテンポな名曲。実にパーラメントらしい作風のこのトラックでは、グルーヴが勢い良く刻まれる中、ホーン・セクションがユニゾンで奏でるフレーズがサウンドに華を添えている。
8曲目の「I Misjudged You」は、このグループの前身であるザ・パーラメンツの作風に通じる1曲になっている。ヴォーカル・ハーモニーやストリングの音色により、1960年代の上品なソウル・バラードさながらの華やかな楽曲に仕上げられているのである。
成就しなかった恋を歌った同曲はごく真面目な楽曲とも取れるが、重厚なソウル・サウンドに仕上げられていなければ、あるいはフランク・ザッパや初期10ccの作品の模倣と評価されていたかもしれない。そう、彼らはこんな楽曲も作り上げることができるのだ。
そして『Chocolate City』は、グレン・ゴインズが初めてリード・ヴォーカルをとった1曲で幕を降ろす。驚くほどパワフルなシンガーである彼はこのあと2年に亘ってPファンクの世界で活躍したが、そののちにガンでこの世を去ってしまった。
その「Big Footin’」では、”the one” (ファンクのリズムの基本である、各小節の一拍目のこと) がたどたどしくも力強く演奏されている。そのビートはまるで、雪男がダンスフロアで踊っているかのようだ。
アルバムの主役とは?
さて、このアルバムの主役は一体誰だろう?彼らはきっと、グループ全員が力を発揮したと言うはずだ。だが、『Chocolate City』のサウンドを牽引しているのは、縦横無尽に動き回るベースを得意とするブーツィー、音楽理論に精通したウォーレル、グループの生みの親であるジョージ・クリントンの3人である。パーラメントは彼らを中心として70年代中盤に、大ヒットを連発する大物グループへと成長していったのである。
確かに面白半分でふざけている箇所もあるが、このアルバムには彼らの内なる野心が表れている。当時の彼らは、ファンク界のモンスター・バンドとしての本来の実力を世間に認められたいと強く感じていたのだ。同作でのホーン隊の演奏やヴォーカル・ハーモニーは申し分なく、グルーヴも奥深い。そして、このアルバムにおける彼らの姿勢は好戦的で皮肉っぽく、同時に辛辣でありながらも誠実である。
『Chocolate City』はその後のパーラメント作品の基礎となったアルバムであり、現在もファンク界における名作の一つとして愛されている。このアルバムは”ほんの一時的なもの”などではなかったのである。
Written By Ian McCann
