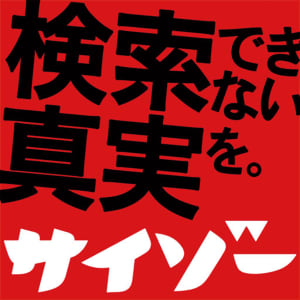──歴史エッセイスト・堀江宏樹が国民的番組・NHK「大河ドラマ」(など)に登場した人や事件をテーマに、ドラマと史実の交差点を探るべく自由勝手に考察していく! 前回はコチラ
『光る君へ』、前回(第20回)の「望みの先に」は複雑な人間関係や、当時の習俗を巧みに整理して詰め込んだ意欲的な内容でしたね。一方、筆者の周辺では「大ネタ回だったのでは……」という声もあり、確かに歴史的知識がなければ、そう見えてしまう可能性もあると感じましたので、今回はドラマに描かれた「長徳の変」とその後始末を巡るあれこれをお話させていただきます。
「長徳の変」とは、長徳2年(996年)1月16日の夜、前太政大臣の故・藤原為光(阪田マサノブさん)の邸宅において、鉢合わせしてしまった花山院(本郷奏多さん)と、藤原伊周・隆家兄弟(三浦翔平さん・竜星涼さん)の間で発生した乱闘事件のことです。伊周は、為光の三女(氏名不詳。寝殿の上)と関係していたのですが、彼は三女を(出家後も色好みで知られた)花山院に寝取られたと勘違いし、牛車に乗り込もうとする花山院に矢を射掛けるという蛮行をしでかしてしまいました。
しかし、花山院の本当の恋人は、為光の四女・儼子で、すべては伊周・隆家の盛大な勘違いだったのです(ちなみにこの二人の女性は、花山院がかつて愛した忯子の異母妹です)。ドラマでは射撃を受けた院自身は矢で脅される程度で済みましたが、史実では袖に矢が突き刺さったとされています。ただドラマでも描かれた通り、院の従者二名が伊周の従者に殺され、犠牲者の生首が持ち去られるなど凄惨な結末になってしまいました。
当初、この事件は花山院の意向で、内々にされ、沈静化するはずだったようです。花山院はすでに髪をおろした出家者です。出家後でも色恋の誘惑に負けているのは当時、もっとも恥ずべき行為でしたので、スキャンダルを恐れた院は被害者であるにもかかわらず、周囲に箝口令を敷き、事件をなかったことにしようとしていたのですね。
しかし、この事件について藤原為光の息子・斉信(金田哲さん)からの情報提供を受けた道長(柄本佑さん)が、平安京における警察組織に相当する検非違使(けびいし)の長官・藤原実資(秋山竜次さん)に情報を流したので、花山院の隠蔽の意向もむなしく、事件は世間に明らかになってしまいました。
斉信から道長への情報提供は、「長徳の変」勃発以前から行われていたと考えられます。斉信は長い間、伊周・隆家兄弟の父(で、道長の長兄)の藤原道隆(井浦新さん)の派閥の人物でしたが、道隆が糖尿病で早逝し、伊周・隆家兄弟に人望がないことから、権勢を振るう道長の派閥に鞍替えしようとしていたのでしょう。
その際、道長から斉信の本気度を試すために、彼が仕えていた伊周・隆家兄弟のことを調査・密告せよと迫られ、斉信は拒めなかったのではないかと想像されます。もちろん、斉信は被害者である花山院から口止めを頼まれていたでしょうから、伊周・隆家兄弟だけでなく、院のことも裏切ったことになります。しかし、そこまで多くの恨みを買ってでも、少しでも自分が有利に生き残るため、斉信は道長側に付こうと考えたわけですね。
道長は、伊周・隆家兄弟には花山院襲撃事件に加え、数々の冤罪をなすりつけました。史実では、その冤罪で確実に彼らを失脚させるつもりだったのでしょう。ドラマでも彼らの母親である高階貴子(板谷由夏さん)のセリフで「祈祷を行わせた」というものがありましたが、あれも道長の手で大問題にでっちあげられてしまっています。
道長の「告発」によると、伊周・隆家兄弟は、天皇の命でしか行ってはいけない「大元帥法(だいげんすいほう)」という祈祷を行わせていたそうです。そういう虚構の「罪」に対する「罰」として彼は大宰権帥(だざいごんのそち)、弟・隆家は出雲権守に降格され、左遷=流罪が決定しました。ドラマでは死刑から罪を一等だけ軽くしたという描かれ方でしたが、当時は死刑が名目上廃止されており、流罪はそれに次ぐ大罪ということになります。
さらに伊周・隆家兄弟には、体調不良に悩んでいた道長の姉・藤原詮子(東三条院・吉田羊さん)を呪詛したという罪まで道長の手でなすりつけられていたのです。ドラマでも道長の正室・源倫子(黒木華さん)が、「悪しき気を感じる!」といって詮子の周辺を調査させたところ、陰陽師が関与したと思しき、あやしげな御札が貼られた壺などが見つかったりしていましたね。
当時の陰陽道でいう「式神」とは、まさにああいう壺のようなものにすぎず、現代のファンタジーに出てくるような妖怪変化を自在に使役するものではありませんでした。式神とは、呪いを発生させるための装置――現代風にいうと、ターゲットの身辺にポケットWiFiみたいな装置を配置し、そこから呪いの怪電波を照射して弱らせるという構図を想像してもらったほうが理解しやすいかもしれません。
ドラマの壺の「モデル」としては、晩年の道長がとある陰陽師の手で呪詛され、その式神を安倍晴明(ドラマではユースケ・サンタマリアさん)が見事に発見するという経緯が、鎌倉時代前期に成立した『宇治拾遺物語』に見られます。この書物に式神として紹介されているのは、2つの土器を重ね、その内部に「呪」と書いた黄色い紙をひねったものを入れただけの代物でした。まぁ、安倍晴明などの平安時代の陰陽師が、実際にどんな式神を使っていたかについては、完全に門外不出の秘伝で、本当のところはよくわかりませんが……。
ドラマの伊周は道長を訪ね、呪詛などはしていないと泣きながら訴えていました。また、史実でも伊周は大宰権帥への左遷人事をなかなか認めようとせず、逃げ回っていたことが知られますが、それは花山院襲撃事件はともかく、呪詛事件などは完全な冤罪であるという抵抗でもあったのでしょう。
当初は弟の隆家も兄同様、何者かによって(通説では道長によって)捏造された「罪」を否定し、一条天皇の中宮・定子(高畑充希さん)の屋敷にこもっていましたが、兄よりも早期に「罪」を認め、京都を出ています。しかし、彼は出雲権守に左遷されていたにもかかわらず、出雲(現在の島根県)には行かず、病気を理由に但馬国(現在の兵庫県北部)に滞在しつづけました。これも一種の抵抗だったと考えてよいでしょう。
結局、史実の伊周も逃げ惑うのに疲れ、検非違使のもとに出頭し、太宰府(現在の福岡県)に流されることになりました。しかし、伊周・隆家兄弟は「長徳の変」の早くも翌年、つまり長徳3年には罪を許され、京都に帰ることができました。この背景にあったのも、やはり藤原詮子の体調不良でした。史実の彼女は弟・道長がでっち上げの罪で苦しめた相手を「恩赦」することで、なんとか病からの回復を願ったらしいのです。この時、隆家や、その父・道隆の「霊」に詮子や道長が悩まされていたという記述が史料に見られ(『権記』)、非常に面白いのですが、ドラマでも描かれるかもしれませんので、これについてはまた後日……。
兄・伊周が無様に逃げ惑う中、屋敷に踏み込んできた検非違使たちを前に定子が小刀を振りかざし、喉を突く付くのかと思いきや、黒髪が束になって廊下に落ちたシーンについても最後に補足しておきますね。
史実でも定子は、不甲斐ない兄たち二人を匿ってしまった自分の罪の責任を取るべく、そして兄たちの罪を軽くしてもらえるよう、ドラマで描かれたように髪の毛を一部切り取って出家の意思を示したそうです(『小右記』)。
しかし、事実上は出家した身にもかかわらず、定子は一条天皇の後宮に戻り、猛批判を受ける中で天皇からふたたび寵愛され、複数の御子を設けることになりました。花山院のケースもそうでしたが、出家者の色恋は当時のルールでは大スキャンダルでしたから、そのあたりに道長が付け込み、愛娘・彰子を入内させ、定子から一条天皇の寵愛を奪いとる余地があったのでしょうね。盛り上がってきた『光る君へ』、今後が楽しみです。
<過去記事はコチラ>