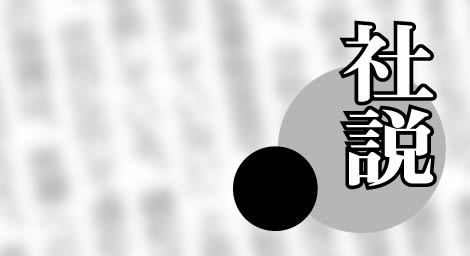JR西日本が、利用の低迷する木次線の出雲横田(島根県奥出雲町)―備後落合(広島県庄原市)間の在り方について、沿線自治体に相談する方針を明らかにした。
沿線の庄原市や奥出雲町、そして広島、島根両県は「廃止が前提なら応じられない」と警戒を強めている。JR西が「特定の前提は置かない」とした説明を、言葉通りには受け取っていない。
確かに、なぜ今なのかという違和感は拭えない。木次線と接続する芸備線の備後庄原(庄原市)―備中神代(岡山県新見市)間の存廃を3年以内で話し合う再構築協議会が、3月に始まったばかりだからだ。議論が深まる前に、JR側が木次線にまで言及したのは、同時並行での話し合いを望んでいるようにも受け取れる。さすがに拙速ではないか。
2003年に可部線の大部分、18年に三江線が廃線になった。木次線の行方も危ぶむ声はかねてある。人気だった観光トロッコ列車「奥出雲おろち号」が昨年11月で運行を終えて出雲横田―備後落合間に乗り入れられない列車が後継となったことも、地元の不安を招いていよう。
とりわけ庄原市は木次線と芸備線が走る。二つの区間が仮に廃止になれば、市民生活やまちづくりに多大な影響が出るのは避けられない。木山耕三市長がJR側の新たな動きに「到底理解しがたい」と反発したのも無理はない。
出雲横田―備後落合間は、29・6キロに6駅がある。1キロ当たりで1日に運ぶ乗客数を示す輸送密度は2022年度、54人にとどまった。管内の区間では2番目に少ない。JR西は「相談」の理由として通勤や通学などの生活利用に乏しい点を挙げた。
ただ三江線が廃止されて以降は、広島と島根の陰陽を直結する唯一の鉄道路線となっていることを忘れてはならない。そもそも鉄道はネットワークが保たれてこそ強みを発揮するインフラだろう。緊急事態に高速道路が寸断された場合、輸送に果たせる役割はまだまだあるはずだ。
観光資源として生かす道も大切だ。木次線には列車の進行方向を切り替えて傾斜地を進む「3段スイッチバック」がある。沿線には松本清張の小説「砂の器」と映画化作品で知られる亀嵩(かめだけ)もある。地方の魅力に目を向けるインバウンド(訪日客)を含め、観光戦略の面でも鉄路の価値をもう一度、捉え直すべきだ。
木次線を巡るJR西の方針を受け、広島県の湯崎英彦知事は「国において全国的な鉄道ネットワークの方向性を早期に整理してほしい」と注文した。その通りである。
再構築協の枠組みでは、国の関与が強まった。政府として赤字ローカル線とどう向き合い、利活用にどんな青写真を描くのか。大局的な方針が今こそ必要だろう。それがないままなら芸備、木次線に限らず、同じ悩みを抱える各地の沿線住民の不安と向き合うことにはならない。