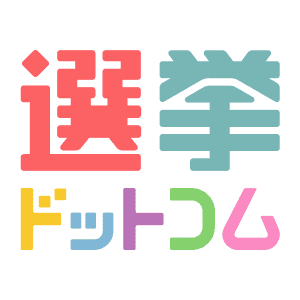選挙ドットコムが公式メディアパートナーを務めた「日本GRサミット2024」が4月13日(土)に開催されました。
今回はイベント当日のレポートと、イベントを主催した一般社団法人日本GR協会(以下、日本GR協会)の代表理事・吉田雄人さんのインタビューをお届けします。
150名のGRパーソンが集結した「日本GRサミット2024」
日本GRサミット2024は4月13日(土)にPOTLUCK YAESU(東京都千代田区)にて開催。総勢20名の日本を代表する官民のルールメーカーが集結し、「地域から変える社会、ルールメーカーが見据える未来」をテーマに語り合いました。来場者数はおよそ150人。全国から、民間企業、NPO、公務員や学生など様々なジャンルの方々が集まりました。
ところで、そもそも「GR」とは何か。日本GR協会は「GR」を下記のように定義しています。
GRは「ガバメント・リレーションズ」の略で、直訳すると「政府との関係構築」となります。GR協会は「社会課題解決のための、政治行政との関係構築の手法」と定義しています。
政策や法律・条令は、かつては政治家と官僚/公務員だけでつくるものと思われてきましたが、テクノロジーの発展により、民間が大きく関わってくるようになってきています。
そこで日本GR協会は、ルールメーカーとして注目される官民のリーダー達に呼びかけ、官民連携による政策づくりや法整備のあるべき姿を議論し発信する場が必要だと考え、日本GRサミットの開催を企画するに至りました。
現職首長や「日本のルールメーカー」ら20人が登壇
今回の日本GRサミット2024は5つのテーマでセッションが行われ、現職の首長やForbes JAPANが発表した「日本のルールメーカー」ら20名が登壇しました。
・メインセッション「政治行政だけでは社会課題の解決はできない時代がやってきた」
登壇者:熊谷俊人氏(千葉県知事)、鈴木周也氏(行方市長・全国青年市長会 会長)、山梨崇仁氏(葉山町長・全国若手町村長会 会長)、吉田雄人氏(日本GR協会 代表理事、元・横須賀市長)

・セッションA「パブリックアフェアーズが企業に標準装備されるためには?」
登壇者:藤井宏一郎氏(マカイラ 代表取締役CEO)、宮田洋輔氏(株式会社ポリフレクト代表取締役社長・プロトタイプ政策研究所有識者メンバー)、吉川徳明氏(株式会社メルカリ 執行役員 VP of Public Policy 兼 Public Relations)、朝比奈一郎氏(青山社中株式会社 筆頭代表 CEO・福井県立大学 客員教授)

・セッションB「ソーシャルセクターが担う公共サービスの作り方」
登壇者:伊藤和真氏(株式会社PoliPoli 代表取締役/CEO)、陶山祐司氏(株式会社Zebras and Company共同創業者)、廣田達宣氏(株式会社issues 代表取締役・官僚の働き方改革を求める国民の会 代表)、佐藤大吾氏(NPO法人ドットジェイピー理事長・(公財)日本非営利組織評価センター理事長)

・セッションC「ルール・メイキングの現在地 〜法令との新たな向き合い方〜」
登壇者:落合孝文氏(渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 シニアパートナー 弁護士・スマートガバナンス株式会社 代表取締役 共同創業者)、杉原佳尭氏(Netflix ディレクター/公共政策担当)、水野祐氏(シティライツ法律事務所 弁護士・九州大学GIC客員教授)、小木曽稔氏(株式会社政策渉外ドゥタンク・クロスボーダー代表取締役)

・セッションD「行政と民間を「つなげる」にあたって求められるお作法とは?」
登壇者:栫井誠一郎氏(株式会社Publink 代表取締役社長 CEO)、駒崎弘樹氏(認定NPO法人フローレンス 会長)、藤沢烈氏(一般社団法人RCF 代表理事)、関口宏聡氏(NPO法人セイエン 代表理事)

イベントが開始された午後から、日が落ちてイベントが終了するまでの5時間以上の間、ほとんどの参加者が最後まで登壇者の話に耳を傾けていました。休憩時間の限られた時間内での名刺交換も積極的で、多くの有益なネットワーキングに繋がっていた様子。熱心な参加者の意欲、オフラインならではのイベントの熱量からGR分野への期待の大きさを感じることができました。
首長を経験した自分だからこそ・・・

イベントを主催した日本GR協会・代表理事の吉田雄人さんはインタビューで次のように語ります。
編集部:
官民連携の必要性が高まった背景は何ですか?
吉田雄人氏(以下、吉田氏):2011年に日本は人口減少社会に突入し、時を同じくして東日本大震災が発生しました。この時を境目に、多くの現代的な課題が顕在化してきています。それらの課題は、財源不足・人材不足・ノウハウ不足の三重苦によって行政だけに解決を依存することができない状況です。
一方、テクノロジーの発展を背景に、民間のサービスやソリューション、プロダクトの中には、それらの地域課題の解決に資するものが湧き出してきています。民間にとっては、これらの課題解決にあたることが、そのままビジネスやシーズに育つこともわかってきました。
そうした背景から官民連携の必要性が高まってきました。
編集部:そうした背景があるにも関わらず行政と民間の連携がうまく進んでいるとは、まだ感じられません。なぜでしょうか?
吉田氏:
それは両者の間にある違い(時間の流れ方、言葉の使い方、仕事の向き合い方など)が、高い壁となって立ちはだかるからです。
そうした壁を越えるために「社会課題解決のための政治行政との関係構築の手法(GR:ガバメント・リレーションズ、Government Relations)」の必要性が高まってきました。日本GR協会では、GRの必要性を「広めること」、GRの成功事例や失敗事例を「学べること」、GRプレイヤー同士がセクターを超えて「繋がれること」を目的に活動を展開しています。
編集部:吉田さんは横須賀市長を経て、今は民間で事業を運営していらっしゃいます。政治家から民間に転身するにあたって苦労したことはありますか?
吉田氏:行政の年度単位の仕事の進め方に慣れてしまっていたので、民間企業、特にスタートアップ界隈の、変化に柔軟に対応する意思決定とスピード感についていくのが、最初は大変でした。
編集部:ありがとうございます。反対に強みは何でしょうか。
吉田氏:私はもともと民間企業に勤めていました。市長になる前は、ニュースや新聞を見ていて「どうして課題解決に向けて、物事が進まないんだろう」と感じていました。これは、皆さんも同じことを感じていると思います。
その後、自ら現場に飛び込んで社会の問題を解決したいと、議員を務め、市長に就任するわけですが、行政の立場になって初めて「行政と民間は全く違う世界」ということが分かりました。具体的には先述の”時間の流れ方”などのほかに、政治の生々しさ、意思決定プロセスの独特さなどが挙げられます。
ゆえに、民間から市長を経験した者の強みは、民間と行政の間に入って両者の橋渡し役や翻訳者を務められることですね。
編集部:最後に、熱を帯びる「GR」の展望を教えてください。
吉田氏:
今回のGRサミット2024は、コロナ禍を経て4年ぶりの対面イベントだったということもあり「来場者はちゃんと来てくれるだろうか」「イベントの雰囲気は大丈夫だろうか」など、不安な気持ちでいっぱいでした。
しかし、素晴らしい登壇者の皆様やGRオフィサー(日本GR協会のプロボノスタッフの総称)のおかげで滞りなくイベントが進み、来場者のほとんどが最後まで残って熱心にセッションに参加してくれました。そうした姿から「GR業界は可能性しかないな」と強く感じています。
業界には少しずつですがプレイヤーが増えてきていますので、日本GR協会がプレイヤー同志を繋げて、日本に山積する社会課題を1秒でも早く、そして1つずつ着実に解決できるように努めていきたいです。ぜひ、今後も応援していただけると嬉しいです!