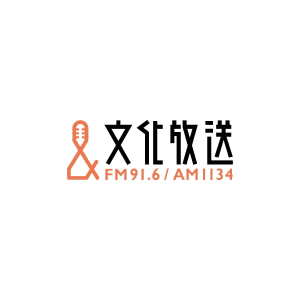ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティーを務める「長野智子アップデート」(文化放送・月曜日~金曜日15時30分~17時)、5月27日の放送では「アイスランドから読み解くジェンダー平等社会へのヒント」と題し、14年連続で世界経済フォーラム発表のジェンダー・ギャップ指数(男女格差が少ない国)で1位となっているアイスランドに着目。先週まで現地で取材をしていたジャーナリストの浜田敬子に実情を聞いた。
長野智子「ジェンダーの問題を人権としてきちんと取り上げて、世界全体のジェンダー・ギャップ指数1位をとる。どうやってアイスランドはそうできたの……」
浜田敬子「と思った(から取材した)んですよ。有名なのは1975年10月24日に『女性の休日』という、国の人口の4分の1ぐらいが参加する、女性のストライキがあったんです。その日は仕事を離脱する、主婦なら家事をしない。それによってこの国の暮らしや経済をどれだけ女性が抱えているか、というのを知らしめたんですね。女性の賃金が当時、男性の60%ぐらいだった。それに対し、女性が怒りの声を上げて。それがずっと続いています」
長野「はあ~……!」
浜田「男女の賃金格差、アイスランドはまだ12%ぐらいあるそうです、日本だともっと大きいんですけど。12%あるからといって去年も10月24日に10万人の女性のデモをしているんですよ。人口40万弱の国で10万。レイキャビク市の中心街を女性たちが埋める、みたいな」
長野「首都が!」
浜田「そうして女性が声を上げ続けているんです。それがすごく大きいと思っていて。立場を超えて、働いているか働いていないかを別として、やっぱり男性より賃金安いよね、とかケア労働みたいな低賃金のところに女性がついている、ということにおかしいよね、と。女性たちが団結して声を上げている、というのがいちばんの基本なのかなと。それによって社会が変わってきている
長野「これって最初は、まとめあげる一人がいた?」
浜田「その中心人物が、世界で初の女性で(民選の)国家元首になった人なんです」
長野「最初にストライキをしよう、と言ったときは政治家ではなかった?」
浜田「なかったんです。声を上げ続けた人が女性の政治家になり、そういう人たちが声を上げ続けることで同一労働同一賃金法、というかなり厳しい法律もできて。それを達成していないと罰金とか、そういうことになっている。それによって賃金格差も埋まってくる。あと長野さんが一生懸命に伝えているクオータ制というのが2008年に入って。それによって女性議員が増え、女性や子供に対する政策の優先度が上がる。レイキャビク市議会は5割以上が女性です」
長野「すごい。もはや男性よりも多いと。具体的にこういうことがよくなった、こういう動きがあった、というのは?」
浜田「やはり女性に関する法律が優先的に議論されるようになった、というのは言われています。同一労働同一賃金法なんかも、『カトリンさん。カトリンさん』と皆さん親しげに読んでいますけど、カトリンさんが首相時代にいちばん力を入れていた政策なんですね。やはり当事者が政治の現場に入る、ということが女性政策を前に進めるために大きい、ということは痛感しました」