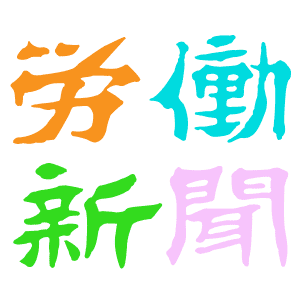今年も全国安全週間準備期間が6月1~30日、本週間が7月1~7日に行われる。年度末で何かと慌ただしい3月、新たに就任した職長に対する講習、労働災害を起こしやすい新入社員の教育を経て、管理体制も整い、ようやく年間の取組みの佳境となるのが6月ではなかろうか。年の半ばに位置する6、7月は全国安全週間にかかる。この機会に事業場の施策について、分析・検証のための中間チェックを行うとよいだろう。
全国安全週間というと毎年、安全衛生担当者は大会の開催に奔走することになる。安全に貢献した者への表彰の実施や飽きさせない講演・講話にしようと知恵を絞ったりとなかなか神経を使う仕事だ。大会は働く人の安全意識向上や今後の活動に弾みをつける起爆剤として欠かせない施策なのは間違いない。
その一方で安全週間には準備期間があり、しかも1カ月とそれなりに長い期間が設定されている。このタイミングを好機と捉え、大会の準備を進める傍ら、これまで行ってきた取組みが盤石になるよう望むところだ。
職場の実情を見直すための着眼点として、本誌姉妹誌「第一線監督者のための職長ノート(2024年3月号)」では、安全衛生活動の基本要件を挙げているので、いくつか紹介したい。まず災害防止は全員参加でなければならないという。一部の作業者だけが孤軍奮闘するのではなく、事業場のトップを先頭に、各人が役割を認識して危険の芽を摘まなければ無災害は難しいとしている。
活動にマンネリの兆候はないだろうか。危険を見過ごしても、何事も起こらなかった場合、安全が保持されたと判断する心理となる。これがエスカレートすると気が緩み、安全軽視へとつながる。4S、KYなど習慣化されている活動に、慣れや気の緩みがないか注意を傾ける必要がある。
長期的な展望と方向性が周知されているか確認も求めている。目的を持たない活動は動機付けが曖昧になり、行動意欲が湧いてこないとした。
全国安全週間は上半期を振り返り、修正と改善を重ねたい。活動のブラッシュアップを図る位置付けとして捉えるのもよいのでは。