
田中泯はダンサーである。その踊りは70年代より国際的に高い評価を受け、今なお世界各国からオファーが絶えない。また、田中泯は俳優である。映画『PERFECT DAYS』では踊るホームレスを演じ、カンヌ映画祭のレッドカーペットの上を歩いた。そして、田中泯は農業者である。山梨県に拠点を構え、泥だらけになって畑仕事に汗を流す。それら以外に執筆活動も行い、2024年3月にはエッセイ集『ミニシミテ』(講談社)を上梓した。そんな、アクティブに躍動を続ける79歳の「THE CHANGE」とはーー。【第1回/全4回】
田中泯は、1945年3月10日、東京の八王子で生まれた。その日、東京の空には焼夷弾の雨が振り、大勢の人たちの命が失われた。
田中「僕は東京大空襲の日に生まれました。もちろん、その日のことは何も覚えていませんが、いろいろなことを聞かされて育ってきました。そのお陰で小さな頃からずっと、“世界”というものに興味を持ち、いろいろなことを考えるようになりました。そのことは、自分の人生に大きく影響していると思います」
田中の幼き日の記憶のなかに、復興していく東京の姿が残っている。
田中「八王子の闇市の風景とか、進駐軍のMPが歩いている姿とか、そうした記憶はあります。僕が生まれて初めて生で見たバンドというのは、アメリカ空軍のブラスバンドでした。『カッコいいなあ』と思いましたよ。それから、『Far East Network(FEN=在日米軍向けラジオ放送)』で、向こうの音楽を聴いていましたね。特にアメリカ志向が強かったわけじゃないけど、そうしたものに刺激は受けました」
やがて、欧米のダンスを目にする機会も増えていった。
田中「高校1年生の時に観た、映画の『ウエスト・サイド物語』はすごく驚きましたね。“は~こういう踊りがあるんだ”と。映画を観た当時は想像もしませんでしたが、のちにアメリカに行くようになった時に、『ウエスト・サイド物語』の振付師であるジェローム・ロビンスに会うことができたんですよ。パリで成功した僕の踊りの噂を聞きつけ、同じ年のNY公演をさっそく見に来てくれたんです。“アメリカはすごい国だなぁ……”と思ったとともに、そういう素晴らしいアメリカもあることを知り、それはとても嬉しかったですね」
ただし、ミュージカル映画が踊りを始めるきっかけになったわけではない。田中が踊りの世界に本格的に足を踏み入れるのは意外に遅い。
田中のエッセイ『ミニシミテ』(講談社)の第一章の始まりにこんな文章がある。
〈二十代前半、オドリに望みを託し、定職も求めず、アルバイトをしながら生きていくギリギリの暮らしを受け入れた時代がある〉
“憧れた”“夢見た”ではなく、“望みを託した”というのは独特のニュアンスだ。
田中「子どもの頃に踊りを少しやっていましたが、その後は中学、高校とバスケットボールに熱中していました。大学に入っても続けていましたが、大学のバスケットボール部は完全に実力主義の世界です。上には上がいるということを思い知らされて、僕は挫折するんですね。“踊りをきちんと習ってみよう”と考えたのはそんなときです。踊りというのは何もいらない。ボールもシューズもなくていい。身体だけあれば表現できる。そこに希望を感じたんですね」
バスケットボールをやめた田中は、ひ弱だった子ども時代に培われた感性に導かれ、踊りを本格的に習い始めるとともに、新たに取り組んだことがあった。
田中「地球上に言葉が生まれる以前から、人は踊っていたはずなんです。踊りが始まった頃はどんなものだったか? 踊りというのは、一体どういったプロセスを踏んでここまで来たのか? それが一番の関心事でしたね。だから、そうしたことを徹底的に勉強していきました」
身体で踊りを覚えるとともに、文献を漁り、踊りに対する理解を深めたのだ。
満を持してパリへ「チャンスが沸き起こった」
田中「踊りというのは、芸術的な舞踊以外にも、ありとあらゆるところにありますね。戦後の日本では、大人はなにかあるとすぐに宴会を開いて踊った。あるいは、結婚した女性たちは婦人会を作って、そこから盆踊りが広まっていった。それに、世の中には流行の踊りがありますよね。僕が若い頃なら、ディスコダンスとかゴーゴーダンスとか そんなものが流行っていました。
そのようなことを20代の半ばまで夢中で調べていました。踊りというのは間口が広い。人類学、民族学、哲学、そういうものを含んでいます。当時の僕は踊りを夢中で勉強し、身体を使って自分なり踊りを探ることで、何かに、どこかに近づけるんじゃないかという気持ちがありました」
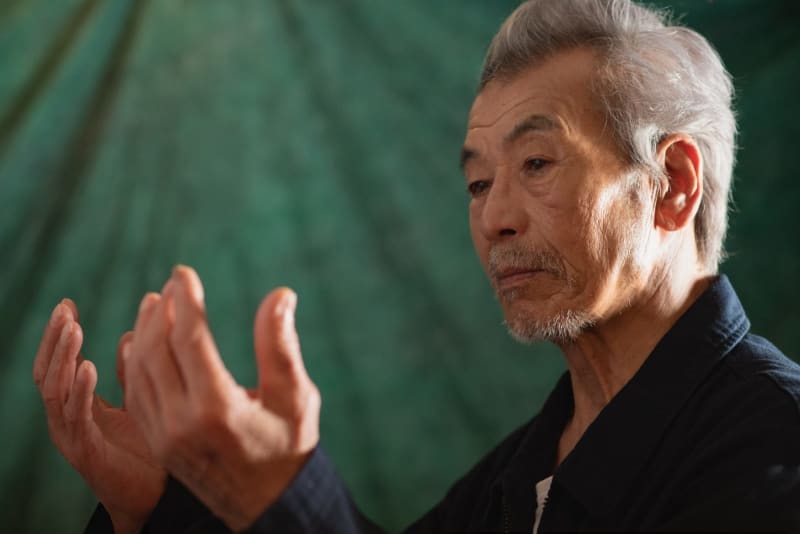
クラシックバレエとモダンダンスなどを10年ほど学び、舞台にも出演を果たしていた田中は、1974年に独自の活動を開始、「ハイパーダンス」と呼ばれる独特のスタイルを作り出していく。ひとつの大きな転機となったのは、海の向こうに活動のフィールドを広げたことだ。最初の行き先は“花の都”パリだった。
田中「僕は予感として“そのうち海外に行くだろうな”とは思っていました。実際にパリに行く前にも、何度か『来ないか』と声がかかったことはあったんです。ただ、それらは自分のお金で行かなければならなかったし、直感的に“これは行かないほうがいいな”と思って断っていたんですね」
慎重に機会をうかがっていた田中がパリに行ったのは1978年のことだ。その頃の田中は、ほぼ全裸に近い状態でのパフォーマンスが話題になっていた。
田中「現在も継続しているパリで最大の芸術祭である『パリ秋芸術祭』(パリ・フェスティバル・ドートンヌ=Festival d’Automne a Paris ※正しい表記は「a」にアクサン・グラーヴつき)。建築家の磯崎新さんと音楽家の武満徹さんが総合プロデューサーとなり手掛けた『間-日本の時空間 展』という、日本文化を中心にした、いまだに語り草になっている展覧会が1978年に起こりました。そのパフォーマンスの部門に僕が選ばれたんです。
ご存知かと思いますけど、当時の僕は裸体のダンサーですから、すでに何度も警察のご厄介になっていたんです(笑)。その僕を磯崎さんや、武満さんが推薦してくれたんですよ。これは本当にラッキーでした。あのときの感覚は“チャンスが沸き起こった”というニュアンスが正しいですね」
パリでの踊りが評判を呼びNYへ、翌年にはオランダ・アムステルダム市立美術館、1980年にはフランス・アヴィニョン演劇祭、イタリアのローマ・カラカラ浴場と、あげるとキリがないほど、各地で独舞を披露するに至る。日本という国で生まれた表現者が、諸外国で受け入れられたのだ。
田中「当時は1ドルが200円くらいでしたから、経済的には大変な面があったかもしれません。しかし、表現の部分では特に自分にハンディキャップがあるとは感じなかったんです。踊りそのものの間口は広いに決まっている。先程も言ったように、言葉より前に生まれたものですから。そういう意味での間口の広さを自覚していれば、どこの国でも特別なものにはならないんです。でも、『これが私の表現だ』と、自分の所有物のように考えてしまうと間口の広さがわからなくなる。1人の人間の間口なんてそんなに広いものじゃないですから」
現在はまた円安となり、日本から海外に行く人の経済的な障壁になっている。しかし、田中の俳優デビュー作となった映画『たそがれ清兵衛』で共演した俳優・真田広之をはじめ、様々なジャンルで日本から海外に出て活動する表現者は増えている。
田中「それは当然のことだと思いますね。しかし、ハンディキャップとまでは言いませんが、島国である日本で育った感覚は、簡単に拭えないですよね。島が連なった国の人々の平均的な性格のようなものが我々にはある。そこが、ひとつの課題になることはあるように思えます」
海外に活動範囲を広げて約45年。80歳を前にして、田中は今も世界各国で踊り続けている。
田中 泯(たなかみん)
1945年3月10日生まれ。クラシックバレエとモダンダンスの訓練を経て、1974年「ハイパーダンス」と名付けた独自のダンス活動を開始する。1978年には、パリ・ルーブル美術館で1か月間のパフォーマンスを行い、海外デビューを果たした。1985年、山梨県の山村へ移住。農業を礎としながら、国内外でのダンス公演は現在までに3000回を超える。一方、俳優としても活動し、デビュー作となった2002年公開の映画『たそがれ清兵衛』では、初映画出演ながら複数の賞を受賞。その後、多くの話題作に出演している。2022年には、その生き様を追った、ダンサー田中泯の本格的ドキュメンタリー映画『名付けようのない踊り』は釜山国際映画祭にノミネートされた。2024年4月からは、新田真剣佑と親子を演じた「Disney+」の配信ドラマ『フクロウと呼ばれた男』が公開。2024年3月にはエッセイ集『ミニシミテ』を講談社から出版した。
