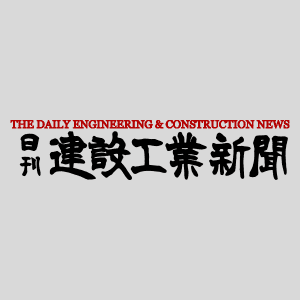国土交通省の有識者会議は28日、河川の地下空間を活用した水害対策の提言案をまとめた。気候変動による降雨量の増加で、集中豪雨や大型台風による水害が頻発している。川沿いに市街地が広がる都市部では河道の拡幅が難しく、従来の対策手法だけでは限界を迎えつつある。活用事例が少ない地下空間に着目し、安全な施工や技術者の確保に向けて取り組むべき施策の方向性を示した。
同日に「浸水被害軽減に向けた地下空間活用勉強会」(座長・鼎信次郎東京工業大学環境・社会理工学院教授)の最終会合を東京都内で開き、提言案を報告した。「地下河川」など河川の地下空間を活用した治水対策の重要性を示し、必要な施策をまとめた。
河川地下空間での工事は、高水敷などの管理施設にダメージを与えないよう、安全性の確保が求められる。一方、国がこれまでに整備した地下河川は全国で5施設で前例が少ない。国が技術的なノウハウを周知したり、施工中の地山の変形を把握できるモニタリング手法を定めたりして、工事を安全に進められるようにする。
地方自治体は河川事業でシールド工事を行った実績が少なく、設計や施工の経験を持つ技術職員が不足している。国が相談窓口の設置や研修の実施を通じて、技術者を育てる環境を整える。整備を進める際には、国が技術的・人的に支援する体制も検討する。
地下空間を有効に活用するため、他の公共事業と共同で施設を整備する必要性も示した。鉄道の車両基地の地下を活用した遊水池や、地下河川と下水管を一体化した貯留施設の整備を検討する。河川周辺だけでなく、市街地にある地下空間の活用も提言。廃止される地下駐車場などを改修し、貯留施設に転用できるようにする。
地下構造物の施工費の縮減を優先した結果、維持管理の手間がかかる構造になってしまい、トータルコストがかさむ事例が多い点も課題に指摘した。施工や維持管理の効率を高めるための基準を国で定め、費用負担を減らせるようにする。
地下空間は道路や鉄道など幅広い用途に活用される。これらは地表に近い部分から整備されていくため、深度が深くなる後発の事業ほど整備費や維持費が高くなってしまう傾向がある。各河川の地下空間を計画的に活用できるよう、河川管理者が利用ルールを定めるようにする。まずはモデル河川を選定し、ゾーニングを検討する。
国交省有識者会議/河川地下空間を活用した水害対策で提言案、安全施工や技術者確保へ
- Published
- 2024/05/28 22:00 (JST)
© 日刊建設工業新聞社