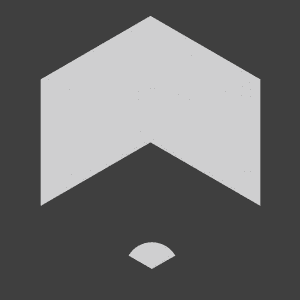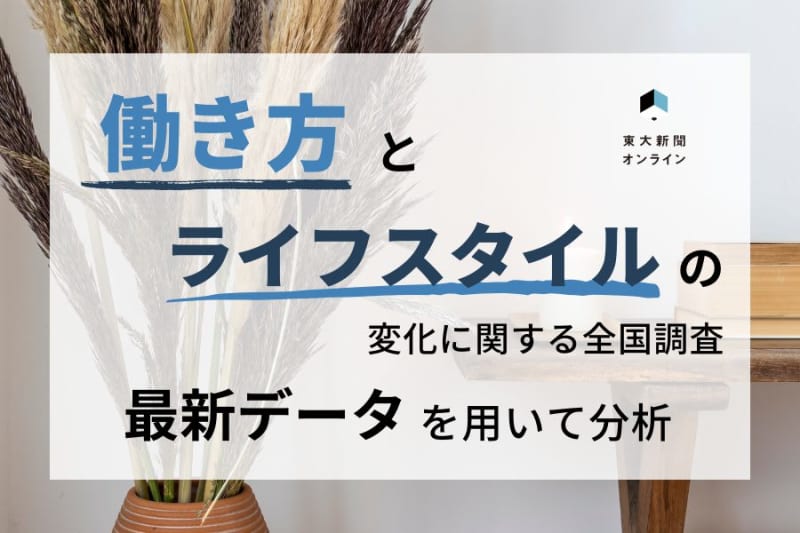
石田浩特別教授(東大社会科学研究所)らの研究グループは、「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査」の2023年のデータを用いた分析結果を報告した。同調査は07年より毎年実施され、社会構造や経済の変動が個人の生活に与える影響を解明することを目的としている。
2000年代から現在にかけて、個人のレベルで行動や意識の変化を追跡している研究は少ない。今回の研究では同一の集団に対して繰り返し調査を行う手法を用いることで、高い信頼性の実現と適切な変化の追跡を可能にした。
調査データは、①幸福に対する考え方とその関連要因、②時間に追われていると感じやすい人の特徴、③希望する結婚・出産年齢、④希望する介護形態という4つの観点から分析された。
現在の幸福度を1から10の10段階で評価してもらったところ、6以上と回答した人が全体の76%を占めた。幸福度の3大決定要因は経済的豊かさ、主観的健康度、社会的繋がりであった。将来のより大きな幸福のために現在の幸福を犠牲にできるかという問いに対しては、上記3要素を含む社会経済的資源を持っている人の方が寛容な回答をした。
続いて、普段どれほど急いでいるか、「いつも」「ときどき」「まったくない」の選択肢を提示して質問した。男女別に集計したところ、男性よりも女性の方が「いつも」の回答割合が高く、「まったくない」の割合が低い結果となった。加えて、時間に追われる感覚と生活時間の多くを占める睡眠・労働・家事時間との関連を検証した。男女ともに1日当たりの睡眠時間との関連は薄かった一方、月当たりの労働時間が長いほど普段急いでいると感じやすい傾向にあった。女性は平日の家事時間の長さとも関連が見られたが、男性は明確な関連は確認できなかった。性別役割分業の規範が依然定着している中、女性の社会進出が進んでいることが要因として考えられる。今後男性の家事参加が進めば女性と同様のリスクが高まる可能性がある。
希望する結婚・出産時期の回答傾向は07年と23年でほとんど変化は見られなかった。他方で、実際の平均初婚年齢や第1子出産年齢は遅くなっており、理想と現実の隔たりが拡大していることが示唆される。07年時点での希望結婚時期が現時点で実現した人の割合は男性で約3割、女性で約4割であった。男性は経済的な余裕があること、女性は年齢が若いことが実現の要因となっており、ジェンダー間の差異が見受けられた。07年時点での希望出産時期が現時点で実現した人の割合は男女ともに約15%であったが、実現の明確な要因は見出せなかった。
希望する介護施設は全体の過半数が「介護施設や老人ホーム」、続いて「自宅」、希望する介護者は全体の約7割が「介護職等の専門家」、約2割が「配偶者」と回答した。男性は「自宅」や「配偶者」、女性は「介護施設や老人ホーム」や「介護職等の専門家」を希望する割合が高かった。年代別では、年齢が高いほど「自宅」での介護を希望する傾向にあった。20代・50代は30代・40代と比較して「配偶者」による介護を希望する人の割合が高かった。
少子高齢化や経済変動などの社会的要因による個人の生活への影響に関心が高まる中、本研究は今後の政策議論を深める知見を提供すると期待される。
The post 「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査」最新データを用いて分析 first appeared on 東大新聞オンライン.