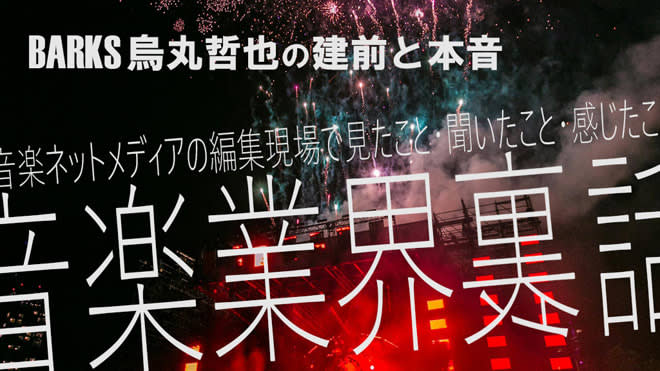
、音楽との出会いとその後のハマり具合には、タイミングやきっかけがあるという話をしたけれど、私の場合、思春期ならではの意固地で偏屈な価値観によって、好き嫌いをこじらせていた。音楽が好きと豪語していたけど、正しく言えば「好きな音楽が好き」なだけで、好きじゃないと思った音楽は聴かず嫌いのまま毛嫌いするという始末。こういうの、誰にでもあります…よね? あれ、ないのかな。
中高生の私にとって、3大嫌いなものは「カウベル」「ラッパ」「女性ボーカル」。理由は単純で「これはロックじゃない」と思っていたから。
カウベルは「ふざけている」と思った。「ドリフのコントで使う音じゃん」「あんなマヌケな音を入れるセンスが信じられない」と烏丸少年はご立腹。1970年代、頭でっかちになった田舎の中高生の話ですから、大目に見て欲しい話なんだけど、大学生になってからグランド・ファンク・レイルロードの「アメリカン・バンド」で無事克服。
「ラッパ」はロックじゃないから嫌いだった。ブラス系を「ラッパ」と言っちゃう時点でお察しなんですが、一時期は海上自衛隊基地内の官舎で育ったため、起床ラッパが早朝に鳴っていたことも深層心理に作用していたかもしれない。ブラスバンドや管弦楽・吹奏楽系のサークルを見ているとロックとは無縁にみえたから、ロックにもブラスは完全に不要と思った。大好きなピンク・フロイドやキング・クリムゾンにブラスが多用されていることに気付きもせず。ずいぶん後になって『狂気』や『炎』などで聴いていたゴリゴリカッコいいあのフレーズがサックスであることを認知し、あっさり克服。
そして女性ボーカルを毛嫌いしていたのは「ロックは男のもの」と思ってたから。多様性が叫ばれジェンダーレスのこの時代にありえない発言ですが、1970年代のこじらせ少年の矮小な価値観ゆえご容赦を。そうは言え、スージー・クワトロは大好きだったし、ザ・ランナウェイズが出てきた時は鳥肌立ったんだけど。
ただ、この女性ボーカル嫌いってのが意外と根深く、1990年代のJ-POP全盛でも克服せず。でも2000年代に入ってから、じわじわと女性ボーカルに惹かれ始め、気付けば自分のiPodは邦楽女性ボーカルの楽曲だらけになった。反動がエグい。遅まきながらEvery Little Thingから始まって、the brilliant green~Tommy february6 & Tommy heavenly6とかGIRL NEXT DOOR、mihimaru GT、Do As Infinity、moumoon、Sweet Vacationといったバンド/ユニット系から、aikoとかJUJUとかBONNIE PINK、倖田來未、BoAやら、とにかく女性ボーカルが好き好きおじさんに大変貌した。hiro:nとかI-lulu、珠妃、和紗、mink、KOTO、BRIGHT、SunMin、カミタミカ、まきちゃんぐ、塩ノ谷早耶香…大好きだったなあ。毎日聴いていたなあ。
もちろんハードなやつも聴いてた。BAND-MAIDは渋谷Eggmanで初めて観てその場で『MAID IN JAPAN』を買って聴き込んでいたし、DOLL$BOXXや黒崎真音やALTIMAやMay'nあたりもヘビロテしてた。上木彩矢も好き。Seventh Tarz Armstrongも聴いてたなあ。きゃりーぱみゅぱみゅはもちろん、なっちゃんPEAKもヘビロテしてた。JASMINE三昧、當山みれい三昧の時期もあった。
今思うと、ゴリゴリメタル好きを自認していた大学時代、オジーの『Bark at the Moon』をダビングしていた90分テープのB面は松田聖子の『風立ちぬ』だったし、そもそも1980年代はWink好きだった。1990年代初頭はjaco-necoも大好きで、2000年代になったらt.A.T.uをよく聴いていたから、本当は女性ボーカルは最初から大好きだったのかもしれない。強引に「嫌い」というカテゴリーを設けておくことで、音楽人としてキャラの立った個性とアイデンティティを演出したかっただけかもしれない。髪も長くメタル丸出しの格好だったから、それに似合う自分になろうとしていたのか?
こと思春期の頃の「音楽」は、自分の価値観を見定めてそれを育んでいくために最適な「背伸びのアイテム」でもあったから、無理矢理にでも「自分というキャラ」を当時の美意識で作る作業をしていた気がする。でもそれが自分の人生観や美学の最初の一滴となったのかもしれない、とも思う。素直なのかひねくれているのか、今でもそれはわからない。

文◎BARKS 烏丸哲也
