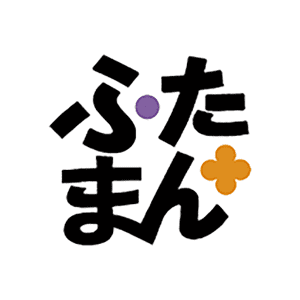昭和の時代、お茶の間を湧かせたテレビ番組の1つに「大映ドラマ」がある。大映ドラマといえば当時社会問題であった若者の非行をテーマにした内容が多く、今では考えられないような大立ち回りやセリフが特長だった。
なかでも1987年10月からフジテレビ系列で放送された『プロゴルファー祈子』は、いろいろな意味で話題になった作品だ。今回はそんな『プロゴルファー祈子』がどのようなドラマだったのか、あらためて振り返りたい。
■これぞ大映ドラマ!初回から怒涛の展開
『プロゴルファー祈子』は、女子プロゴルファーの主人公が波乱万丈に満ちた人生を送る物語だ。主人公の神島祈子(れいこ)を演じたのは、約5000人ものオーディションで選ばれた安永亜衣さん。その父親である神島友平役を岡本富士太さん、兄・徹役を沢向要士さん、そして折子の幼馴染である野上信也役を風見しんご(当時は慎吾)さんが演じた。
『プロゴルファー祈子』は初回からストーリー展開が激しい。そもそも祈子という名前は“礼子(祈子)”という字を父が出生届で書き間違えたためだ。もう、このネーミングからして大映ドラマの香りがプンプンだ。
祈子は会社を経営する友平一家の娘であり、裕福に暮らしていた。しかし15歳のある日、幼馴染の信也が打ったゴルフボールが祈子の胸に当たり重症を負ってしまう。それを見た兄・徹は信也のせいで祈子が死んだと思い、怒りのあまりゴルフクラブで信也を殴りつけて失踪。その後、父も行方不明となり、後日遺体となって発見される。世間から白い目で見られるようになった祈子は非行に走り、18歳で信也と再会するのであった。
ボールが胸に当たり気を失っている祈子のそばで、怒り狂って信也をゴルフクラブで殴る兄の徹。いや、それよりまず祈子の救命処置をしようよ……と言いたくなるが、このいろいろとあり得ない展開が大映ドラマの醍醐味なのだ。
■ただのプロゴルファーじゃない…5番アイアンを背負って敵と立ち向かう!
『プロゴルファー祈子』は、祈子が女子プロゴルファーとして成長していく姿も見どころではあったが、祈子がゴルフクラブを武器に敵を倒す姿も印象的だった。
非行に走った祈子の姿は、サイドポニーテールのヘアスタイルに青色ベースの濃いアイメイク。そしてなんといっても特徴的なのが、背負った“5番アイアン”。憎き敵が現れた際にはそのアイアンを武器にし、やっつけていくのだ。
ただしアイアンはただ振り回すだけでなく、戦闘スタイルにはかなりインパクトがある。時に祈子は敵の女番長とゴルフクラブを手にタイマンを張る。またある時は火のついたゴルフボールを5番アイアンで相手に向けて打ち、炎を使って攻撃している。
背中にアイアンを背負って啖呵を切る祈子はカッコいいが、5番アイアンは思ったより長いため、歩くたびにどこかにぶつかりそうで心配になってしまう……。
■熱いセリフ、結ばれない恋愛、父の死の真相…ドロドロがてんこ盛り
『プロゴルファー祈子』は大映ドラマの醍醐味である“ドロドロ展開”がてんこ盛りのドラマだった。
まずは謎めいた父の失踪、そして遺体発見。父の死は自殺に見せかけた殺人であり、その犯人と格闘する祈子の姿も見逃せない。
また祈子の兄である徹は、後日祈子とは血縁関係がないことが判明する。もともと祈子に対し妹以上の感情を持っていたこともあり、徹は祈子の幼馴染である信也と恋敵になっていく。こうした“実は赤の他人だった兄妹の恋愛”も、大映ドラマお約束の展開だろう。
そして本作品には、大映ドラマならではのびっくりするような展開や、熱いセリフが次々に登場する。
たとえば、第2話「ああ 私の敵は兄!?」では、祈子と信也が埠頭で話していると不良グループがバイクでやってくる。すると危険を感じた祈子は信也とともに海にダイブするのだ。
洋服のまま海にダイブするなど通常では考えられないが、そんなときに信也は「僕はもう二度とキミを離さないよ!」と熱いセリフを口にしている。その後、不良たちに茶化され、クロール泳ぎで不良のもとへ戻る祈子……。今、見返してみるとツッコミどころ満載のシーンが多いのも本作の魅力なのだ。
『プロゴルファー祈子』はこれぞ大映ドラマの代表格!という作品であり、非行少女がプロゴルファーとして成長するという、ちょっとユニークなストーリーが魅力だった。
当時視聴していた人に、懐かしさを感じてもらえただろうか。ゴルフクラブで戦うような行為は絶対にマネをしてはいけないが、昔はこうした波乱万丈なドラマが人気だったのも覚えておきたい。
ちなみに『プロゴルファー祈子』は現在のところ再放送される様子はなく、動画サイトでも配信されていない。“THE 昭和”といった作品が見られなくなるのは残念だが、当時見た人々の記憶には深く刻まれていることだろう。